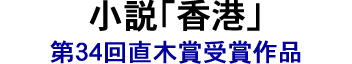|
第一章 自由の虜(1)
その1
彼は追われていた。
逃げることがいまの場合、彼の唯一の目的である。
なぜ自分は追われているのか、
なぜ自分は逃げなければならぬのか。
それを反問するだけの余裕はなかった。
原因はある。
煎じつめていえば、
地上にしか住む世界を持たない人間どもの闘いに敗れたのだ。
人を殺したのでもなければ人の財を奪ったのでもない人間が
たえず何者かに追われながら生きるというのが
戦後台湾の現実であってみれば、
生きのびるためには考えることよりも
逃げ足の早いことがまず第一の条件である。
この条件だけはどうやら生まれながらに備わっているらしい。
ところが逃げる先のことになると、
てんで方向感覚がなかった。
台湾島内では汽車があれば汽車に、
トラックがあればトラックにとび乗った。
ようやくのことで台湾から離れる機帆船に潜り込み、
生命からがら厦門へたどりついた彼が、
厦門を離れる時は機上の人になっていた。
一九四九年の初夏、南京決戦を前にして
逃げ腰になった国民党が台湾へ移動しはじめた頃のことである。
たしかこの飛行機の行先は香港のはずだ。
が、離陸した飛行機が空に向かってぐんぐん上昇しはじめると、
ただそれだけの理由で彼はすっかり愉快になった。
肩にかかっている空気の圧力が、
上空にのぼればのぼるほど軽くなっていくようだった。
もっと上がれ、そしてなにもかも忘れてしまえ。
…あれから何時間か経っているのだが、
頼春木(らいしゅんぼく)はまだ完全に夢から覚めきっていない。
プロペラの音が相変わらず耳元でガンガン鳴りつづけている。
坐っていながら、だんだんと気が遠くなっていくような気がする。
と、その時、彼の前に黙って坐っていた男が
突然大きな口をあけてアハハハ……と笑った。
「さっき君はよほど驚いたようだね」
そう言われた瞬間に、春木は我に帰った。
それとほとんど同時にいままでの経過が記憶の中に蘇ってきた。
驚きはまだ生々しく、
血液の中を駆けめぐっている。
いま、彼が腰をおろしているのは
九竜半島の飛行場に近い場末の貧民窟にある
上海人の旗亭の中である。
旗亭といっても露店に少し毛の生えた、
きたならしい掘立小屋で、
油のにじんだ卓が三つばかり並んでいるだけで、
彼と彼の前に陣取った男の二人以外に客はいなかった。
店先に饅頭を蒸す、大きな蒸籠があって、
そこからシュンシュンと蒸気の立つ音が聞こえてくるのが、
エンジンの響きを連想させたに違いない。
旗亭の中には電灯の代りに、
石油ランプが天井からぶらさがっている。
クローム・メッキされた新式のランプは
石油がガス化されて小さな太陽のように激しく燃えるので、
狭い部屋の中を真昼のように明るく照らし出している。
その明りの下で見ると、
自分の前に肱をついた男の痩せて骨ばった顔が
妙に黄色味を帯びている。
ただでさえ貧相な風貌をしているのに、
身につけた短袖のシャツが疲れきっているので、
吹けば飛ぶような、つまらない男に見える。
この男を最後の頼りに自分ははるばる台湾からやって来たのだ。
この男があの李明徴(りめいちょう)なのだ。
そう自分に言いきかせようとするだけでも、
火が消えたような淋しさがこみ上げてくるのだった。
官憲に追跡されて、台湾じゅうを逃げまわっていた春木が、
転々と居所をかえた末に、
ある友人の所へ転がり込んだのはつい一月ほど前のことである。
仲間たちが次々と捕えられては投獄されていたので、
その友人は彼に香港へ渡ることをすすめてくれた。
香港には自分の友達で李明徴という男が住んでいる。
かなり手広く商売をやっていて、大邸宅を構え、
自家用車も持っているくらいだから、きっと助けてくれるだろう。
そう言って、友人は紹介状を書いてくれたうえに、
自分で基隆(キールン)港まで出かけて行って
香港へ渡るという機帆船に交渉してくれたのである。
ところが高い闇の船賃を払って乗り込んだ船は、
香港へ行かずに真直ぐ厦門へ直航した。
厦門には用事がないので、
港に着いても船中にがんばっていると
そこへいきなり家財道具をもった避難民が乗り込んできた。
船は内戦を避けて台湾へ渡る難民を乗せてまた台湾へ戻るという。
こうなると、どんなに騒いだところで勝負は明らかである。
結局彼はカバンを一つ手にさげて
厦門の街へ上陸するよりほかなかった。
二か月に及ぶ逃避行で、いまは身も心も疲れ果てている。
一時も早く目的地にたどりついて、
ゆっくりした気持で睡眠をとりたかった。
懐中にはいくらも金がなかったが、
香港に着きさえすればどうにかなるだろう、
と一途に思いつめて、
厦門から香港行き飛行機の切符を買ったのである。
|