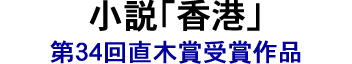|
第四章 揺銭樹 - かねのなる木 -(2)
その3
「だってちっともお便りが来ないじゃないの。
いくら国に財産があるといったって、
たまには送金ぐらいしてやるものよ」
「前にはよく手紙をよこしたけれど、
返事をやらないものだから、もう諦めているよ。
送金するといったって、たいした収入があるわけでなし」
「でもたとえ五十ドルだっていいわ。
気持の間題ですもの。
女ってそんなちょっとした心やりでもとても嬉しがるものよ」
春木が笑って相手にしないでいると、
リリは自分で町に出かけて行って、
女ものの長衫の衣料や
子供のカウボーイのズボンなどを買ってきて、
台湾へ送ると言ってきかない。
その心理が春木には解しかねるのだが、
あるいは彼の情婦となって
彼を独り占めしていることに対する罪ほろぼしのつもりだろうか。
春木はだまってリリのするに任せるよりほかなかった。
老李の予言したとおり、一週間もすると、
また一万箱の追加注文がカサブランカから入ってきた。
「どうして商人はこう莫迦なんだろうな」
と春木が首をかしげていると、
「いや、最初のあの五百箱が効いているんだよ。
僕のほうであと一万箱在荷があるが、
同じカサブランカのもう一軒の店から照会があるが、
できればいままでの取引先である
あなたの店に売りたいと言ってやったんだ。
値段が相場より少しばかり安いから、
他の店に買われて相場を崩されるより、
独り占めしようと思ったまでのことさ」
「じゃ早いところ荷造りをしないと駄目だ。
この間の船はもうどこまで行っただろうか」
「ちょうど、今日サイゴンに入ったところだ」
と老李は即座に答えた。
気にしていないふうを装っているが、
老李は何事もちゃんと計算に入れているに違いない。
「わざと船足の遅い船を選んだから、
カサブランカに着くまでまだ二ヶ月ぐらいかかるよ、
あちらこちら小さな港に寄って行くからね」
「で、今度もまた台湾に注文するつもりか」
「いや、もう面倒臭いから現地で集めよう。
どうせもう後は野となれ山となれだから、
黴(かび)のきた古い茶でも何でもかまわないよ。
員数さえ揃えばいいんだ」
老李は自ら事務所へ出て来ると、
茶のブローカーを総動員して
香港じゅうの粗悪茶を集めさせた。
しかし、短い期間に一万箱かき集めるのは
容易なことではなかったので、
たりない分は空箱だけ買ってきて、
石ころや新聞紙を詰め込んで重量を調節し、
とにかく、所要の数量だけ作りあげた。
ちょうどアフリカに行く船の期日に間に合わせるために、
春木は四、五日の間、 目のまわるほど忙しい思いをしたが、
ようやく船積みが終わって、事務所へ帰ると、
老李が笑顔で彼を迎えた。
「や、ご苦労さん。
今夜はひとつ君のために慰労会をやるから一緒に行こう」
タクシーに乗ってホテルへ戻ると、老李の部屋に客が来ていた。
それは日本との密貿易に従事しているあの洪添財だった。
添財は春木を覚えていたばかりでなく、
狸の置物のような顔を綻ばせて、その手を握った。
「いつお帰りになったのですか?」
「十日ほど前です」
「日本のほうの景気はどうです?」
「最近は相当やりにくくなりました。
密輸がますます大組織になったのと、
アメリカから直接のルートが開けたので、
大資本でないと駄目です。
それで、李さんにも一肌脱いでもらって、
ひとつ大々的にやろうというわけです」
「いや、それはこっちの言うことだ」
と老李が脇から口を出した。
三人はそれから表に待たせてある添財のビックに乗って
石塘咀にある金陵酒家へ夕飯を食べに出かけた。
シートの幅の広いビックの車は
三人の男が坐ってもゆったりしている。
こんな車に乗っていると、
共産主義は対岸の火事ぐらいにしか見えないのは無理もない。
「奥さんには久しく会いませんが、お元気ですか?」
「ええ、まあ、宜しくやっていますよ」
「でもいつも留守にしていちゃ心配でしょう?」
「なあに、香港の女は麻雀を一組与えておけば、
男がいなくてもいいんですよ。
その点じゃ日本の女よりかえって扱いやすい」
「心配なのは、旦那さんのほうより奥さんのほうじゃないか、
ハハハハ…」
老李が大きな声で笑った。
その晩は老李が主人役をつとめた。
食事が終わるとキャバレーへ回った。
どこのキャバレーでも添財は顔がきいている。
女たちがわッときて、この肥っちょの小男を取り囲んだ。
老李は仲間はずれにされ、
ひとりでぼんやりソファにもたれかかって
暗い照明の中で踊っている人々を眺めている。
もうもうとした煙草の煙で、
シャンデリアのまわりがぽっとかすんで見える。
「なんだ、お前たち。
俺のまわりにばかり寄って来ないで、
この老班をもてなさないか。
俺なんかよりこの李先生のほうがずっとでかい鴨だぞ」
添財が冗談を言うと、
二、三人のダンサーがようやく老李のそばへ寄って来た。
「李先生ってとてもおとなしい方ね」
とダンサーのひとりが言った。
「人は見かけによらんぞ」と添財が怒鳴った。
「李先生はどんなご商売?」といまひとりの女がきいた。
「さあ、どんな商売をしているように見えるかね」
「そうね。
南洋帰りの華僑だわ。
とてもお金持のようね、そうじゃない? 洪先生」
「お前はカンがいいぞ、
李先生はマレー半島に大きなゴム園を二つも持っている。
うまくだまして搾ったらうんと出て来るぞ」
「まあ」
と女たちは朗らかそうに笑いころげた。
「さ、踊りましょう」
「いや、僕は踊れないんだ」
老李はどんなにすすめられても
絶対にソファから立ち上がろうとしなかった。
春木や添財が女たちを抱いて、
早いリズムに乗って忙しそうに踊っているのを、
彼はゆうゆうと煙草をくゆらせながら眺めているばかりである。
十二時を過ぎると、
ホールの中は次から次へと入って来る客で
ますますいっぱいになった。
遊んでいるというよりは、
狂乱の限りを尽くしているような光景である。
赤や青と矢継ぎ早に照明がかわり、
そのたびに女たちの顔が妖しげな美しさを増してくる。
どの女の着ている長衫もきらきらと光っており、
腰の線が流れるように動いている。
一時近くなってから、三人はキャバレーを出た。
暗い階段の踊り場を通る時、
老李は春木の肩を叩きながら言った。
「さっきの女たちは昼間見たら皆失望してしまいそうだね」
|