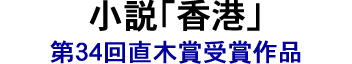| 第三章 海の砂漠(2)
その1
本格的な伊勢海老とりはその翌日から開始された。
金竜が有能な潜水夫であることを春木はたちどころに
認めざるを得なかった。
海中からぬっと現われるたびに、
彼は海老を手につかんでいる。
一時間ほど海中で仕事をすると、
今度はボートの上に上がって来て、
息もつかずに酒をぐいぐいとラッパ欽みにする。
野郎同士だからとはいえ全裸のまま
春木の前に坐り込んでひるむところがない。
「何年前だったかな、
基隆の近くの海岸で工事をしたことがあったが、
暑い時だからどの男も素っ裸だった。
ところが、そこにある日、
工事監督の嬶(かかあ)がやって来たんだ。
女気ひとつなかった所へさ。
すると実に不思議な現象が起こった。
翌日、見ると二百人ほどいた男が
全部パンツを穿いて仕事をしているんだ。
誰に命令されたというわけでもないのにさ。
女の威力は全く凄いもんだよ。ハハハ…」
「君もパンツを穿いた組か」
「ああ、穿いたとも。
俺たちはな、ふだん裸が多いだろう。
だから服を着ている時のほうがかえって感じが出るんだ」
「ヘエ、そうかな」
「たとえばだ、女の素裸よりは
ズロースの桃色がちらちらするほうがええじゃないか。
今日はもうひとふんばりして、女のズロースを見に行こうぜ」
そう言うと彼はふたたびボートから海中へ下りた。
用意してきた魚籠が半分ほどになったのは、
もう太陽が海の中に姿をかくしてからであった。
暗闇の中で魚籠を手さぐりでつかみあげると、
金竜は一日の疲れも忘れて、
「うむ。五十斤はたっぷりあるな。
そろそろ引き揚げるか」
まだ太陽の温みのほのかにのこった砂浜には人の気配はなく、
別荘に点々と電灯がともりはじめている。
夜に入ると、星が空いっぱいに輝き出したが、
二人は香港仔への道を急ぐのに我を忘れていた。
喜びが温かく春木の胸を包んだ。
この調子ならその日の市況によって多少の出入りがあるにしても
一日に百ドル近い収入がある。
酒代、船の損料、食事費などを差し引いても
かなりの金が手元に残る勘定だ。
月に何回か休養をとるとしても、夏じゅう働けば…
と空想するだけでも張りが出てくる。
ところが、彼の胸算用がまだ終わらないうちに、
彼の夢は早くも破れてしまった。
海老を売り払うと金竜は売上げ代金をごっそり
自分の懐中にしまい込んでしまったのである。
春木はあきれはててものが言えなかった。
自分にも当然利益の半分を要求する権利があるはすだ。
プランは自分が立てたものだし、
金竜が水に潜っている間も自分は一緒になって働いている。
ところが、金竜は分け前をよこさないばかりでなく、
次の日も次の日も、金のある間決して海へ行こうとしなかった。
曖昧宿に女を呼んで夜を明かし、
昼間は映画を見に行くのでなければ、
朝から酒びたしになっている。
直接、自分の懐中とつながっていることだけに、
春木はそれが不服でたまらない。
「毎日、やれと言わんが、
少し精を出して舟ぐらい自分たちで買おうじゃないか。
借賃を倹約するだけでも、どんなにいいかわからんよ」
「魚じゃあるまいし、そういつも海の中に入ってたまるものか」
「でも夏の間しかできない仕事だから、
稼げる間に冬の用意をしておかんと、あとでこたえるぜ」
「なあに。その時はまたその時で考えるさ。
いらん心配をすると頭が禿げるぞ」
図体が大きいだけで、たいした知恵もなさそうな男である。
それを見越した上でつけ込んだつもりだったが、
歯が立たないどころか金竜と一緒にいると
逆に肉体的な圧迫を感じてたじたじとなってしまう。
金竜のほうでは彼をせいぜい
臨時傭いの船頭としか思っていない証拠に、
時々、気が向いた時に五ドルか十ドルくれるていどで、
あとは主人面をして、
一緒に飲み食いをした時の金を払ってくれるだけである。
喧嘩しようにもはじめから勝負のわかった相手だけに、
春木は憂欝になった。
憂欝の原因がはっきりしているだけに、
ますます憂欝の度が深まっていった。 |