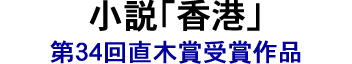| 第三章 海の砂漠(1)
その1
カポックの黄色い花がまるで木の実のようにぼたぼたと落ちると、
紫色のライラックが咲きはじめる。
もう春だ。
雪の降らないこの香港では膚をさす氷のような西北風が
冬じゅう吹きまくるが、
風の向きが変わって、海のほうから暖かい東南風が
そよそよとそよぎはじめると、急に陽気が暖かくなる。
公園の樹はいっせいにうす緑の芽を吹き出し、
芝生はまばゆいくらい美しさを増す。
頼春木は山の中腹にあるこの公園のベンチに腰を下ろし、
はるか下方を通る汽船を眺めている。
九竜半島と香港島に挟まれた海峡は海も深く、
そのまま天然の良港を形成し、眺めの美しいことでも、
また出入りの船の多いことでも広く知られている。
公園の“ゆうかり”の樹の下からは、
この港が手にとるように見渡される。
もう三時間以上もここに坐っているが、日没が遅くなったので、
陽はまだ高い。
この三時間の間に、三隻の汽船が出港し、
四隻の汽船が入港してきた。
そのほかに澳門(マカオ)行きの小型船や
戎克船(ジャンク)などが出たり入ったりしたが、
それは勘定に入れていない。
しかし、こうしてぼんやりと無思想に、
風景に見惚れることは確かにいい時間潰しの方法だ。
この方法を彼に教えたのは周大鵬だった。
昨年の暮のあの寒い時に、女と密会に行くと公言しながら、
その実、大鵬はこっそりこの公園へ来て
夜遅くまで、出船入船を見ていた。
長い間、大鵬はそのことをひたかくしにかくしていたが、
ある時、話の調子で、
春木が問いつめると、とうとう本音を吐いた。
それによると、最初の頃、女は愛想よく彼を迎え、
飯をふるまってくれたりしたが、
それは彼が彼女の旦那の洪添財の友人であるという
一線を越えたものではなかった。
ところがその間の区別のつかない大鵬がそれをいいことに
しょっちゅう訪ねて行くので、
とうとう居留守を使うようになった。
邸宅の門前には自家用のビックが止まっているのだから、
いないはずはないと思いながら、
ある時、近くにある学校の運動場でがんばっていると、
やがて女が門前に現われ
自動車に乗ってどこかへ出かけて行くのが見えた。
大鵬はひどく自尊心を傷つけられ、
それ以来、女の所へは行かず、
かといって自分の失敗を喋るのはいかにも情なかったので、
一週間に一度はここへ来て、
ひたすら添財が日本から帰って来るのを待ったのである。
添財さえ帰って来れば、金を出してもらって、
密輸船に乗って日本へ渡るつもりでいたのだ。
ところが帰って来た添財にその申込みをすると、
一言のもとにはねつけられた。
期待が大きかっただけに、大鵬の受けた打撃は深刻だった。
それ以来、彼は二度と
ふたたび公園へ来なくなってしまったのである。
だが、その代りに春木が時々、ここへ足を運ぶようになった。
他人のために一日に八粁の道を水汲みに行って、
それでようやく飢えを充たす生活には何の希望もない。
牢獄につながれたのなら、まだいつか刑期が終わって
晴れの身になれるのだという夢があるが、
この青空の下における牢獄は
永遠に果てる日があるとは思われない。
当然のことながら、春木の考えが少しずつ変わりはじめた。
老李のようにユダヤ人に徹底したいとは思わないまでも、
チャンスを追って、浮かび上がる努力をする以外に
救いがないことは明らかだった。
(我々は誰からも保証されずに
自分のカで生きて行かなければならないのだ。
我々に与えられた自由は、それは滅亡する自由、
餓死する自由、自殺する自由、
およそ人間として失格せざるを得ないような種類の自由なのだ。
金だけだ。
金だけがあてになる唯一のものだ)
いつか老李が怒り狂って吐いた言葉が
そのまま脳裏に刻み込まれて忘れられない。
のみならず、それがしだいに真実感をもって
迫って来るではないか。
もっとも春木は大鵬のように
幸運がいつかは必ず訪れてくるとは考えていない。
幸運とは自分でつかむものだ。
そのためには常々眼を光らしていなければならないのだ。
だから渡し船に乗って香港へ渡った時は、
同じ人込みの中を歩いても、
大鵬のように自分の身につけるものや、
金があればすぐにも手に入れたいものに眼をくれることはない。
たとえば、グロスター・ホテルのアーケードを通る時、
彼は冷房器具や電気冷蔵庫を売る店の前には止まらずに、
きまったように花屋の前に立ち止まる。
花屋のウインドから覗くとグラジオラスやパンジーや
スイートピーなどが店いっぱいに並んでいる。
だが、彼が見惚れるのは、
ウインドの上の段に飾られているカトレアである。
いつかその値段をきいたら、
一鉢で三百ドルと言われてあっけにとられた。
こんなとてつもない値段では誰が買うものかと思っていると、
ちょうどそこへ一人の二十歳ぐらいのハイカラな服装をした女が、
同年輩ぐらいの青年を連れて入って来て、
「これいくら」と聞いた。
「はい三百ドルでございます」と店員が答えると、
「そう、じゃあこれをもらうわ」と言って、
バッグをぱっと開いた。
そのハンドバッグの中には百ドル紙幣がぎっしり詰まっており、
女はその中から三枚抜いて店員に渡した。
「お届けいたしましょうか」と店員がきくと、
「いいわ、あなたこれを持ちなさいよ」と傍にいる青年に言った。
青年はたぶん彼女の恋人か、ボーイ・フレンドなのであろう。
女の命ずるままにカトレアの鉢を持ちあげると、
そのあとからついてそそくさと
自家用車のとまっている街路へ出て行った。
それ以来、春木は香港へ出るたびに必ず花屋の前を通った。
よく注意して見ると、洋蘭の売行きはなかなかばかにならない。
薬九層倍というが、洋蘭はそれどころではない。
農業学校時代に日本人の先生について
洋蘭の栽培をしたことがあるが、
雪や霜の多い日本と違って熱帯地方では洋蘭は温室の必要もなく、
栽培もいたって簡単である。
どこかに土地を借りて洋蘭屋をやれば、金になるのになあ、
と考えるのだが、
しかし、何を始めるにしても
ある程度の資本がなくては話にならない。
結局出るものは溜息ばかりだ。
|