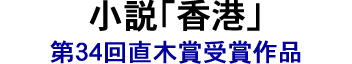| 第二章 密輸船(3)
その3
こうして何時間かが経っていった。
対岸の明りは夜に入ると、数がふえたが、
夜がふけるにしたがって、しだいにまた消えていった。
もう何時になっただろう。
時計を持っていないので、大鵬自身にもわからないはずだ。
彼はベンチから腰を上げ、暗い公園の道を、
もと来た方向へ向かって歩きはじめた。
冷たい石段には風のほか誰もいなかった。
二、三分遅れて、バラックにたどりついた春木が聞いた。
「ずいぶん帰りが遅いな。
あんまり寒くてやりきれんから、
いま、腹ごしらえに行ってきたところだ。
今日はどうだった?」
「どうしても今日は、泊まっていけと言ってきかないんだ。
いくらなんでもそれじゃあんまりだから断わると、
あなたは冷淡だって言うんだ。
ほんとにいつか君の言ったように、女は怖ろしいもんだね、
つくづくそう思ったよ」
「そうか」と春木がもっともらしい顔をすると、
「最近は僕も女に厭気がさしてきた。
女なんて知らないうちが花だな。
もう香港も厭になったから、今度、洪の奴が帰って来たら、
日本へ行かせてもらうことにするよ」
さすがの春木も、本当のことをあばくだけの勇気が失せてしまった。
大鵬はしんみりした調子で言った。
「この頃は船を見ていると、
どれもこれも日本へ行く船のように見えてしょうがないんだ。
洪の奴が羨ましいよ。
同じ女といつも一緒にいると、
どんな美人だってあきあきするからな」
その後、大鵬は女の家に行くのをやめて、
ひたすら洪財の到来を待った。
一日に八粁の道を走ると、冬でも玉のような汗が流れる。
その汗を手で拭いながら、彼は言った。
「奴が帰ってきたら、
少し支度金をもらって服や靴など必要品を買おう。
東京は物資欠乏で外国製品などとても高いそうだからね。
そしたら、僕のお古でもよかったら、皆君に払い下げるよ」
やがてクリスマスが来た。
街のショー・ウインドに赤や青の照明が点滅し、
大きな包を持った西洋人が行き来した。
だが、このダイアモンド・ヒルには寒い風が吹くだけで、
サンタクロースの姿は見えそうもない。
ある日、対岸へ出かけて行った大鵬が、吉報をもって帰ってきた。
「明日、奴が着くそうだ」
彼はバラックの中を、急ぎ足で行ったり、来たりしながら言った。
「君も一絡に迎えに行かないか?」
「いや、またの機会にしよう」
「でもせっかくの機会を惜しいじゃないか。
この前の時みたいにガツガツしないで、
少し控え目に食ったら大丈夫だよ。
それに顔をつないでおくほうが将来のためにもなるしさ」
「君からよろしく言っておいてくれ」
「そりゃもちろん、頼まれなくたって、そのくらいのことは心得ているよ」
ところが、その翌日、大鵬はぶりぶり怒りながら帰ってきた。
感情をかくすことを知らない男だから、酒でも飲んだように、
首すじまで真赤にしている。
「俺あ、俺あ、親友と思っていた男から裏切られた。
見事に裏切られた。畜生奴!
少しばかりの小金を握ったとたんにすっかりのぼせやがって、
たかが密輸をやって、あぶく金を掴んだだけのことじゃないか。
それがよ、まるで天皇陛下にでもなったような面をしやがってさ」
「どうせそんなことだろうと思ったよ」
春木はべつに驚かなかった。
大鵬は続けた。
「人間なんてわからないものだ。
昔はあんな男じゃなかった。
俺と一絡に水汲みをしていた頃は、いつもいまに俺が偉くなったら、
貴様を助けてやろうと誓いあった仲だ。
金ができたとたんに気が狂ってしまいやがった」
「困った時には誰でもそんなことを言うさ。
人間は自分に都合の悪いことは
片っ端から忘れるようにできているんだ」
「そんなことがあるものか。
嘘と思うなら、俺を金持にしてみろ。
俺あ、君のためにだっていろんなことをしてやる。
小遣いもやるし、因ったことがあったら、相談にものってやる。
絶対に嘘は言わん。神様に誓ってもいい」
春木はほとんど笑い声がこみあがって来そうになるのを
辛うじて抑えた。
「いったいどうしたというのだ。
女のことでも感づかれたんじゃないのか?」
すると、一瞬、大鵬はびっくりして顔をあげた。
言葉に詰まってウウと稔った。
「俺がそんなへまなことをするものか」
「でも君があんまり逃げ腰になるから、
女が前後の見境もなく告げ口をしたかもしれん。女は怖いぜ」
「いや、そんなことは絶対にない。
俺あ、それほど要領の悪い男じゃない。
悪いのは洪の野郎だ。彼奴は悪党だ!」
いまにも泣き出しそうになりながら、
大鵬は叫びつづけた。
「金、金、金、金がなんだ。
金は天下の回り物じゃないか。悪党ばかり栄えるものか。
俺がいま貧乏だからといって、
絶対に金持にならんと誰が断言できるか。これを見ろ、これを」
彼はポケットから一枚の赤い紙切れをとり出して
春木の前につき出した。
それは香港の春と秋に定期的に行なわれる大競馬の馬券だった。
「この馬票(マアピユ)が一等に当たったら、
明日から俺あたちまち百万長者だ。
香港ドルの百ドルだぞ。
米ドル二十万ドルだぞ。
ビルディングを買って世界大漫遊をしてもまだおつりが来る。
この香港で誰か一人が必ず当たるんだから、
それが俺でないと誰が断言できるか」
毎日、水を運んで稼いだわずかな賃金の中から、
彼は自分の飢えを犠牲にして、
一枚ニドルもする馬券を買っていたのである。
毎期約二百万枚売れる馬券の中の、
わずか一枚に彼のすべての夢が託されているのだ。
海岸沿いに並んだ倉庫の中には山のように
シャム米が積み上げてある。
その中から一粒の米を選び出すような、
そんな確率にもなお絶望を感じない男。
今期、不幸にしてその選にもれても、来期、
来期が駄目なら、またその次と、
いつかきっとその幸運に恵まれると信じて疑わぬ男。
「それが俺でないと誰が断言できる!」
と気狂いのようになって大鵬は繰り返した。
それを聞くと、春木はもう我慢ができなかった。
泣いたつもりが、大きな声を立てて笑っていた。
笑ったとたんに涙が眼からほとばしり出た。
|