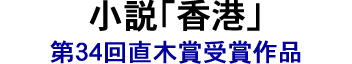| 第二章 密輸船(3)
その2
けれども紳士のいでたちをすることには
ある種の苦痛が伴うものである。
なぜならば、紳士らしくふるまわねばならぬからである。
まさか革靴をはいて、一時間近くかかって
渡し場まで歩くわけにはいかぬ。
渡し船の中は時間が短いのと、
靴の底がへらないから三等でもさしつかえないが、
そこまで行くバス代と渡し船の代を合わせると、
最低六十セントはかかる。
つまり紳士らしくふるまうためには、
彼は八粁の道を汗水垂らして天秤俸を担いだうえに、
その日一日飢えなければならないのだ。
こうした出血作戦が毎日続くことはもちろん不可能であった。
しかし、彼は辛抱強い男である。
だいたい一週間に一度ずつ、彼は海を渡って香港島へ出かけて行った。
大鵬の話によると洪夫人は山の中腹にある大邸宅が落成したので、
そちらへ転居したそうである。
車庫の前にはいつも四九年型のピックがとまっており、
銀色に塗り立てられた鉄の門には
「内有猛狗」の貼り札がしてある。
ライラックや紫陽花などの草花に埋められた庭園には、
小さな池があって、睡蓮が浮かんでいる。
その素晴らしいことを大鵬は夜遅く帰ってくると、
事細かに喋ってきかせる。
が、肝心の女のことはいっさいふれようとしない。
「どうだ。よろしくやっているらしいね」
春木が冷やかしても、彼はただ黙笑するだけで、
多くを語らないから二人の間がどんな具合に発展しているか、
さっぱり見当がつかなかった。
ところが、それからしばらくたつと、大鵬は急に鏡舌になった。
今日は彼女のピックに同乗して
リパルスト・ベイまでドライヴに行ったとか、
今日は皇后戯院に映画を見に行ったとか、
金陵酒家で食事を一緒にしたとか、夢のような話である。
「昔ダンサーをしていたのなら、あのほうの腕もたいしたものだろう」
春木が一言うと、大鵬は気の毒なほどあわててしまった。
「そんなこときくもんじゃないよ。いくら親友でもさ」
「自分ひとりで楽しまないで、少しは公開するものだ。
ちらりとしか見たことがないが、あの乳房はよかったぞ」
「品がないな」と大鵬は遮った。
「君と一緒に話していると、僕まで品がなくなってしまう」
しかし、大鵬の話には何となく不審な節がないでもなかった。
もし本当に女とぬきさしならない関係になっているとすれば、
彼がいつまでも同じ背広を着ているはずがない。
彼が貧乏していることを向うも承知なのだから、
いろいろと心尽くしのプレゼントをしてくれそうなものだ。
ある日、大鵬が背広を着込んで、いつものとおり出かけて行くと、
春木はその後から相手に気づかれないように、こっそりついて行った。
一方がバスの二階に上がるのを見届けてから、
一方が階下に乗り込んだ。
春木は大鵬と同じ渡し船に間に合わせるために、一等を奮発し、
香港島に着くと、柱のそばにかくれて、
相手の出て来るのを待って尾行した。
大鵬はゆっくりと街を歩いた。
流行の品々の並んだ有名店のショー・ウインドの前まで来ると、
立ち止まって長い間丹念に中を覗いた。
一足百ドル以上もするフローシャイムの靴や
英国仕立てのガウンやカシミヤのシャツなど、
貧乏人にはまるで縁のない紳士用品が飾ってある。
彼はその前に立って、心からそれを楽しむ様子である。
時計屋の前でもそうだったし、靴屋の前でもそうだった。
彼は冷やかしの客には見えないほど、熱心に見惚れていた。
それから、辻を横切ると、中央市場がある。
彼の姿がいきなりその中に消えたので、
春木があわてて後を追うと、
じめじめした廊下を入った所に公共便所があった。
老人がひとり便所の入口で塵紙を売っている。
しばらく待つと、大鵬が便所の奥から姿を現わした。
今度はデパートに入った。
デパートはちょうど大売出しの最中で、客が混雑をきわめている。
まだ時間の余裕があるとみえて、
大鵬はゆうゆうと人ごみをかきわけて歩いている。
煙草の道具ばかり売っている所に立ち止まる。
ガラス戸棚の中にダンヒルのパイプやロンソンのライターが
ずらりと並んでいるのを店員に取り出させる。
戸棚の上がそれらのものでいっぱいになった。
大鵬はなにやら喋ったが、急に笑顔をした。
生活に不自由のない紳士らしい笑顔である。
何か買うのかと思えば、そのまま戸棚を離れた。
その次は映画館だ。
ポスターや写真の張りつけてある所で、彼は何十分もねばっていた。
今週の番組はおろか、来週の映画の配役の名前から、
その服装まで全部暗記してしまえるほど長い時間である。
家を出てから彼がそこを離れるまでに
すでに三時間以上を経過している。
しかし、時間はまだたっぷりあるらしい。
冬の陽は暮れやすいとはいえ、まだ山の端にもかかっていない。
大鵬は時計塔を見上げた。
春木はいらいらしてきた。
すると、大鵬はまた歩き出した。
その次に止まったのは珈琲屋の前だった。
ぷーんと芳しい匂いが通りにまで漂っている。
彼はそこで人を待っているような恰好をしたが、
その実、いくどもいくども深呼吸をしているらしい。
狭い香港の繁華街では
もうこれ以上することはなにも残っていないはずだ。
やっとのことでそこを離れると、今度は銀行の建物の前を横切って、
公園へ登る坂道のほうへ出て行った。
いよいよこれから山頂の邸宅へ乗り込むのであろうか。
しかし、聖ジョン教会の前を通り、登山電車の駅を過ぎると、
大鵬はそのままヴィクトリア公園の中へ入ってしまった。
もうあたりはすっかり暗くなっている。
椰子の葉に冬の風がさらさらとなって、
ぞくぞくとするような寒さが
春木の身体の底から湧いてくるようだった。
公園の中にはほとんど人影もなかった。
大鵬はひとりベンチに腰をおろし、じっと海のほうを見つめている。
洪添財の邸から眺めるのと同じあの港の風景だ。
彼は誰かを待っているのかもしれない。
あの女が人目を忍んで、そっと会いに来るのかもしれない。
じっと頬杖をつきながら、思案気にしている彼は
何者かを待っている風情だ。
|