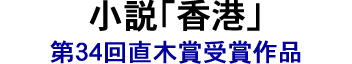| 第三章 海の砂漠(5)
その1
春木が張込み中の密探(刑事)に
いきなり両手をつかまえられたのは、
その翌日、
暖昧宿の戸口から寝呆け顔で出て行こうとした時である。
彼は少しもあわてなかった。
刑事が手錠をはめると、宿のまわりに人だかりがした。
彼は顔を上げてそれらの人々を見た。
人々の中にはリリの姿は見えない。
人知れぬ微笑がその顔に浮かんできた。
自分の持っていた金を一銭のこらず与えた時の、
彼女の驚いた表情を思い出したからである。
「さ、どいた、どいた」
人波をかきわけた密探は、タクシーをとめると、
春木を先に乗せ、自分もその脇に乗り込んだ。
警察の厄介になるのはこれが最初ではない。
物売りをしてつかまえられた時に比べると、
彼はずっと落ち着いていた。
というよりここへ来るのが彼の最終の目的ではなかっただろうか。
凶悪犯人と思われたのかどうか知らないが、
独房に入れられたのは有難かった。
鉄のべッドが片隅に置いてあって、
たぶん、DDTを撤いたのであろう、
白い粉が板の間にこぼれている。
狭いことは狭いが、
清潔で誰とも口をきかないですむのがとても気楽だった。
午後になると、鉄の格子があいた。
取調べだと思って出てみると、老李がそこへ来ている。
「いったいどうしたというんだ」
老李はとてもびっくりしているらしい。
しかし、老李の顔を見ても春木は少しも嬉しくなかった。
「どうもしやしないさ」
「でもさ、金竜を海におっぽり出したまま
一人で陸へあがったそうじゃないか」
「それがどうしたんだ」
「冗談じゃない。
そんなことをしてただですむと思っているのか、
金竜の奴、素っ裸で陸まで泳ぎついて、
海岸をうろうろしているところを警察に捕えられたそうだ。
警察で着るものを借りて帰って来てそんな話をするから、
こっちが驚いた。
どうして君がそんな気になったのか、
僕にはてんで見当がつかん」
「理由なんかあるものか。
ただなんとなくそんな気持になったんだ」
「莫迦な」と老李は言った。
それから急に声をひそめると、
「同じやるにしてもさ、もう少しほかに方法がありそうなものだ。
だいいちあんな所じゃ泳いであがれる距離じゃないか。
君はもう少し利口かと思ったがな」
「そんなことを考えてもみなかったよ」
「おい、気は確かかい?」
「ふふ……。気はいたって確かだ」
春木は金竜が裸で警察につかまった時の情景を思い浮かべていた。
世の中に怖いものなしのあの大男が
嘘のように警察を怖がるのが目に見えてくるようだ。
「全く正気の沙汰じゃないぜ。
自分で投げた石のとばっちりを自分が食うのを承知だとすると、
これはまるで自分を虐待しているようなものじゃないか」
「そうかもしれん」
氷のように冷たいその返事を聞くと、
さすがの老李もあきれて口がきけなくなった。
老李が帰ると、春木はまた元の独房へ戻った。
ひとりでいることがこんなにいいと思ったことはいままでにない。
もしこのまま一生を終わることができたらどんなにいいだろう。
どうせたいして楽しくもない人生だ。
自分は殺人未遂の罪に問われるかもしれないが、
一生でなくて何年かであってもかまわない。
とにかく、自分の力や人の力で生きてゆくのが面倒くさい。
ここの政府がただで養ってくれるなら、それでもいいと思う。
夜になってから、彼はもう長い間思い出したこともない
母親のことを思い出した。
母親は彼がまだ子供の頃に死んでいるから、思い出といっても、
せいぜい三十代の女くらいの若さである。
十年たっても二十年たっても
自分の心の中に生きている人の面影は
少しも年をとらないから不思議だ。
「お母さん」
と彼は呼んでみた。
すると面影の中の母親は静かに顔をあげて、
じっと彼のほうを見つめた。
その顔は少しばかり笑っていたが、とても淋しそうだった。
ああ、やっばり母親は死んだのだな、と彼は思った。
母親の姿が消えると、今度はリリの顔が浮かんできた。
リリは少しも苦労性の女に見えない。
リリは生きているのだろうか。
人間の誰もが食べるような食物を食べているのだろうか。
そう聞いてみると、彼女は笑った。
それがとても朗らかそうだった。
目尻のあたりが特に人がよさそうに見える。
ああ、やっぱり彼女は生きようとしているのだ。
生きるのはとても難しいんだよ、と
教えてやりたいのだが、
彼女はてんでそれを受けつけそうにもない。
でもとにかく、彼女に自分のありったけの金をやって
本当によかった。
もう自分には金なんぞ要らなくなったのだから…。
ところが次の朝、昼近くになってから、
留置所の係官が鍵をじゃらじゃら鳴らしながら入って来て、
彼の入っている部屋の扉を開けた。
「おい、早く出て来い。釈放らしいぜ」
「えっ」死刑の宣告を受けたよりも
まだ驚いた叫び声を彼はあげた。
|