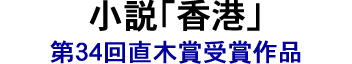| 第三章 海の砂漠(5)
その2
「ぐずぐずせんで早く出ろ。
お前は運のいい男だ」
なにがなんだかさっぱりわからない。
追い立てられるようにして外へ出て見ると、
警察署の裏門のところに老李が立って待っていた。
春木の顔がみるみる凄い形相になった。
「なんだって要らんことをするんだ、貴様は!」
「莫迦野郎!」ふだんに似ぬ威厳のある声で老李は一喝した。
その勢いに呑まれて、春木は口をつぐんでしまった。
「そんなに牢獄が恋しいなら、
たったいま出て来たところから入って行け」
しかし、そう言われても、
もう一度回れ右をして中へ入って行く気はさすがに起こらない。
もっとも入りたいと言っても入れてはくれないだろうが。
警察署は山の中腹にあって裏門からすぐ急な坂になっている。
その坂に沿って海岸まで段々になった建物が続いている。
秋晴れのさわやかな日射しが、
洗濯物のひるがえる年代の経った高層建築の間から覗いていた。
付近には場末の穢い店が並び、
屋台の花屋では広東人の女が
葬儀用の大きな花輪を道端で作っていた。
老李が先に立って歩き出すと、
春木は羊飼にひかれた羊のように後について下りはじめた。
「いくら世の中が厭になったからといっても、
牢獄に救いをもとめるという手はない。
本当に厭で厭でたまらないなら、あすこに見える、
あの、香港上海銀行の十三階に上がって、
派手に跳び下りるんだ。
そうすれば、ひと思いに解決がつく。
高い建物がたくさん建っているのは、
土地が狭いせいばかりじゃない。
世の中が厭になった人間のためを思って、
建築家は設計しているのだ」
「…………」
「もしそれが厭なら、本当に世の中に愛想をつかしたのではない。
面あてに牢獄に逃避行を企んだところで、
世間は君の愚を笑うばかりだ。
なるほど世間の風は冷たい。
だが、その風で頭を冷やさなければ、
人間は生きることの意味を忘れてしまう。
牢獄は一時逃れのためにはいいかもしれないが、
人間が本当に生きたいと思う時に、
それができなくなってしまう。
自由とは、荷厄介な代物さ。
たとえてみれば、女みたいなもので
眼の前にいるとうんざりするが、
やはりなくてはならないものなんだ。
やりきれないくらい孤独な存在なんだよ」
「…………」
「君がなにをやらかそうが、僕はちっとも苦にならない。
仲間を踏台にしてよじ登ろうが、
他人の金をふんだくろうが、
またあの金竜の奴を海に置きざりにしようが、
そんな君を僕は非難しやしない。
どうせ世の中ははじめから不公平にできているんだ。
誰かが得をすれば誰かが損をするようにできている。
共存共栄とか、右の頬を殴られたら、
左の頬も出せなんていうのは、
政治家や坊主の飯の種さ。
ただ忘れてならないのは、いまは文明の世の中だということだ。
文明とは人間が原始的な暴力手段に訴えて奪い合う代りに
もっと巧妙な間接的な方法を使うことをいうのだ。
政治にしても、商売にしても学問にしても皆そうさ。
そして、行動の自由が人間に許されている限り、
人間は自分に有利なチャンスがきた時、
いつでもそれをつかまえることができる。
牢獄にはその自由がない。
僕が君のことで心配するのは、その点だけだよ」
「どうやって金竜を口説きおとしたのですか」
と春木は聞いた。
薬にもならない理屈を並べ立てられるよりも、
さっきからその返事が気にかかっていたのだ。
「そんなことは造作もないことだ。
奴はまさか君が自分を殺そうとしたとは思ってもいない。
そんなことよりも君が持って逃げた海老が惜しくて惜しくて
たまらないんだ。
彼奴、裸で警察につかまったりしなかったら
おそらく警察に訴えたりしなかっただろう。
警察とかかわり合いになるのがとても厭な男らしいからな。
だから、海老の代金を僕が払ってやると言ったら、
即座に示談にすることを承知したよ。
素朴愛すべき男だよ、彼奴は。アッハッハッハッ……」
それから急に思い出したように言葉をついだ。
「そういえば、昨日だったか、
奴のところへ台湾から入境証が舞い込んできたそうだ。
女房から帰れ帰れと矢の催促さ。
あんな男は帰る故郷があるんだから帰ればいい」
海から冷たい風が吹き上げてきた。
渡し場へ歩いて行こうとしてふと見ると、
港の真中で二万トン級の巨大な英国船が
静かに方向転換をしていた。
海で真中に突き出した九竜碼頭は、
船を見送る人々で埋め尽くされている。
二人を乗せた渡し船が海を横切って対岸に着いても、
巨船はまだ少ししか動いていない。
螢の光、窓の雪
文読む月日重ねつつ
船上の楽隊の奏でるリズムに乗って、
公学校の時にでも覚えたのであろう、
老李が古い歌を嗄れ声で唱っている。
あの「螢の光」が外国の歌であることを、
春木はフィリピンの子供たちがうたっているのを聞くまで
知らなかった。
それを知った時、
春木はとても悲しかったことを記憶している。
西洋人の真似ばかりしている日本人の
そのまた真似をして生きている自分が無性にいじらしくなって、
思わず涙が出たほどだった。
しかし、いまはもう泣くまい。
泣いたところで失われた夢はもう帰ってこないのだ。
|