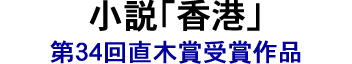| 第四章 揺銭樹 - かねのなる木 -(1)
その1
老李のような男でも縁起を担ぐということを春木が知ったのは、
旧暦の正月が明けてからである。
それまでの約三ヶ月間、春木は全然働かないで、
もっぱら老李に食わせてもらうことにした。
伊勢海老をごまかして貯めた金がまだいくらかあったので、
老李は春木に厭な顔も見せなかったし、
春木自身ももう二度と水汲みをする気にはなれなかった。
「待てば海路の日和さ」と老李は落ち着いている。
いつ海路日和になるか見当もつかないが、
老李がそう言うのだから、
そういうことにしておこう。
老李は予言者で、
いままでなにひとつとして的中しなかったことがない以上、
彼の家来になって、彼任せにするに限る。
クリスマスが過ぎ、新暦の正月が過ぎ、旧暦の歳末になると、
香港の海岸通りにある高士打道(グロスターロード)と、
九竜半島の旺角(モンコク)という所に、花市が立つ。
桃の花、ダリア、グラジオラス、水仙、菊、その他季節の花が
市を埋めるが、その中でも桃の花が人気の中心である。
桃の花は香港の正月には欠くことのできないもので、
ふだん花など買ったことのない家でも
大きな花瓶に桃を飾って来訪の人を迎える。
そして、その花の咲き具合によって、
これから始まろうとする一年の収穫を予告するのである。
もう何年も正月らしい正月を迎えたことのない老李が、
年の暮から今度こそどうしても桃の花を買うと言い出した。
大陸の内戦で、香港には難民が雪崩込み、
いろいろと激しい変化が起こったが、
過ぐる一年間は土地の商人にとっては確かに最良の年であった。
一本五十ドル、百ドルもする桃の花がとぶように売れる。
とてもそんな金持の真似ができるものかと春木がたかをくくると、
「本当に買うんだぜ。
ただし年が明けて花売商人が
花の捨て場に困る時間になってから行くんだ」
なるほど老李の話には一理がある。
大晦日の晩の十二時になると、
鑚石山の貧民窟でもあちらこちらで
爆竹の音がやかましく鳴りはじめた。
それを合図に老李は蒲団の中にもぐり込んでいた春木を
無理にたたき起こした。
「実はいま、ちょっといい着想があるんだ。
成功するかしないか、まだ未知数だが、
どうも今年は成功しそうな気がする」
「なんの話だ?」
つい釣られて春木は寝床の中から這い出した。
「早く着がえをしろよ。話は外へ出てからする」
だらだら坂になった鑚石山の小道は
赤い爆竹の屑でいっばいになっていた。
その上を踏みつけながら、
「種明かしをすれば、たわいもないことなんだ。
なぜいままでそれに気付かなかったのか不思議でならない」
老李はひとりで喋り、ひとりで領く。
「結局、人間はどんなに賢い奴でも
運不運はつきものなんだと考えるよりほかない。
一つの事業なり、念願なりが成功するためには、
時期というものがある。
たとえば花だって季節が来なければ、咲きはしない。
とすると間題は花が咲くまで
人間が辛抱しきれるかどうかにあるらしい」
「説教は後まわしにしてくれ」
いらいらしながら、春木は怒鳴った。
「ハハハ、そうあわてるなよ。
たしか君の友人で台北でお茶屋を開いている男があったな」
「いるよ」
「今夜帰ったら、
すぐその男へサンプルを送るように手紙を書いてくれんか」
「サンプル?お茶のサンプルを取り寄せてどうする?」
「まあいいから僕のいうとおりにやってくれ」
「お茶屋でもはじめようというのか」
「そのとおりだ。
なんだってそんな間の抜けた顔をするんだ?」
「茶の商売ぐらい難しいものはないそうじゃないか。
玄人さえフウフウいっているというのに、
ずぶの素人にできるはずがない。
しかも一文無しの無手勝流でさ」
「資本があって、専門のことをやるなら、莫迦でもできる。
他人の褌で角力をとるのが商人の腕だよ」
「なにか変な企みでもあるんじゃないか」
「だまって見ていろよ。
いまに香港じゅうの人をあっといわせてみせるから」
老李はさも自信あり気に、にんまりと笑った。
終点から赤い二階バスに乗り、
二人は旺角の花市の前で降りた。
もう午前一時を過ぎていたが、
どこの店の前も人だかりでいっばいである。
運転手にダリアの鉢をかかえさせている太々(たいたい)や、
千葉水仙を後生大事にさげている長衫(ちょうさん)の老人、
さては時間を気にしながら、客を呼びつづける花売商人。
「さあさ、一週間前に車を乗りつけた紳士が
三百ドル出しても売らなかったこの見事な桃の花が
たったの五十ドル。
五十ドルです。
さあ、買って下さい」
人々はぞろぞろと機械的に動いている。
流れ作業の機械の上にのせられた半製品のように、
先へ先へと押し流されて行く。
「いまにあれが五ドルで買えるようになるぜ。
少し早すぎたからどこかで粥でもすすろう。
粥代ぐらいは花屋さんが出してくれるよ」
粥屋の中を覗くと、どこもここも満員だった。
「人間は誰でも同じようなことを考えるらしいな」
しばらく戸口に立って待っていると、
やがて奥の座席が空いた。
二人はそこへ入りこんで及第粥という内臓の入った粥を食べた。
及第という名からして変だが、
粥といっても広東料理の粥は貧乏人の食べるものではないから
(貧乏人は飯を食う)、
あるいは生存競争の及第者の食べ物という意味かもしれない。
湯気のふかふか立っているのを口で吹きながら、
粥を口の中へ入れると、
熱いものが食道を通り抜けて胃の中に流れ込む。
身体全体が急に温かくなってくる。
たいした豪遊ではないが、金持になったようないい気持だ。 |