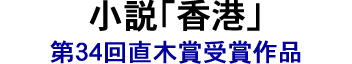| 第四章 揺銭樹 - かねのなる木 -(1)
その2
粥屋を出ると、
また半製品になって人波の中をもまれて歩く。
金魚を売る店があり、
ゼンマイ仕掛けの蛙を売っている店もある。
子供ばかりかと思うと大きな男が
のっそりのっそり動く蛙に見入っている。
二時を過ぎ、三時を過ぎると、
さしもの人波もしだいに密度がうすくなって、
いつの間にか店をしまう商人の姿も出てきた。
「そろそろ勝負をしようか。
もう少しすればただになるだろうが、
元旦早々ただ貰いでは縁起でもないからな」
値段も安く、品のよさそうな店の見当をつけておいたので、
そこへ入った。
「これいくらかね?」
老李が指さしたのは、
この店でも一番見事な枝ぶりのものであった。
「ヘイ、五十ドルです」
「なにを言っているんだ。
いったいいま何時だと思っているのかね。
元旦早々苦カを傭って捨てに行くのはそう安くはないぜ」
「じゃ、いくらなら買います、旦那」
「そうだな。二ドルはどうだ?」
「ご冗談でしょう。
二ドルで売るぐらいなら、いっそただでさしあげますよ」
「ただじゃ悪いから、二ドル払うと言っているんだ」
「それじゃいくら何でも可哀そうです。
ね、旦那、もう少し色をつけて下さいよ」
「よし、じゃもう五十セント奮発しよう」
それ以上はもう出せないという気構えを見せると、
商人はあっさり手を打った。
もうあたりには人影もなく、花市の明りもほとんど消えていた。
春木がそれを担ぎあげた。
「こんなに大きい奴じゃ、バスに乗せてくれないかもしれないぜ」
「じゃ歩いて帰ろう」
「それにしても厄介なものを背負いこんだものだ」
「いや、僕はさっきから、これをねらっていたのだ。
でもまさか、二ドル五十セントで売るとは思わなかったな。
此奴はきっと見事な花が咲くぜ」
「凄く金が儲かるぜ、と言っているように聞こえるな」
「まあ、だまってみていろよ」
老李は莫迦に上機嫌だった。
朝になると、バラックじゅうが老李の花のことで持ちきりだった。
花瓶がないので、罐詰の空罐に挿したが、
桃の枝を束ねていた竹縄をほどくと、
ただでさえ狭い部屋の中がいっぱいになってしまった。
水揚げをよくするために、老李は綿に水を含ませて、
枝と枝の間に挟み、綿が乾燥すると、
一日のうちに何度も水に浸しなおした。
まるで老李自身の今年の運が
いっさいこの花の咲き具合で
決定されるかのような慎重ぶりである。
その朝、バラックの裏で、
春木は水汲みから帰ってきたばかりの大鵬から話しかけられた。
「老李は二十五ドルも出してあの花を買ったそうじゃないか」
「うむ」
きっと老李が自分で宣伝したに違いない。
事実それくらいの値打ちは充分にあったし、
またそれだけバラックの貧乏人どもを驚かす効果もあったのだ。
「いったいどうやってあんな金をつくったのだろう。
花のためにそれだけ金が出せるなら、
きっとたいした金をつかんだに違いないぜ」
「さあ、知らんな」
「だって君は毎日一緒だから、知らんはずがないじゃないか。
いいことがあったからって、ひとり占めするなよ」
「ほんとに知らないんだ。知っていたら公開するよ」
「奴が出世したら、君もきっとよくなるね。
その時は僕のことを忘れないでくれ」
「そんな心配をするのはまだ早すぎる」
実際、春木には老李が何を企んでいるのかさっぱりわからない。
ただ彼の命ずるままに台北へ手紙を出すと、
折返しお茶のサンプルが航空便で届いた。
それをさらに包装しかえると、
老李はカサブランカにある商社にあてて発送した。
発送人は香港の連邦公司という
きいたこともない名前の会社である。
ここのところ、老李は毎日のように香港へ渡っていたが、
ある日一束の印刷物を持って帰って来た。
包装紙をとくと、中からインキの匂いのまだ新しい便箋と
封筒が出てきた。
老李のある友人の住所が刷り込んであり、
電話番号も電略もすべてそっくり拝借に及んでいる。
「どうだ。立派なものだろう。
どうせ相手はアフリカの商人だ。
便箋紙を見て店の大きさを判断するよりほかないんだから、
うんと奮発して、とびっきり上等の紙を使った。
これなら誰の眼にも一流商社に見えるだろう」
「便箋紙だけ見れば、そうかもしれん。
しかし、お互いに一面識のない相手に
いきなり注文などくれるかな。
少なくともその前に銀行を通じて信用調査をしに来ると思うね」
「その点は大丈夫さ。
銀行の調査係なんて原則として
お客に都合の悪いことは書かないものだ。
とにかく、注文が来るか来ないか、
この二週間のうちにきまるよ」
どういうわけで老李がこんなにも自信満々であるのか、
春木には見当がつかない。
しかし、二月に入ってからの陽気が暖かかったのも手伝って、
桃の花は次々と咲きつづけ、
あの黄色くて栄養不良な老李の顔にさえ
久しぶりに太陽がさしはじめたように見えた。
それから十日もたたないうちに老李が一本の電報を握って、
あたふたと駆け込んできた。
「どうだ。僕の眼に狂いはなかっただろう」
彼の差し出したのは烏竜茶五百箱の注文だった。
春木は狐につままれた思いで、
「しかし、どうやって台湾からそれだけの茶を取り寄せる?
いまの僕にはとうていそれだけの信用はないぜ」
「なあに、カサブランカから信用状がくれば、
それを抵当にして台湾向けの信用状を開けばよい」
三日もすると、フランス銀行を通じて、
香港ドルにして約一万五千ドルの信用状が届いた。 |