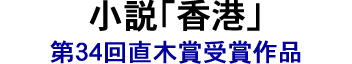| 第四章 揺銭樹 - かねのなる木 -(1)
その3
それを見せつけられた春木は少なからず驚いてしまった。
なぜならば台湾側からの買値は一箱三十六ドルだから、
一万八千ドルの元値になり、
この取引によって三千ドルの出血を見ることになるからである。
貿易の素人が考えたら、無一文の老李に
こんな商売ができるはずがないと思うかもしれないが、
戦後の台湾香港間の貿易は
公定為替相場と闇の間が数倍も差があるため、
信用状の額面どおり取引が行なわれることはまずない。
たとえば五百箱の信用状は一箱二十四ドルとして、
総計一万二千ドルで組み、
残金の六千ドルは、
着荷後台湾側の指定人に香港ドルで支払うことになっている。
老李の狙いはそこにおかれたのであるが、
彼自身に三千ドルの損失をカバーする能力がないのだから、
結局その皺が台湾側に寄せられてしまうのは明らかだ。
「そんなことをしちゃ、
君、僕の面子は丸潰れだ。やめてくれ」
「僕が残金を払わないと思っているのか?」
「払える道理がないじゃないか」
「なんだってそうコセコセするんだろうな、君は」
老李はむしろ蔑むような口調だった。
「五千ドルや六千ドルの金で、
この李明徴は男を売りやしないよ。
こう見えても野心はそう小さくはないぜ。
君は僕のようなやり方は無茶だと思っているのだろうが、
僕に言わせると、君の算術は学校で習ったのから
一歩も出ていないじゃないか。
もし、一プラス一が二で、二プラス二が四だったら、
世の商人はとっくの昔に滅亡しているよ。
商人の世界の銭勘定はまた違っているんだ。
とにかく、勘定はちゃんと払うから心配するな」
そう言われると春木は二の句がつげなかった。
老李は月百ドルの契約で友人の事務所に
机を一つ借り、表に連邦公司の看板を掲げた。
「君を副経理にするから、毎日出勤してくれ。
はじめのうちはたいして月給も払えないが、
そのうちに金が儲かるようになったら、
相当のことがしてあげられると思う」
どうせ食わせてもらっているのだから、
春木は老李の言うとおり、毎日、事務所に出るようになった。
間もなく台湾から五百箱の茶が到着した。
それをカサブランカ行の英国船に積み込み、
船会社からもらった荷積証書や保険証書など
いっさいの必要書類を取り揃えて、
銀行へ提出すると、すぐ差引三千ドルの金がおりた。
「さ、久しぶりにお茶でも飲みに行こう」
商人の町香港では茶楼といって、
商人たちが茉莉花の匂いのする香片茶や、
広東省の六安に産する六安茶や、その他水仙、竜井など、
それぞれの好みに応じた茶を飲みながら、
商談をする所がある。
広東人が人口の大部分を占めているこの商港では、
十二時から三時頃までが茶楼の一番混雑する時間である。
どこの商店も原則として朝と晩の二食を店員に食わせるが、
金のある階級も貧乏人も
昼はお茶を飲んで軽い点心を食べるからである。
老李に連れられて上がった茶楼は、
オフィス街のビルディングの一番上にあって、
何十も卓の並んだ広い部屋の中が
美しく着飾った人々でいっぱいになっていた。
高等難民とおぼしき上海人や北京人は男も女も派手な服装で、
その中に入ると、二人の一張羅さえずいぶん貧弱に見える。
「人間と生まれたら、金持になるべきだな」
老李は周囲を見まわしながら言った。
「そして、どうしても金持になれる見込みのないものは
共産主義者になるんだな」
「全くだよ。
こんな連中を見ていると、僕でも共産主義者になりたくなる」
「自分に自信の持てない人間の言う言葉だ。
それがいまの世の中の流行だからね。
もっともひところ前までは反対に、
国粋主義者になったものらしいが、
要するに左になる奴は右にもなる。
いじらしいくらい弱いことではどちらも似たようなものだからな。
僕はそんな奴を軽蔑するが責めやしないよ。
僕だって人によりかかって生きたいと
何度思ったかしれないからね」
「なんだか僕のことを言っているみたいだな。耳がかゆいよ」
「いや、君のような男は共産主義者にもなれないだろう」
「じゃもっと悪いのか」
「ハハハ……。そんなにひがまなくてもいいじゃないか。
僕の見るところじゃ君はしんは弱い男じゃないが、
ただ少しやきがたりないんだよ」
「じゃ、どうすれば、やきがたりるようになるんだ」
「もっと苦労するんだ。苦労がたらんよ」
「これでもか」
「もちろんさ。
その証拠に、いっも世の中を
おっかなびっくりで生きているじゃないか。
矢でも鉄砲でも来いという気持になるまでは
まだまだ年季を入れる必要がある」
「性格の間題だよ」
「まあ、それもあるだろうが、
しかし、君は悲哀というものを知っている。
悲哀を知っている人間は共産主義者になろうと思っても
遂になりおおせないだろう。
なぜって、君、悲哀は
人間性のもっともっと深い所に根ざしていて、
社会制度をいくら改善したところで、
解決ができないものだからな」
「しかし、人間の社会にはまだまだ改善の余地があるだろう」
「そりゃあるだろう。
しかし、どんなに世の中が変わったって、
人間は絶対に人間を信ずることはできないだろう。
結局、生き方は二つあるだけだ。
民衆に媚びて生きるか、それとも威張って生きるかだ。
媚びて生きれば生きるほど
人間はますます疑い深くなって
とうとう最後には疑いの虜になって減びてしまうだろう。
共産とか民主とかそんなに皮相な間題じゃなくて、
それを越えたギリギリの話だよ」
「じゃ君は威張って暮らそうというわけか」
「そうさ。心にもなくぺこぺこして暮らすよりは、
そのほうが僕の気質にあっている」
老李は小兵のくせに言うことが大きい。
物を食べる量も莫迦にならない。
二人の前にはいつのまにか
蝦餃や焼売や炒麺の空皿がうず高く積み上げられていた。
「これから、当分は借金取りにせめ立てられるだろうが、
君は僕のせいにして、 知らぬ存ぜぬで突っぱねればいいんだ。
弁済能力のない人間がくよくよしたらおかしいぜ」
茶楼を出る時、老李はそう言って
そっとポケットから一枚の百ドル紙幣を抜き出して、
春木の前においた。
「さしあたりの小遺だ。
じゃ明日、また事務所で会おう」 |