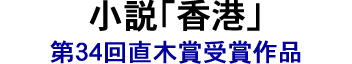|
第一章 自由の虜(3)
その1
老李はまめに動きまわる男だった。
まだ春木が否とも応とも言わない先から、
古物市のある摩囉街(モロカイ)のどの店にローラがあるとか、
海産物問屋の並んだ南北行(ナムパッホン)の
どの店のするめが一番割安だとか着々と調べをすすめた。
そのうえで、春木を誘って、
香港と九竜のあらゆる盛り場を下検分してまわった。
なるほど、どの盛り場にも、“のしいか”だけは売っていない。
少しずつ様子がわかってくると、
春木は“のしいか”屋をやってもよい気になった。
日一日と懐中が心細くなるにつれて、
どうにかしなければならないという焦りが募ってきた。
それに毎日同じ部屋で顔をつき合わせてみれば、
老李はそう悪い人間ではない。
商売をする以上は言葉のできる協力者が必要だし、
たえず眼を光らせていれば
売上げをごまかされる心配もまずない。
そして、なによりも心強いのは、
老李が実に有能な働き手であることだ。
数多い盛り場の中でも香港島の湾仔(ワンツアイ)にある
蕭頓球場(シュトンカウチョン)の脇が
一番人の出が多いから、そこにしようと老李は言った。
ローラや七輪やするめを買い入れ、
万一、警察の手入れが行なわれた場合の手順も
あらかじめきめておいた。
七輸は嵩ばる上に重たいから、
いざという場合は犠牲にするよりほかないが、
ローラは老李、原料のするめは春木がそれぞれ担ぐことにした。
球場はサッカーや、バスケットボールができるほどの広さで、
金網でぐるりを囲んである。
その金網の垣に沿って、露店商人が店を張っている。
雲呑麺(ワンタンメン)の店。
蝋腸や家鴨の干したのを屋台にぶらさげてある飯屋。
甘蔗の汁を搾っている店。
熱帯果実のバナナやマンゴーや
マンゴスチンなどを並べている果物商人。
花柳病にかかった性器の写真を掲げた、
得体のしれぬ膏薬を売る大道商人。
胡弓を奏でる女役者。
さては日本製の安物の玩具や万年筆の類を拡げている男たち。
以前から住んでいる人々に
新しく流れてきた避難民たちも入り乱れて、
一日に数えきれぬほど多数の人々が集まってくるので
朝から晩までたいへんな雑踏である。
昼は昼で強烈な太陽が容赦なく直射し、
塵埃や喚声や溜息や汗や体臭で狂わんばかりにざわめく。
夜は夜でアセチレン灯が青白く燃え、
その明りを囲んだ人々の暗い、生活に疲れた影を大地に投げる。
ここに集まる人々には明日が感ぜられない。
人々は歩き、時々立ち止まり、
物欲しげな眼をなげかけ、そして、また歩き出す。
盛り場を歩く人々の歩みはきまったように鈍重で、
それが一種重苦しい空気を醸し出す。
人々はなんのために歩くのか、
自分でもおそらく知らないのではあるまいか。
いや、目的などはじめからなにもないのだ。
人生が不必要に長く、時間をもて余しているに違いないのだ。
人々はただ叫び、笑い、嘆き、売り、買い、
そして手から手へと血と汗によごれた紙幣を渡す
単純なる運動を繰り返しているのだ。
そんな中へ春木たちが割り込んで開業した日は
一日じゅう、警察の手入れもなく、しごく平穏だった。
老李の予言したとおり、珍しい商売なので、
彼らのまわりにはたくさんの人だかりがした。
春木が慣れぬ手つきで、するめを焼き、
老李がそれをローラにかけたり醤油をつけたりしながら、
客を呼んだ。
「さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。
一度食べたら絶対忘れられない味なするめ!」
てれるどころか、老李の商売は堂に入りすぎていて、
下働きをしている春木のほうが何度顔を赤らめたかわからない。
しかし、奮闘の甲斐あって、店をしめるまでに、
十ドルほどの売上げがあった。
その半分が儲けだから、
二人は疲れを忘れてお互いに顔を見合わせた。
しばらく物もいえないくらいだった。
もう十二時を過ぎていたが、
二人はそれから二階電車の三等に乗って渡し場に行き、
そこから渡し船の三等に乗り換えて九竜へ渡った。
星が妙に散る夜で、海の生臭い匂いもなんとなくこころよかった。
希望に似たものが、安心に似たものが、
その暗い鱗のようにひかる表面から
しだいに這い上がってくるような気がした。
やっぱり老李は偉い男だ。
自分にはとうてい及びもつかない芸当をして、
無から有を、不安から安心を、
幻滅からほのかな希望を作り出すことのできる男なのだ。
「毎日、こんな調子だといいんだがな」
ダイヤモンドのようにきらめく対岸の灯を眺めながら、
春木は咳いた。
「好事魔多しだ」と老李は笑った。
「あんまり繁盛すると、すぐ競争者が現われるから、
そう長く続かないかもしれないよ。
まあ、稼げるうちに稼いでおこう」
ところがその翌日になると、
巡邏車が昼過ぎに一度、盛り場を襲った。
盛り場ではあらかじめ見張番を遠くにおいてあるので、
「それっ」と合図があるや
無鑑札の行商人はたちまち荷物をまとめて逃げ出した。
一瞬、盛り場の中は爆弾を落とされたような騒ぎになり、
逃げ遅れた女子供の叫び声があちらこちらであがった。
それらをふりかえる間もない。
見物人や通行人を押しのけ春木も老李も無我夢中で走った。
するめを包んだ風呂敷の中で、
自分の心臓が激しい動悸を打っている。
その風呂敷の中の心臓のように、
大切な商売道具を奪われないために
春木は自分の意志で制止できないほど
素早く動いている自分の足を感じた。
どのくらい走っただろう。
気がついてみると、老李の姿が見当たらない。
もう警官が追って来ることのない距離にいるのだが、
膝小僧のふるえがまだとまらない。
ほっとするよりも先に、春木は老李のことが心配になった。
老李に万一のことがあったらと思うと、
さきほどの怖さも忘れてまた元の盛り場へ引き返して行った。
新聞紙や塵挨の取り散らかった盛り場には
正式に鑑札を持った数軒の屋台店が残っているだけで、
さきほどまでのあの雑踏は見る影もなく失せている。
ちらほらとのこった屋台店にさえ客の姿はまばらであった。
春木は自分たちがつい数十分前まで忙しく立ち働いていた、
あの場所まで戻ってみた。
靴ででも蹴られたのか、新しい七輸は無残に割れて、
地面に転がっていた。
春木は感慨無量で、ただ痴呆のように立ち尽くすばかりである。
人間の小さな希望は
こんなにも脆く踏みにじられてしまうものだろうか。
衛生とか交通妨害とかいう理由が
いかにごもっともなものであるにせよ、
飢えと闘っている人間の最後のよりどころまで
なぜ破壊せずばやまないのであろうか!
重い足を引きずりながら、春木は広場を立ち去ると、
繁華街の間を海岸通りへ向かって歩き出した。
そこには九竜の油麻地(ユマテイ)へ出る
小さな渡し船の碼頭(マートウ)がある。
日除けのかかった騎楼の下を通り抜けようとした時、
後から、「おい、頼春木!」と呼びとめられた。
びっくりしてふりかえると、
すぐ脇の茶楼から老李が顔を出した。
「なんだ、こんな所にいたのか。
ずいぶん心配したぜ」
と言いながらも、さすがに春木はほっとした。
「そうやすやすとつかまってたまるものか。
心配させられたのはこっちだよ」
「でもまあ、とにかくよかった。
また七輸を買わなくちゃならないから、
今日ははじめからやりなおしだ」
「まあ、中に入って少し休めよ。
あと何時間かはどうせ駄目だから、
夕飯をすませてからまたはじめることにしよう」
茶楼で簡単な飯をすませてから、
二人は新しく七輸を買いなおして、ふたたび盛り場へ出た。
電灯や石油ランプやアセチレン灯など
さまざまの灯火の下には、
昨夜と少しも変りのないたくさんの露店と
群衆が集まって賑やかな市を形作っている。
そのどこに昼間見たような、
あの落花狼藉の跡をとどめているであろうか。
薬売り女は胡弓を弾き、看客は呆然と聞き惚れている。
手相見の爺さんは、通行人を引っ張り込もうとして
手当りしだいに呼びかける。
市はますます賑やかに栄え、
人類が存続する限り永遠に夜の火を絶やすことがないかのようだ。
これは終わることを知らない貧民の祭典である。
その夜遅くまで稼いだおかげで、
損失にはならなかったが、たいして儲けもなかった。
「いくら安いといったって、
手入れのあるたびに七輪や炭を台無しにされちゃ、やりきれんな」
汗水垂らして稼いだものが
粉々の七輸になってしまったかと思うと、
春木は惜しくてたまらない。
「仕方がないさ。
まさか七輪ひとつのためにつかまるわけにもいかんからな」
「それにしてもさ、この新しい七輸の生命もあと何日あるかな」
道具を片づけながら春木は言った。
七輸の生命のように、
彼自身の生命も明日がしれないように思われた。
|