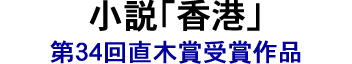|
第一章 自由の虜(2)
その3
飛行場の垣根沿いの広いアスファルト道路は、
太陽の直射を浴びて真夏のような暑さである。
その遂をしばらく行くと、
九竜城(クウロンセン)に出た。
九竜城は労働者の町である。
地価の高い香港だけにやはり三、四層楼の家が立ち並んでいるが、
いずれも戦前の旧式な造りで、
壁は黒い黴(かび)で覆われ、
雫のしたたる洗濯物が騎楼にへんぽんと翻っている。
街路は薄よごれており、
騎楼の下には物売りや食べ物屋が雑然と続いている。
その間を通り抜けると、
老李は、とある路傍の竹椅子に腰を下ろした。
床几のような、低い椅子が四、五脚おいであるだけで、
屋台の仲間にも入らない、お粗末な飯屋である。
大きな髷を結った、田舎びた広東人の女が
石油罐を二つ七輪の上にかけて、客を待っている。
石油罐の中は野菜と肉をごたごた煮たものらしく、
ほかほかと煙が立っている。
「お友達ですか」と女は老李の顔を見ると、
言葉をかけた。
「うむ。昨日、国から出て来たんだ。
どうも香港へ出て来さえすれば、
どうにかなると思う者が多くて困るよ」
老李は広東語で答えたが、
きょとんとしている春木をふりかえると、
今度は台湾語で言った。
「あちこち研究してみたが、一番安くてうまいのは、
この婆さんの所なんだ。
飯が一膳で五セント、おかずは野菜だけなら一皿五セント、
肉が入れば十セント。
だから二十セントか三十セントあれば、
どうにか一食分にはたりるわけだ。
自分で炊くよりもまだ安上がりだから、
天気がよければ毎日ここまで食いに来てるんだよ」
腹がすいていたが、
春木はたいして食欲がすすまなかった。
ガツガツと食べている老李を見ると
腹よりも胸がいっぱいになってきた。
「どうして食わんのだ。気味が悪いのかい」
「いや」と春木が首をふるのを眺めながら、
「しかしね、この飯にありつける間はまだいいんだぜ。
ぐずぐずしているうちに
この飯を食う金さえなくなってしまうよ。僕がそのいい例だ。
だからそうなる前に何とか手を打たなくちゃ嘘だ」
「それもそうだけれど、
僕にできることなどありそうもないじゃありませんか」
「なにひとつやってみたこともないのに、
どうしてそんなことがわかる。
僕なんぞはこうなるまでに実にいろんなことをやったものだ。
甘納豆を作ってみたり、水羊羹や晒し飴を作ってみたり、
あるいは子供相手にお菓子の景品が付く籤引きを考えたりした。
いずれもうまくはいかなかったがね」
「前にそんな商売をしたことがあるのですか」
すると、老李は急に口をゆがめて、
「これでも昔は満州ではれっきとした役人だったんだぜ。
驚いたかい。貧すれば鈍すだよ。ハハハ……」
食べ終わると、老李はポケットから
一枚の十ドル紙幣をとり出して釣銭を求めた。
瞬間、春木の眼が光った。
それは昨夜、自分が手渡した金に相違ない。
自分からは二十ドル受け取って、
家主に半分しか払わなかったに違いない。
現に昨夜は肉饅頭の代も春木が払わされたのだ。
しかし、老李は春木の表情に現われた変化には全然無感覚だった。
あるいは無感覚を装ったのかもしれない。
「実はいま、金の儲かる確実な仕事があるんだがね」
「資本がなくてもできる仕事ですか」
皮肉のつもりで、春木は尋ねた。
しかし老李は素知らぬ顔をして、
「全然資本なしというわけにはいかないが、
でも要るにしてもほんの少しばかりなんだ。
たぶん、君の手に合う仕事だよ」
「僕に金があると思っちゃ因りますよ」
「いや、絶対大丈夫だよ。
五万ドルには五万ドルの商売の仕方があるし、
五十ドルには五十ドルの商売の仕方がある。
これは五十ドルの資本でやれて
絶対確実に儲かる商売なんだ」
老李は急に雄弁になった。
それにつれて眼が異様に輝きを増した。
五十ドルと聞いて知らず知らずのうちに、
春木は心を動かしていた。
そのくらいの金ならいま彼のポケットに入っている。
「その商売っていったいなんですか?」
「それはね、市場へ行って”のしいか”を作って売る商売なんだ」
「のしいか?」
「そうだよ。
するめを焼いてのばした、あの”のしいか”さ」
彼の説明によると、香港の盛り場では
ほとんどあらゆる種類の食い物を売っているが、
不思議なことに、日本人が作るような、
ローラにかけてのばした”のしいか”だけはないそうである。
日本から輸入される北海道するめは一斤が
小売値段で二ドルぐらいであるが、
焼いて加工をすれば量もふえるし、
味も珍しいからその倍にはなる。
一日に五斤か十斤売れれば生活は保証されたようなものだ。
「ただ問題はね、鑑札なしに露店商をやるんだから、
警察につかまったらお陀仏だ。
毎日のように警察の犬どもがやって来るから、
さっと素早いところ逃けないと、ぶち込まれてしまうぞ。
しかし、警察が怖いか、飢死が怖いか、
比較の対象にはならんからな。
その証拠にさっき我々が歩いてきた道の両側に並んだ物売りは
ほとんど全部が無鑑札だよ」
話の筋が通っているだけに、
春木は自分のおかれた立場が恨めしかった。
相手も悪かった。
相手がもう少しおっとりした男なら、
たとえ最後の五十ドルが皆消えてしまっても悔いはない。
ところが、自分を食い物にしようとしているとしか
思えない相手であってみれば、
猜疑心はますます強くなるばかりである。
しかし、彼が警戒心を強くすればするほど、
老李の口元の微笑は大きくなっていく。
果実は熟すれば、やがて落ちてくる。
それを待てばいいと思っているふうである。
「やれやれ、久しぶりに腹いっぱいになった。
少し散歩でもしようか」
そう言って、老李はゆっくりと腰をあげた。
青空が騎楼の間から少しばかり覗いていた。 |