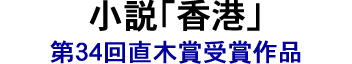|
第一章 自由の虜(3)
その3
三日目の朝、春木は許されて、
ふたたび鑚石山のバラックへ戻った。
彼がそっと忍び足で梯子段を上がって、
部屋の戸をあけると老李はベッドの上に足を投げ出して、
ぼんやりと天井の窓からさしこむ陽光をまぶしそうに眺めていた。
「やあ、帰って来たか」
そう言って老李は彼のほうを向いた。
一瞬、春木は自分の頭を見られたような気がして、
怒りがほとんど頂点にまで達した。
牢獄に入れられた時に、
髪毛をきれいに刈りおとされてしまったのである。
「なにを言ってやがるんだ」
やにわに相手の胸倉をつかまえていた。
胸倉をつかまえられながらも
老李はすこぶる落ち着いている。
「まあ、まあ、そう腹を立てるな。話せばわかることだ」
「弁解なんか聞きたくない!」
「弁解じゃない。今日は君が帰って来る日だと思って、
朝から飯も食いに出かけないで待っていたのだ」
「帰って来ると知っていたら、
なぜ迎えに来なかったんだ?なぜあの日すぐ来なかったんだ?」
「行きたかった。行ければ行きたかった。
だが行けなかったんだ」
「その理由を聞こう」
春木は握っていた手の力を少しばかりゆるめた。
「理由は簡単だ。
もしあの日、僕が警察署へ行っていたら、
二十ドルの金を出さないわけにはいかなかったからだ」
「しかしあの金はもとはといえば俺の金だ。
ローラさえほったらかして逃げたくせに何をぬかすか」
「それなら僕のほうにも言い分がある。
見ろ、僕のこの足を!」
そう言って、
老李は自分のズボンの裾を少しばかり引っぱりあげた。
春木は思わず握りしめていた手をはなした。
それはおよそ三寸ほどもある、かなりに深い切り傷だった。
膏薬を塗ってはあるが、
腿の肉が裂けて、紅い肉が気味悪く露出している。
「逃げる時に垣根の針金でひっかけたのだ。
夢中だったから、長い問、気もつかなかった。
血がズボンににじんで、
道を歩いている人に注意されてはじめてわかったんだ」
「………」
「なるほど、僕はローラも持たないで逃げた。
ローラを持つだけの余裕があって、
ローラを持たないで逃げる男と思っているのか。
隙があれば人の物だってかっさらっていきたいほどの僕が、
どうしてローラをおいて逃げたか考えたってわかるじゃないか。
あれほど、僕は君に
なにはさておいても逃げろといっておいたはずだ。
うまく逃げきれなかったのは君のほうが悪い。
それを棚にあげておいて僕を責める手があるか」
「しかし、金は俺のものだ」
「そのとおりだ。金は君のものだ。
これ、このとおりここに保管してある」
老李はポケットから
二十数ドルの皺くちゃになった紙幣をとり出した。
「膏薬を買うために、一ドルばかり使った。
残金は全部でこれだけだ。
そりゃ君は自分ひとりつかまって、
僕がつかまらなかったのが不満だろう。
その気持はわかる。
しかし、僕がつかまったところで、
やっぱり君と同じように三日問、牢屋の中でがんばったよ。
僕だってできれば君の保釈金を払いたかった。
君がつかまって丸坊主にされるのを手を叩いてみているほど、
悪趣味な男じゃないつもりだ。
だが、いまの僕らにはそれはゆるされていない。
考えてもみたまえ。
もし三日間の牢獄生活を避けるために二十ドルを支払ったら、
それから後、二人の男がどうやって飯を食っていくんだ。
二十ドルの金があれば、
最低生活をやればまだ何週間かはもちこたえられる。
その間に気持をもちなおすこともできるだろう。
それをもし君の考えているように、ぱっと払ってしまったら、
その日から二人して飢えなければならないではないか。
僕はこの二つを天秤にかけてみたのだ。
行きたかったが、我慢したんだ。
もし君と僕が逆の立場に立ったら、
君が保釈金を払いに来ても、僕はやっぱり拒否しただろう」
しかし、春木は老李の言葉を
そのまま素直に受け取る気にはなれなかった。
老李は口先のうまい男なのだ。
その口車に乗ってまたまた利用されるほど俺はお人好しではない。
そう思わざるを得ないほど、
春木の受けた屈辱は大きかったのである。
お互いに同志であれば同生共死を要求する権利がある。
だが、同志と思った人間さえ
あてにならない世の中であってみれば、
行きずりに出会ったこんな男になんの頼み甲斐があるだろうか。
そして、三日間を過ぎたいまになってみると、
罰金を払わないで金を残したことは
憎らしいほど慎重な態度だと舌を巻かざるを得ないのである。
「君にはすまなかった」と老李はもう一度繰り返した。
「しかし、我々は誰からも保証されずに
自分の力で生きてゆかなければならないんだ。
我々は自由を愛して故郷を捨てた。
我々は自由を求めて、この地に来た。
だが、我々に与えられた自由は、
それは滅亡する自由、餓死する自由、自殺する自由、
およそ人間として失格せざるを得ないような種類の自由なんだ。
こんな生活をしていて、
まだ善良なる市民の根性から抜けきれない奴は
よっぽど無神経な野郎だ。
我々には故郷もなければ、道徳もない。
こんな世の中ではそんなものは犬にでも食われろだ。
金だけだ。金だけがあてになる唯一のものだ」
「莫迦な」
春木はむっとして思わず口走った。
「ユダヤ人!貴様のような奴はユダヤ人だ」
「そうだよ。ユダヤ人だよ。
ユダヤ人になることが僕の当面の目標だよ」
老李はすこぶる冷静だった。
「君は軽蔑するだろうが、
ユダヤ人は自分らの国を滅ぼされても、
けっこうこの地上に、生き残った。
この香港に巣食うユダヤ人の根強い勢力をみたまえ。
あの山の中腹にある豪華なユダヤ人会館をみたまえ。
奴らを軽蔑する前にまず自分を軽蔑したまえ。
国を失い、民族から見離されながら、
いまだにユダヤ人にもなりきれないでいる自分を笑いたまえ」
ふと春木の脳裏に、故郷の山河が浮かんできた。
一望千里のはるかなる嘉義平野に
えんえんと続く甘蔗畑の青さが眼にしみるようだった。
なぜ自分はあの美しい故郷を捨てて、
こんな異郷まで来てしまったのだろう。
なぜあの同志たちのように、
むしろ縄につながれることを選ばなかったのであろう。
まざまざと台北市の情景が思い出されてくる。
彼の仲間の一人が「共匪」と書いた赤いチョッキを羽織らされ、
台北市中をトラックに揺られながら
街から街へと見せしめに引き回された日の光景だ。
あの友人は自分なんかと違って
台湾南部でも屈指の大財産家の息子だった。
もしあの男が共産党だったら、
そしてすべての金持が喜んで共産党になるものなら、
この世の中はもっとはるかに理想的な社会になっていたであろう。
あの男はたぶん自分がなんのために、
赤チョッキを着せられているのかわからなかったに違いない。
悪夢を見つづけているのだと最後まで思っていたに違いない。
そして、今日になってみれば、
たとえ台北駅頭の広場で、
衆人の環視を裕びながら銃殺されたとしても、
あの男は自分よりずっと幸福だったのだ。
|