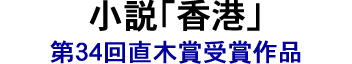| 第二章 密輸船(1)
その1
「いずれこんなことになるんじゃないかと思っていたよ」
てかてかに刈り上げられた春木の丸坊主を見上げながら、
周大鵬は言った。
春木が厭な顔をしてそっぽを向くと、
はじめて自分の失言に気付いた様子で、
「しかし、犠牲者は君ひとりだけじゃない。
なにしろ老李の奴はあのとおり口はうまいし、
利口者だから誰でも一度は必ずひっかかるんだ。
僕はよっぽど、君に忠告しようかと思った。
でも君とはそれほど親しい間柄じゃなかったし、
焼餅をやいているように思われちゃやりきれんからね。
ものは考えようだが、人を信用して裏切られたって
べつに恥にはならんよ。
少なくとも最初の一回は裏切るほうが悪いんだからね。
そういっちゃすまないが、薬にはなっただろう」
薬になったどころか、薬はむしろ効きすぎたくらいだ。
人口二百五十万を擁するこの香港で、警察に捕えられて、
体刑や罰金刑にあうのは日常茶飯事である。
新聞ダネになるような大事件ならまた別だが、
春木のようにたかが不法行商のために
牢獄で三晩を明かした男など誰も気にとめるはずがない。
にもかかわらず、春木はあの三日間にこだわった。
このバラックに住む貧乏人どもが、
皆して彼を笑い者にしているように思われた。
一番いけなかったのは牢獄で坊主頭にされたことである。
中国人の間で丸刈りにしている人は一人もいない。
英国人は兵隊だって皆きれいに髪を分けている。
坊主でいるのはたったいま、<あすこ>から出て来たところです、
と広告しているようなものだ。
もっとも人々が彼を笑うのは
あながち彼ひとりの被害妄想ではなかった。
彼が帰って来たばかりのときに家主のおかみさんが、
「まあ、頼さんは案外頭の恰好がいいのね」と言ったばかりに、
それ以来、おかみさんとは口もきかなくなってしまった。
「頼さんにはうっかり冗談も言えない」とあとで、
おかみさんは老李をつかまえてこぼしていた。
バラックの人たちは彼を笑ったが、
それは牢獄帰りの男を軽蔑したわけではなかった。
べつに悪意があってのことではないが、しいていえば、
警察に御用になった彼の間抜けさを笑ったのだ。
しかし、春木にしてみれば、
道ですれ違った人がほんのちらっと流し眼で、
自分のほうを向いただけでも、頭を見られたような気になって、
ゆえ知らぬ敵意を感じた。
全く敵意というよりほかない。
このバラックに住んでいるのは
職にあぶれた波止場苦力(クーリー)や
上海から流れてきた中年の夫婦や、
それからなんの職業についているか見当がつかないが、
一日じゅう外を出歩いている連中で、
どいつもこいつも明日のない、その日暮しの人々ばかりである。
そのくせ、誰もがお互いに敵意を持って暮らしている。
はじめてこの家へやって来た時、
春木はなぜ人々がお互いに助け合うかわりに
憎み合って生きるのか不思議だった。
しかし、いまでは貧乏人の心理が
しだいにわかってきたような気がする。
それは他人だけが助かって、
自分ひとりが永遠に取り残されるかもしれないということに対する
底知れぬ恐怖――貧乏人をいらだたせ、絶望に陥れ、
冷酷にさせるのは、実にこの恐怖なのだ。
裏返していえば、もしこの家に住むすべての者が
皆一様に助からないときまっておれば、
人々はいまよりずっとなごやかな気持になって、
お互いに慰めの言葉のひとつもかけあったに違いない。
ところが現実は他人を押しのけてでも助かりたいという欲望が
いやらしいほど強烈なのだから、
人々は猜疑と嫉妬の眼でお互いに厳重に監視しあうのである。
これらの「眼」を血走らせるのはいとも簡単なことだ。
誰かがにわかに景気よくなることだ。
眼は次から次へと、どこまでも執拗に助かろうとしてあがいている
一つの魂のあとを追う。
眼には呪いの言葉がこもっている。
失敗せよ、失敗せよ、早く失敗せよ。
呪いの言葉は細菌のように空気の中に伝播される。
そして、失敗が現実になったとたんに、眼には笑いが浮かんでくる。
だから笑いとは涙のことだ。
笑いとは救いのことだ。
|