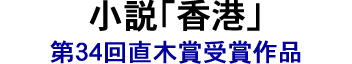| 第二章 密輸船(1)
その2
春木の敵意はそうした笑いに取り囲まれたために
反射的に湧いてきたものであった。
自分では全然気づかないうちに、
それはびっくりするほど激しいものになっている。
それだけ貧乏人根性が板についてきたのだともいえる。
同じ部屋で寝起きをともにしながら、
春木は老李とろくに口もきかなかった。
自分が逃げ遅れて豚箱に入れられたのは
老李の罪でないとわかっていながら、春木は老李を憎んだ。
憎みながらも、毎日眼と鼻をつき合わせて暮らさねばならないのは、
もっぱら経済的な理由によるのである。
金が欲しい。
金さえあれば、こんな厭な思いをしないですむんだ。
しかし、奇蹟でも起こらない限り、
金がどこからも転がり込んでくる見込みはなかった。
二十数ドルあった残り金も、いまはほとんどなくなっている。
バスに乗って外出するのはおろか、
飯を食うのさえよほど考えなければならなくなった。
バラックの夏はお話にならないほどしのぎにくい。
屋根が防水質の黒い紙張りであるうえに、窓がないので、
ちょうど乾燥室の中で蒸れているバナナのようである。
いつのまにか青い、栄養不良の顔がしだいに黄色くなってきた。
「毎日、家の中にとじこもっていちゃ、身体に毒だぜ」
と大鵬は言う。
あれ以来、大鵬はなにくれとなく心を使ってくれる。
彼の仕事は朝と晩の放水時間だけで、
それ以外は一日じゅうひまだから、老李が外出して、
いない時は、よく春木のところへやってきて無駄口を叩いている。
老李と違って、大鵬はさっぱりした男で、
適当に相手になっていると、春木をすっかり親友扱いにしはじめた。
だが、春木にしてみれば、健康のことなど気にもならなかった。
青春のない人生にとって、肉体の健康がなんの役に立つだろう。
そんなことに気を配ってくれるのは有難いが、
内心彼は大鵬を軽蔑したくなる。
大鵬のように一日に二度の食事にありつくために、
石油罐に水を汲んで一粁の道を四往復することに、
自らの青春を消磨しつつある人生を笑いたくなる。
そんな生活をするくらいなら、ベッドの上に長々とねそべって、
黄色い、病的な夢でも見続けているほうがましだ。
眼をつぶると、瞼の上が太陽のまぶしい光で、
ちょうど野っ原の中で、体を横たえているような感じである。
すぐ近所にある醤油工場から響いてくる単調な機械の音は、
辛抱強く我慢をすれば、蜜蜂の甲斐なき羽ばたきのように
聞こえないこともない。
すると、彼自身は野花の中に埋もれて、
死んでいくような幻想に陥っていく。
そうだ。
まだ死というものがある。
あらゆる解決のできない問題に解決を与えることのできる
死という大自然の重宝な切り札がある。
春木の顔に思わず笑いが浮かんだ。
笑いというもの以外に、
彼には感情を表現する方法がなくなっている。
「もうそろそろ放水時間だ。
どうせ閑なんだから一緒に行ってみないか」
と大鵬に誘われて、ある日、彼は水汲場へ出かけて行った。
水汲場は貧民窟を抜けて、幅の広い大通りへ出る途中にある。
戦前はわずか百万だった人口が
戦後各地から押し寄せた難民を合わせると二倍以上に膨張し、
一方、貯水施設は昔のままであるため、
香港は常時水の不足に悩まされている。
朝は六時から九時まで、夕方は五時から七時まで、
都合、五時間しか水道の水が出ない。
鑚石山の貧民窟はもともと政府の公有地や農地に難民が
無許可で勝手に建てたバラックの集団であるから、
水道管が通っていない。
したがって公共の給水栓のあるここまで
水を汲みに来なければならないのである。
まだ四時を少し過ぎたばかりなのに、
水汲場にはすでに多数の男女が列をなして、水を待っていた。
黒い布の縁を垂らした藤笠をかぶった広東人の女や、
頭をGI刈りにした若い難民や、
昔は連隊長ぐらいしていたかもしれない
恰幅のよい軍人あがりのおっさんが、
太陽のまぶしい直射を浴びながら水を待っている。
海をすぐ目の前に見ながら、
人々は一滴の水のためにこうして毎日毎日立っているのだ。
いつしか春木は砂漠を連想していた。
茫々たる砂漠の中を、
水草を追って歩く一群の人々の中に彼はまぎれ込んでいた。
彼は渇えていた。
コップ一杯の水でよかった。
しかし、そのたった一杯の水でさえ恵んでくれる者はいない。
もうこれ以上、彼は歩く気力がなかった。
一人だけ落伍したかった。
このままくたばってしまってもよかった。
だが人々は彼にそれをも許さなない。
働け!落伍するな!そして他人の恵みにすがるな!
それは太古から涯知れぬ未来まで、人類が続く限り、
変わることのない鉄則なのだ。
この鉄則のゆえに、彼は歩くことを強制されているのだ。
「僕だってね、まさか、香港へ来て、
こんな渡世をするとは思っていなかったよ」
と大鵬は額を流れる汗をふきふき言った。
かつては白シャツ階級だった、
そのほっそりした身体つきがおかしなほど哀れに見える。
それでいて、その眼の色は青空のようにくっきり澄んでいる。
「もし銀行チェックを落とさなかったら、
今頃は台北の銀行で係長ぐらいにはなっていたかもしれんな」
と春木が言うと、「そうなんだ」と大鵬は無邪気そうに笑った。
「拾った相手が悪かったんだ。
でなければ、そとで話し合って解決のつくことだもの。
なにしろインフレの真最中だろう。
董事長や経理は皆いろんな名目をつけて、
銀行から金を借り出しては、家を買ったり、
品物の囤積(とんせき)をしていた。
銀行利息は安いから、三、四カ月もすると、
すぐ元利合計耳を揃えて返せるんだ。
そりゃチェックを偽造した僕も悪いに違いないが、
そのくらいのことは誰でもやっていたよ。
僕は運が悪かったんだ」
「過ぎ去ったことをくよくよ言ったところでしょうがないよ」
「それもそうだ。
世の中には雨の降る日もあれば、天気の日もあるからな。
そう悪いことばかり続くこともないだろう。
君だって、悲観するに及ばないよ」
|