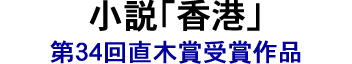| 第三章 海の砂漠(3)
その2
「拙いことをしたものだ。
長い間気づかなかったのに、
どうしてまた今日になって見つかったりしたのだろう?」
春木は何も答えないで、放心したように坐り込んでいる。
「しかし、どうせ寒くなれば駄目になる仕事だ。
少し早く切りあげたと思って諦めるんだな」
そう言われると、春木は無性に腹が立ってきた。
「貴様はそんなことを言っておれば、気がすむだろうよ。
少しは人の身になってみろ」
「まあ、まあ、そう怒るな。
喧嘩をするにも相手が悪い。
あんな男じゃこっちにいくつ生命があってもたらんよ」
「俺が奴を怖がっていると思っているのか」
「そうは思わないが、負けて勝つという言葉もある。
奴はもう君と一緒に仕事をしないと言ったが、
なあに、案外この二、三日のうちに
また頼みに来るかもしれないよ」
「冗談じゃない。
あんな野郎とまた一緒になってたまるか」
「そんないい方は、君、
まるで子供が駄々をこねているようなものじゃないか。
大人の世界じゃ、どんなに癪にさわることがあっても、
相手に利用価値のある間はだまって辛抱するものだ。
後足で砂をひっかけるのは、それからでも遅くない」
老李の言葉には予言者のような自信が溢れていた。
彼のその予言に少しの狂いもないことは間もなく実証された。
それから三日ほど過ぎたある朝、
金竜が大きな足音をたてて
バラックの梯子段を上がってきたのである。
「おい、頼。仕事だ」
狸寝入りをきめ込んでいる春木の肩を彼は激しく揺り動かした。
まさかそれでもまだ寝ているふりはできない。
「もうクビだと言ったじゃないか」
「まあ、そうむくれるな。
あの日は俺も悪かった。
その代り今日から一回にニ十ドルやるからいいだろう」
ふだんと打って変わって、
春木の鼻息を伺うような猫なで声である。
「そりゃ船頭は腐るほどいる。
しかし、やっぱり相棒は気のあった奴がいい」
金竜の腹の中が春木にはみえすいていた。
素性の知れない広東人の船頭を使っては
安心して潜っておられないからだ。
その点、春木ならいつでも
腕力にものをいわせることができると思っているに違いない。
「な、相棒」
もう一度そう言われると、
春木は身体じゅうがくすぐったくなってきた。
もう三日前の恨みは見事に晴らしたような気になった。
「話はもうわかった」
背中を向けたまま、
春木はちっぽけな勝利者の喜びにふけった。
夏もすでに残り少なくなっていた。
海岸の人の出が日一日と淋しくなり、
気候に対してあまり敏感でない西洋人だけが
夕方のひととき車を乗りつけるくらいなものである。
海に入るというより、海辺の砂の上に寝転んで、
日光浴をするのが彼らの楽しみであるらしい。
それらの人々の姿さえしだいに減少するにつれて
春木らが海へ出る日数が逆に増えてきた。
もう先が短いとなると、金竜自身にも焦りがみえた。
もっともいまのうちにうんと稼いで
冬籠りの用意をしようという殊勝な心構えではなくて、
たとえば青春の過ぎ去るのを自覚して、
最後を華々しく飾ろうとする
若人の哀れな心のあがきのようなものである。
だからその日の稼ぎが多くなればなるだけ
浪費の度合も激しくなり、
逆に心はいよいよ荒れすさんでくるのである。
一回に二十ドルの稼ぎがその倍になったところで、
春木のいまの気持を救うことはできないであろう。
人生とは刹那を生きる以外の何ものでありえようか。
刹那を辛うじてつなぎ合わせる金という糸が続く限り
人生は続くものだ。
そしてこの糸がぶつりと切れたところで、
人生そのものが終わってしまえばいいのだ。
こうした彼の刹那主義は秋風が立ちはじめると、
いっそう手に負えないものになってきた。
ネグロス山中で、アメリカ軍の艦砲射撃や空襲を受け
今日にも死ぬかもしれないという目にあっていた時でさえ、
こんなに切羽詰まっていなかった。
あの時の恐怖は、いわば山中を逃げまどう
すべての人々に課せられたものではあったが、
いまの場合は彼ひとりだけに加えられたものである。
一緒に仕事をしている金竜でさえ、
とても彼のやけくそな気持を理解できないであろう。
それどころか、金竜は海から這い上がる前に
必ず舟底を点検してまわるし、ボートの上に上がると、
酒瓶をとりあげる前に、
ボートの中をちらっちらっとさぐるような眼つきをする。 |