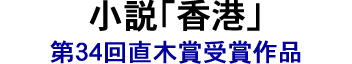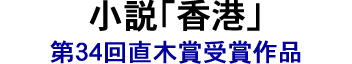| 第二章 密輸船(2)
その3
「君の家かい」
と大鵬がきくと添財は笑いながら頷いた。
すっかり度胆を抜かれている大鵬を楽しむように、
「仕事が忙しくて、建築屋まかせなんだ。海がよく見える所だよ」
なるほど屋上まで上がらないでも、庭から港が見渡せる。
海上には明りをつけた汽船がちらほらしており、
対岸の九竜(クウロン)半島の燈火が
ちょうど美人の身体いっぱいに輝く宝石のように豪華にきらめいていた。
「素晴らしいな」
「神戸でもいま、これぐらいの家を建てているよ。
もっとも向うは日本式だがね」
とさりげない様子で添財は答える。
「中に住まわせる人も日本人ですか」
と春木が聞くと、彼は声を立てる代りに、にやにやと笑った。
三人はそれからふたたび山を下ると、
石塘咀(セツトンツウイ)にある広壮な広東料亭へ向かった。
添財は脂肪分に飢えていた。
日本のいわゆるシナ料理は彼の口に合わないが、
そればかりでなく一週間に及ぶ船上生活は、
歯ブラシとタオルを一枚持ち込む以外は着のみ着のままであり、
船員と同じ飯をあてがわれるので、いやでも痩せてしまう。
船を降りたら、なによりもまず腹ごしらえだと彼は言う。
言にたがわず彼は相当な健啖家だった。
だが、飢えている点では大鵬も春木も変わりはない。
三人ともよく飲み、そして、ガツガツ食べた。
久々の酒で、大鵬は額の血管が見えるほど顔じゅう真赤になった。
酔がまわると、自分がいかに添財と親密であるかを
春木に見せたいらしく、しきりと添財にからんだ。
一緒に水汲みをした頃の事を懐かしそうに話したりするが、
そのたびに添財が厭な顔をするのを春木は見逃さなかった。
春木は大鵬の無神経さに苛立ちを感じた。
しかし、別の意味で、彼もやはり添財によく思われたかった。
機会を見て、彼は言った。
「あなたもやはり政治的なことから台湾を去ったのだそうですね」
すると、添財は急にびっくりして彼のほうを向いた。
一種悲痛な表情がその顔に浮かんだ。
やはりこの男もそうなのだ、とその時、春木は思った。
しかし、それはたとえば、流れ雲が太陽を遮った時のように、
ほんの一瞬の出来事にすぎなかった。
「そんな話は君、やめようじゃないか。
僕はいま商人なんだ。
商人が政治の話をしたところではじまらないよ」
この一言で、春木はひどく自尊心を傷つけられた。
彼が添財に対して抱いていた秘かな期待は
完全に破壊されてしまったのだ。
もともと添財はいま昇天の勢いにある成金で、
自分は水汲みをしてやっと糊口をしのいでいる貧乏人にすぎない。
二人にもしなんらかの親近感があるとすれば、
それは同じ亡国の運命を担っているという共感だけであろう。
それがないとすれば相手に近づくなんの手がかりもないことになる。
知らず知らずのうちに、
見も知らぬ相手によりかかろうとしていた自分が恨めしくなってくる。
その自己嫌悪が強くなればなるほど、
大鵬の親しそうな口ぶりが鼻持ちならなくなった。
食事がすむとそれからキャバレーを三軒ばかり歩いた。
どのホールでも添財はダンサーに知られている。
そうなるまでにどれだけ資本を注ぎ込んできたかは、
彼のチップのはずみ方でわかった。
ホールを出る時、彼はポケットから百ドル紙幣の束を取り出すと、
その中から一枚ずつ抜いてダンサーたちに渡した。
そのくらいの金はいまの彼にすれば痛くも痒くもないに違いない。
しかし、春木は彼が故意に自分らを
絶望させようとしているとしか思えなかった。
ダンサーたちは金に対しては本能的な嗅覚をもっているとみえて、
添財にだけ愛想よくふるまう。
自分らは、その彼を引き立たせる脇役として
さんざっぱら酷使されているのだ。
それを思うと、ご馳走になったことなど少しも有難くなかった。
大勢のダンサーに見送られて、
車に乗り込んだ添財はすっかりいい気分になっていた。
「明日からまた忙しくなるんでね、もう相手はできんが、
二カ月ぐらいしたら帰って来るからその時また遊びに来たまえ」
車は人通りの少ない深夜の街を通って、統一碼頭へ着いた。
「そうそう、服を着替えに行かなくちゃ」
と春木が思い出したように言うと、
「そのまま着て行きたまえ。どうせもう要らないものだから」
しかし、扉があけられでも大鵬はまだ車中でもじもじしていた。
「実はいま、困っているんだけれど、少し助けてくれないか」
といささか言いにくそうに呟くと、
みるみるうちに添財は不愉快な顔をした。
だが相手の申し出を断わるために口をきくのが面倒臭いというように、
ポケットの中に手を突っ込むと、
一枚の十ドル紙幣を掴み出した。
春木は思わず顔をそむけたかった。
その時、大鵬がのばしたあの華著な手は、
あれはまがいもなく乞食の手だった。
もしそれが自分の手だったら、春木は庖丁を持ってきて、
その場で切り落としてしまっただろう。
なんという汚らしい、腐った手だ。
恥知らぬ手だ。
「なぜ君も頼まなかったんだ?」
渡し船の中で、大鵬は平然として聞いた。
春木の胸の中は軽蔑でいっぱいになっていた。
(俺は乞食じゃないぞ)と彼は叫びたかった。
だが、自分もいつの日か
この男と同じようなことをしないとも限らない、
という考えが心の片隅で渦巻いていた。
渦巻きはしだいに大きくなって
彼自身の姿は全くその中に見失われてしまった。
「君ほどあの男とは親しくないからね」
と彼は弱々しそうに答えていた。
「それもそうだな。
でも僕の言ったことに間違いはないだろう。
奴は友達思いの男だから、奴と親しくするといいよ」
「うむ」
春木はこれ以上大鵬の相手をするのがばかばかしくなった。
彼は渡し船のてすりに手を凭(もた)せかけたまま深夜の海を眺めていた。
星の光を反射して、海は青白く光っている。
どうしてか今夜の潮の流れは、
ふだんよりずっと早いように思われる。
すると、自分ひとりが小舟に乗って
波間を漂流しているような錯覚にとらわれた。
自分はただ流されているだけで、
潮に抗して漕ぐことは許されていない。
どこにも陸らしいものは見えないし、海鳥の飛んでいる形跡もない。
糧食もほとんど尽きた。
あとは、ただ肉体のくたばるのを待つだけだ。
|