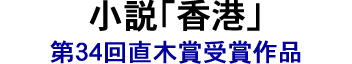| 第四章 揺銭樹 - かねのなる木 -(3)
その3
その声があわてて口を覆った父親の掌の中に押しつぶされるのを
春木は聞いていた。
それを聞かなくても、彼にはわかっていたことである。
部屋へ戻って来たリリは蒼ざめた顔をしていた。
「お前の子供だね」
「聞こえちゃった?」そう言ってリリは顔を伏せた。
「何もかくす必要はないよ」
「でも悪いと思って」
「僕だってお前にかくしていることはたくさんある。
もちろん、そんなことでお前を責めたりしない。
人間は自分が一番信じている人にさえ
打ち明けられない秘密をもっているものだ」
「私に秘密なんかないわ。
ほんとはなんでもあなたに言ってきかせたいんだけれど、
でもそれであなたを不愉快にするかもしれないと思って
やめたんです。ほんとは…」
「やめてくれ。
聞かなくたってわかっている」
と春木は押しとどめた。
「君にどんな過去があっても、
それが君に対する僕の気持を変えるものではない。
それだけは知っておいてもらいたいな」
「ええ」とりリは頷いた。
「それからいままで君には言わなかったが、
ほんとは僕は国に妻も子もいない」
「わかっていましたわ」
「じゃなぜいろんなものを買って国へ送ったりしたんだ」
「私があなたに言わなければならないことを、
どうしても言い出せなかったからです。
そんな自分の気持をどう処理していいかわからなかったからです。
すみません」
リリは顔いっぱい涙を浮かべている。
それを眺めながらも、
胸に引き寄せるだけの気カがなかった。
「本当は私はあの人を見放すべきだったんです。
苦労も知らない金持の家に生まれたあの人は、
中共になってからはすっかり駄目になりました。
全然、生活能カがなくて、親に頼れなくなると
私にばっかり頼ろうとするのです。
貧乏してその日の生活に困るようになっても、
決して働こうとしないし、
私が世話をして働きに出ても、すぐまたやめてしまうのです。
もう私はあの人には愛想をつかしています。
でも私たちの間には子供がありました。
そればっかりに、私は苦労をするのです」
部屋の中はもうすっかり暗くなっている。
その暗がりの中でリリはひそやかに忍び泣いていた。
これが二人の別れの潮時かもしれない。
やがて、この自分も短い黄金時代を
あえなく閉じてしまうのだ。
もう汽船はあの砂漠に挟まれた紅悔を過ぎて
スエズ運河に近づいているはずだ。
砂漠に日が落ちて、星という星がただわけもなく
輝くようになると、地上にまた花が一輪散る。
散って風に吹かれて、
どこへともなく消え去ってしまうのだ。
何度春木は自分の秘密をリリに打ち明けようと思ったかしれない。
だが、そのたびに彼の心の中のもう一つの声にひきとめられた。
いま打ち明けたところで、それがなにになろう。
打ち明けたところで、また逆にひたかくしにかくしたところで、
時が来れば、いつか知れてしまうことだ。
物事は自然の成行きに任せるほうがいい。
この洋々たる大海にボートを浮かべて、
ただ目的もなく漂流する人間にとって、
先を急ぐ必要がどこにあろう。
それから一週間ほどたったある夕方、
突然老李から電話がかかった。
相談があるからすぐ来てくれと言う。
タクシーをホテルに乗りつけると、
老李は部屋の中で彼を待っていた。
机の上といわず、ベットの上といわず、
部屋の中は無数の荷物や包紙で取り散らかっている。
その中にうずくまって、老李は何やら片づけていた。
机の上に置かれた白い包紙は嵩の小さいわりに莫迦に重たい。
包紙の間から、小さな婦人用の金時計が何百個も覗いていた。
「もう一日二日したら、
船がカサブランカに着くことになっている」
老李は春木に椅子をすすめながら言った。
「それで僕は、一時日本に避難しようと思う」
「………」
「問題は君のことなんだが、君はどうする?」
春木は黙して語らなかった。
「もし君も一緒に行くなら、
もちろん、君の船賃ぐらいの面倒はみてあげる。
しかし、僕の考えではこの事件は君となんのかかわりもない。
警察がつかまえに来たところで、
君は使用人でなにも知らなかったと言えばよい。
あくまでそれで突っぱねるんだ」
老李の視線は射るように鋭い。
春木は直視を避けて、バルコニーのほうを眺めていた。
「実は僕にはまた別の計画がある。
それは君もだいたい感づいていると思うが、
香港と日本の間で密貿易をやるんだ。
あんまりよく事情を知らないので、
はじめは洪添財の奴を利用するが、
僕は本当のところ彼奴を信用していない。
だから、もし君がこちらにいて監視をしてくれたら、
とても助かる。
君の今後の生活の面倒も僕がみてあげられるはずだし、
そのうちに君自身も
あるていどの資金をつかむことができるようにしてあげるつもりだ」
「じゃ当分は日本にいるわけか」
「そりゃそうだよ。
うっかり帰って来たらことだからね。
洪添財は僕が帰って来られないことを知っているから、
盛んに僕に焚きつけている。
こちらに君のような人間がいなかったら、
どんなに料理しようが向うの勝手だから、
とても合作する気になれない。
とにかく頼むよ」
「で、いつ出発するんだ?」
「今夜だ」
春木は自分が本当に信用されているのかどうか判断に迷った。
もし心の底から信用しているのなら、
いよいよ出発という日になってから知らせる手はないだろう。
しかし、もし全然信用されていないのなら、
なにも今夜という今夜知らせを受けることもないわけである。
これは老李が自分を牽制して、
一人だけ香港にとどめて、
警察の餌食にするための芝居かもしれない。
自分が網にひっかかることによって
警察の眼をそらせるためかもしれない。
「とにかく、僕は香港にのこるよ」
「のこってくれるか。
それから仕事のほうも引き受けてくれるか」
「いまのところは、なんとも言えんな」
「しかし、君、今後の生活のこともあるんだぜ」
「それはわかっている」
「話はそれだけだ。
急に決めたものだから、てんやわんやだけれど、
少し荷物づくりの手伝いをしてくれないか」
その夜、十二時を過ぎてから、
添財が車を乗りつけて来た。
老李は明日の朝早く発つ飛行機で
シンガポールに帰るから、
今夜のうちに飛行場の近くにある宿屋に移ると、
ホテルの者に話してあった。
ボーイに荷物を積み込ませ、
三人の者が乗り込むと、車は夜の街を走り出した。
小雨が降り出したとみえて、
明けた車の窓から小粒の雫がとび込んできた。
濡れた道路の上をタイヤの回る音が
じーんと胸にこたえてくる。
車は人通りの少なくなった皇后道中を抜けて
いつか大鵬と二人で添財を迎えに行った、
あの建隆行という船務行の前にとまった。
薄暗い階段を上がると、
建隆行の中は密輸船に乗る人で混雑していた。
三人はそこでしばらく待たされたが、
隣合って坐った春木と老李の会話はとかく途絶えがちだった。
「では皆さん出かけましょう」
店の番頭の合図で、一同は腰を上げた。
海岸には小型のポンポン船が人々の乗り込むのを待っている。
春木も一緒になって船の中に入った。
雨はしだいに強くなって、
夜闇の中でさえ船のエンジンの音が聞こえない。
やがて波止場を離れたポンポン船は
港の真中にとまっている汽船に向かって走り出した。
船のへさきに立った水夫が懐中電燈を点滅すると、
汽船の甲板から同じような合図があった。
ポンポン船は汽船に横付けになり、
降ろされた桟橋から一人ずつ甲板へ上がって行った。
「じゃ元気で。
向うへ着いたら、また知らせるからね」
老李のさし出した手は冷たかった。
闇船の乗客たちが甲板の上に見えなくなってしまうと、
ポンポン船は汽船を離れて、また元の波止場へ戻りはじめた。
対岸の灯もあらかた消えて、
終夜つけっぱなしの広告塔だけが夜の港にあかあかと輝いている。
もう渡し船の最終時間も過ぎてしまい、
波打ちぎわはひっそりとして人影がない。
雨のそぼ降る街路の騎楼の下を春木はひとりで歩きはじめた。
老李を責める気持は不思議と湧いてこない。
人には皆それぞれの生き方がある。
今日は老李が去り、明日はやがてリリが去るだろう。
そのリリを責めることもいまの自分にはできない。
いや、もともと人間は誰をも責めることはできないのだ。
それにしても、自由への道はなんと残酷な道であろうか。
小説「香港」完結
|