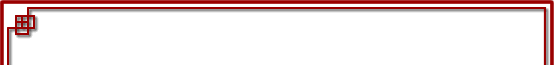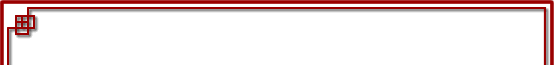|
私は人間の思想は、たとえいかに高邁なものであろうとも、その人間の環境や肉体的な構造、たとえば腺病質であるとか、胃弱であるとかいった卑近なことと離れてありえないと考えたがる傾向があるので、この偶然の符号からひょっとしたら「どもりの哲学」というものがあるのではないかしら、とひとしきり考えさせられた。
人間、肉体のある部分が故障を起こすとか不完全であるとかすると、他の部分がこの欠陥を補おうとする。耳が遠いと、目がよくきくとか、字が読めないと、記憶カがすばらしいとかいったぐあいである。「健康という名の救うべからざる病」などという逆説的な表現を可能ならしめるのは、芸術や学問の要求する異常なる才能が、こうした異常な環境や肉体的条件から生まれるものだからであろう。
たとえば弁舌の才は、頭脳と舌が直結したような才能で、この種の才能は短距離選手のごときみごとさをもっているが、どうしても頭脳の回転率が舌の回転率にひきずられてしまうので、古来、弁舌さわやかな者にはあまり賢人が見当たらない。その点、どもりの舌か滑りすぎる心配はまずないから、いきおい内攻的とならざるをえず、それが頭のなかを何百何千回となく駆け巡って、やがて文章となって現われてくるときは、ちょうど、クモが糸を吐くように一糸乱れず流れ出てくるのではあるまいか。少なくとも、韓非やモームの文章にはそういった論理性があるように私には思われるのである。
しかし、二千年以上もむかしに書かれた『韓非子』が、今日あたかも現代杜会について語っているかのようにわれわれの耳目に新しいのは、もとよりその論理性によるものではなく、人間に対する無情無感動なまでに徹底した鋭い観察眼にあることはいうまでもない。
その根底に横たわっているのは、「人間はみな利己的なものであり、正義のために動くよりは自已の利益打算のために動く」という人間観であり、「人間の良心よりも機構に依存しようとする」彼の政治理論や、「もし徳のあるものが絶対的ならば、孔子が自分よりもはるかに凡庸な魯の君主哀公にぺこぺこするはずがない」という道徳否定論や、あるいは「温情主義は水のようなもので、世に水におぼれる者は多いが、厳罰主義は火のようなものであるから、火に焼かれるものは少ない」という重刑主義は、いずれもこの人間観の上に築かれたものである。
こうした非情な社会観ないし政治思想が、キリストの誕生以前にすでに東洋の杜会に存在していたこと自体が驚くべき事実であるが、もっと驚くべき事実は、こうした思想が存在したにもかかわらず、韓非を代表とする法家思想が一種の毒薬として敬遠され、代わりに仁義をモットーとする儒家の思想が一貫して為政者から支持されてきたということであろう。思うにこれは為政者が本来、道徳を愛する正義の士だったからではなく、彼ら自身が利己的な人間で「なんじら臣民ども」を縛ることには必ずしも躊躇しないが、自分らが縛られることはご免だったからにちがいない。この意味で、孔子の偶像化は、孔子が木偶の坊だったからであると見ることもできるのである。
この傾向はひとり中国の特殊現象でなく、ヨーロッパでも、キリストがこの役割を果たしてきた。そして、キリストの誕生から千五百年もたって、マキァヴェリーがイタリアの一角で『韓非子』的な政治理論を展開した。マキァヴェリーに対する、主として口ーマ法王側からの非難が誤解の上に立っているように、韓非の場合にも誤解が多いけれども、その非難の強烈さは、それだけ韓非理論が人間性の一面を鋭くついていることを物語るものであろう。
|