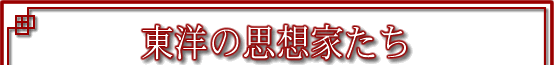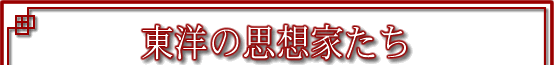|
東洋の古典は、たいてい体系的な著述を目的として書かれてはおらず、当人の言行録を後になって集めたものが多い。『韓非子』の場合もその例にもれず、必要に応じて叙述したものを寄せ集めているために、順序が前後しているばかりでなく、随所に重複があり、それがこの書物を実際以上に読みづらくしている。また自分の思想を表明する代わりに、実際例を羅列してこれに代えている場合も多い。
この一文を書くにあたって、私は読者に与える混乱を避けるために、順序をまったく無視し、できるだけ、彼の思想や基本的なものの考え方を中心にして整理することに努めた。
さきにも述べたように、秦の始皇帝は韓非の文章を愛したが、その後、秦に討韓の議が起こったとき、それまで韓の国内でまったく無視されていた韓非は「時の人」としてにわかに脚光を浴び、「韓の討つべからざること」を始皇帝に説くために、韓王の全権として秦に派遣されることになった。
『韓非子』の開巻第一ぺージは「初見秦」(はじめて秦にまみゆ)で始まるが、これは韓非が毒殺される少し前のことであり、後人の偽作、あるいは『戦国策秦策』にのせられた張儀の建言のひき写しであるともいわれているが、いずれにしても韓非の人生にとっては最後の部分であろう。したがって、韓非の思想を知るうえには、必ずしも重要な意味をもっていないのである。
さて、『韓非子』の全巻を通読しながら、私が絶えず連想したのは、西洋における近代経済学の生成過程においてアダム・スミスやリカルドによって受け入れられた「ホモ・エコノミクス」、いわゆる「経済人」の概念であった。スミスやリカルドは経済行為が一定の合理性に従って行なわれているのに着目し、このような経済行為の主体として、自己の利益の極大化だけを目的として純粋に合理的に行動する人間を想定した。
このことはもちろん、人間が利己的な動機のみによって動くものではないという、人間性の別の面を否定するものではない。
ただ「人間の頭も、豚の鼻と同じく、要するに食物をさがすためにある」ことが事実だとすれば、豚が他の豚を押しのけて食物にありつこうとするように、人間もまた他の人間を押しのけるものであると考えたほうがよさそうである。
|