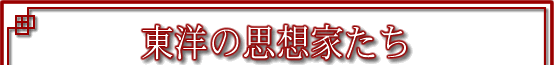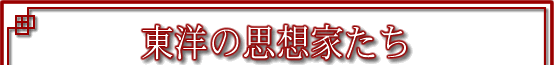|
以上述べてきたところからもだいたい想像がつくように、『荘子』の哲学は当時、世に行なわれていたものの考え方をはじめから終わりまで一つのこらずひっくり返して見せたものである。これはちょうど、ジャン・ジャック・ルッソオが「自然に帰れ」を叫んだのと一脈相通ずるものがある。皮肉屋のヴォルテールは「ルッソオの書いたものを読んでいると、四ツ足になって歩きたくなる」と評したが、荘子の場合もこれに似たような批評が可能であろう。ただ荘子は四ツ足よりももっとずっと古い天地の歴史のそもそものはじまり、いや、はじめも終わりもない混沌そのものまでさかのぼっているので「読んでいるうちに雲や霧になって消えてしまいたくなる」と言ったほうがより妥当かもしれない。
後世、役人の寸法に合わず、出世を断念した連中や小説を書いて戯作者の生涯を終えた連中が『荘子』を読んでいるうちにしだいに神秘の世界へ迷い込んでいって、ついには彼らの作中人物に羽化登仙をさせて空想世界に遊ばせるようになったのはけっして偶然ではない。そうした荘子の支持者が落第坊主の集まりであったがために、『荘子』の哲学が落第坊主の哲学のごとく考えられ、ひいては荘子自身が人生の落第坊主のごとく考えられるようになったが、実際の荘子がおそらくはまったくその反対であったことは彼の文章からも、その言行からもじゅうぶんに推察のつくところである。
荘子が楚王の招聘に応じなかった話も、彼が意外に自我の強い硬骨漢であったことを示しているが、『荘子』のなかにはこのほかに似たような話がいくつか出てくる。たとえば、
「宋の人で曹商という者があった。宋王のために秦に使いし、行くときは車数乗であったが、秦王は彼を喜び車を百乗にしてくれた。そこで宋に帰ってから荘子に自慢してこう言った。
"貧乏して裏長屋に住み、青白い顔をして靴を織ったりするのは不得手ですが、万乗の君主を説いて、たちまち百乗の従者を従える身分になるのはやさしいことですね"
"秦王は病気で諸国から名医を集めているそうじゃないか"
と荘子は言い返した。
"腫物をつぶしてなおした者には車一乗、痔をなめた者は車五乗。下がれば下がるほど車が多いそうだ。あなたにそんなにたくさん車をくれたところをみると、痔でもなおしてあげたのですかね。さあ、たったいま、この家から出て行ってください"」(列禦寇第三十二)
かように荘子は名利に背中を向け、自分の才能が名利をもたらすことを極端に警戒した。
そのため実際的な手腕を発揮する余地を失ったが、だからといって、荘子が実際家でなかったということにはならないであろう。
|