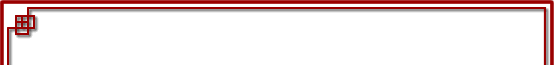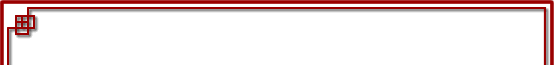|
モームの作品を読んだのも、また、『韓非子』のような文章的(思想的ではない)に難解な書物を読んだのも、実はこうした気まぐれな読書癖に出発しているのであるが、どういうわけだか、この、時代も生まれも作風も違う二人の人間に、私は奇妙な共通点を感ずるのである。
いちばん最初にひっかかったのは、モームも韓非子もともにどもりだということであった。あらゆる天才は気違いに似ているが、あらゆる気違いが必ずしも天才ではないように、たんにどもりであるというたわいのない類似点を、比較思想学(?)の出発点とすることは、もとより危険なことである。しかし、似たような骨相の持主が似たような性格の持主であることは、われわれが日常生活上非常にしばしば経験するところであり、いわゆる人相学もそうした経験に基づいて帰納的に形作られてきたものである。そして、それは人類史上きわめて重要な地位を占めた時代があったし、易学とともに、賢人に必要な学問ないし特技とさえ思われていた。
それがマツリゴトの殿上からついには大道まで追い落とされたのは、本来、性格学であるべきものから、過去・現在・未来を貫く人間の運命を占う、身のほど知らずの予言学になろうとしたからであると、私は考えている。自分の書いた一群の小説に自ら「人間喜劇」という表題をつけたバルザックでさえも「十九世紀において最も発達しなかった科学は骨相学である」と書いていたのを、彼の小説のどこかで読んだ記憶があるが、どういうわけだか私には、どもりという事実からの連想を打ち消そうとしてもなかなか打ち消すことができないのである。
いまをへだたる二千二百年のむかし、中国の歴史上でいえば、いわゆる戦国時代に、韓非は弱小国韓の王族の一人として生まれた。当時、韓は諸列強にはさまれ、隣接する秦の保護国になることによって辛うじて滅亡を免れていた。韓非は生来のどもりで、自分の思うことを満足に表現するだけの弁舌の才にすら恵まれていなかったが、この情勢に憤懣やるかたなく、しばしば、富国強兵の策を韓王に上書した。が、もちろんまったくいれられなかった。
ところが、彼の書いた「孤憤(こふん)」とか「五蠹(ごと)」とかいった文章を秦に持って行った者があって、それが始皇帝の目にとまった。始皇帝は一読、その才を賞嘆して、「ああ、寡人(わし)は、この人と交遊することができたら死んでも本望だ」と言ったと伝えられている。
これはいうまでもなく中国流の文学的表現であるが、今日、彼の著作としてのこされている『韓非子』を読むと、理路整然、林語堂氏のことばをかりるならば、「中国人の思考方法というよりはむしろドイツ人の精神の典型ともいうべき理論」が展開されている。ただ韓非をドイツ人から区別するところのものは、彼が本能的に抽象性を嫌悪したことであって、現実から遊離した理論遊戯の形跡はまったく認められない。
『韓非子』は戦前、廖文奎博士によって英訳され、ロンドンで出版されたことがある。それが惰性でものを読むモーム先生の目にふれる機会はじゅうぶんあったと考えられるが、実際にモームが『韓非子』を読んだかどうか、それによって影響を受けたかどうかは、この場合、さして重要なことではないだろう。私にとって興味のあることは、きわめてシニカルな人間観察家として定評があり、自ら「想像力には欠けているが、論理的な頭を持っている」と称するモームが、どもりのためにたいへん苦労したという事実である。これはあるいはたんなる偶然の符号であるかもしれないが、しかし、偶然にしては、ちょっとおもしろすぎる符号なのである。
|