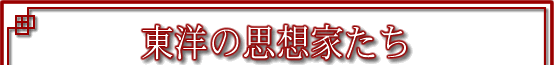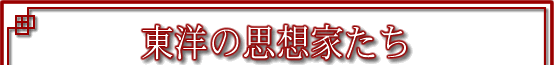こういう書き方をすると、孔子およびその門弟たちが諸国を歴遊するありさまはどことなく、やくざがわらじをはく姿を彷彿させる。ふつうのやくざと違うところは、切った張ったがないこと、博打をやらないことだが、その代わりに学問の押し売りをやる。
「毎日、腹いっぱい食ってなにもしないでいるのはむずかしいことだ。世に博打うちというのがあるだろう。あのほうがなにもしないでいるよりはまだ賢い」
と孔子は『論語』のなかで述べている。これを見てもわかるように、押し売りをして歩くほうが家の中でじっとしているよりはよいと考えたのである。この意味で、孔子とその門弟はふつうのやくざではなかったが、「インテリやくざ」と名づけられる部類に入るであろう。同じ徒党を組むにしても、彼らには誇りがあったので、君子やくざは「和して党せず」、つまり正義という共通の目的のもとに集まっているが、グルになって悪事を働くやくざではないと主張するのである。だから、やくざでいえば、孔子一家、相撲でいえば、孔子部屋、といわれても、ムカッ腹をたてるほどのことはない。
さて、孔子部屋の親方はもちろん孔子であるが、後世、孔子が伝説上の聖人君子になったのは、彼自身の力というよりは彼の「後生畏るべき」弟子たちのしわざであった。
門弟三千人は白髪三千丈と数字までピタリと一致する。しかし、孔子が指折り数えた弟子の実数は七十七人で、部屋としてけっして小さなものではなかった。
そのなかでも最も人間的に愛敬のあるのはおそらく子路であろう。子路は孔子より九歳下で、孔子がまだ比較的無名だったころからの弟子である。孔子が文学青年上がりの、いい意味でも悪い意味でもインテリだったのに比べて、子路は少し頭は足りないが、蛮勇型の正直な男であった。おそらく腕っぷしもそれ相当に強かったであろう。孔子の悪口を言うものがあると、すぐ腕をまくったので、「子路を弟子にしてからは、自分の悪ロが聞こえなくなった」と孔子は言っている。これはそれ以前には孔子に面と向かって毒づく人間が多かったという意味ではあっても、それ以後、孔子の悪口を言うものがなくなったという意味ではもとよりない。しかし、面と向かって悪口を言われて気持のよい人間はいないのであるから、孔子はよい弟子ができたと喜んだにちがいないのである。
孔子は子路を連れて諸国を流浪してまわった。子路は怒りん坊であったが、根が単純な男だから、自分の師匠ほど偉い人間はないと思い込んでいる。その代わり、孔子が聖人君子らしからぬふるまいに出ると、むきになって孔子に食ってかかった。孔子が叛乱者の政治顧問になろうとしたときや、南子に会いに行ったときなど、子路の反撃にあった孔子はさぞかし面喰ったことであろう。しかし、子路の喜怒哀楽はピアノの鍵をたたくように、どの鍵をたたけばどの音が出るか、きわめて正確なものであったから、孔子にとってはむしろ神経の疲れない相手であった。でなければ、気難し屋の孔子とウマを合わせていけたはずがないのである。
「自分の弟子のなかで、早いころの弟子は礼楽に対してはまるで野人であるが、後になってからできた弟子はまるで君子だ。しかし、どっちをとるかといえば、わしはむしろ野人のほうをとる」
と言っているように、孔子は自分に最も欠けた野人的性格に魅力を感じたのである。そのくせ子路を小バカにした態度を再三ならずとった。
「子路よ、琴を弾くのは自分の家に帰ってからにせい。おまえの琴を聞くと胸くそが悪くなる」
それは子路が無器用だったからと解することもできるが、子路の蛮勇は自分に見えないところでふるえ、と言っているようにも聞こえる。しかも子路を扱う態度がきわめて粗暴なので、他の弟子までが子路を軽蔑した。それに気づくと、孔子は言った。
「子路は人間としては、御殿の中に入っているが、奥の部屋の中に入っていないだけのことだ。そうバカにしたものではないぞ」
しかし、孔子は子路のような男はりっぱな判断力と自制心がなければ、いまにひどい過ちを起こすだろうと考えていた。もう少し他人の言うことに耳を傾けなさいと教えたが、持って生まれた性格はなかなか直るものでない。
「あの男はきっとまともな死に方をしないであろう」
と孔子は予言している。 |