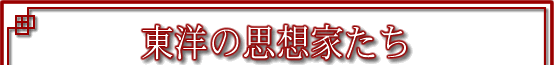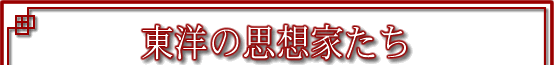孔子は徹底的なリアリストであったがゆえに、いかなる定見にもとらわれなかった。新しい行動をとる必要が起こると、自分のふだんの言動を裏切るようなことを平気でした。
長い、苦い体験の結果、孔子は人間社会に対する一種の設計図を自分の胸の中に作りあげている。彼が裏切行為に出る場合はたいてい、この設計図を実際に施工に移す可能性が現われた場合である。だから、自分の理想を実現するという一点に集中して考えれば、孔子はきわめて純粋な男であったし、自己に忠実であったということができる。
しからば孔子の社会設計図とはどんなものであっただろうか。
われわれは従来、孔子の教えは「徳政」を行なうことであると教えられてきている。徳の問題は個人に出発し、対家族、対国家、対世界の関係として現われる。その場合、孔子は「君は君らしく、臣は臣らしく」と言い、臣下の者が叛乱を起こして、王侯を退けるのを徳に反する行為として、非難しているため、孔子というやつは封建制度の擁護者にすぎないと考えがちである。
ところが『論語』に出ているかぎりでは、孔子が帝王神権説を唱えた証拠はなく、むしろ王侯を槍玉にあげている。たとえば彼自身、齊の景公に仕官しようとして頭を下げに行ったことがあるが、「景公は死んだとき、馬四千頭を蓄えるほどの富があったが、人民はだれも徳のある王とは言わなかった。伯夷・叔齊は首陽山の麓で餓死したが、今日に至るもまだ賞賛の的になっている」と辛辣な批評をくだしている。また、自分の弟子の「冉雍(ぜんよう)は王様になるだけの資格をもっている」と言っている。
これは王たる者は徳をもつべし、あるいは逆に徳のあるものを王とすべし、という見解であるが、叛乱者はいけない、という考え方と明らかに矛盾する。少なくとも理詰めでしかものを考えることのできない人間はそう思う。ところが、孔子自身はおそらく矛盾するとは考えなかったにちがいない。それはその場その場で判断すべき問題であって、もし悪徳の王ならこれを討ってもさしつかえないが、討ってこれに替わった男も同じような悪人なら、叛乱者はいけない、としているのである。しかし、実際問題としては、王を討ってこれに替わった男もたいてい悪人であったにちがいない。替わっても替わっても同じことが繰り返されるために、こんなことなら、王を替えるよりは、王に徳を仕込んだほうがよいと孔子が考えるようになったのだと私は解釈している。
私がそう解釈する根拠は、若いころの孔子は礼に関する自分の知識をふりまわしたが、徳の押し売りはしなかったからである。その彼が徳を強調し、求道精神を発揮しはじめたとき、われわれは彼に「偉大さ」を感ずるよりはむしろ「年」を感ずるのである。 |