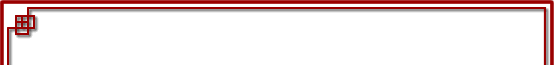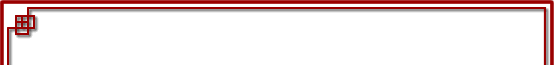市井の人に多少の人気があり、権力者から相手にされなければ、後進の教育に力こぶでも入れようと考えるのが常道である。孔子も諸国を流浪しながら、門弟の教育を続けた。
門弟のほうは孔子のようにお高くとまる必要はなかったから、それぞれの分に応じてあちらこちらに就職する。弟子が出世すれば、師匠の値打ちもしだいに上がっていくのだから、もって瞑すべしといいたいところだが、孔子は死ぬまで満足することを知らない、あきらめの悪い男であった。
「五十にして天命を知る」と彼自身は言っているが、彼の自信の強さから推せば、多くの中国人が考えているような運命論ではなくて、自分には使命があるという確信のほうと解釈したほうが正しそうである。
なぜならば、「心の欲するところに従っても、矩を踰えない」七十を過ぎてからも、彼はお隣の齊で内乱が起こると、ただちに斎戒沐浴して自国の君主哀公に開戦を勧告に出かけているからである。「大義名分を立てるため」と漢学者先生はいかれっぱなしの解釈をしているが、自国で起こった叛乱の首謀者の政治顧問にさえなろうとした変幻自在の男が、そんな単純な動機から主戦論を唱えるはずがない。自衛のためでない戦争、聖戦と名のつかない戦争は人類史上かつてあった試しがないのである。
哀公は当惑して、孔子に三人の家老に相談に行くように命じた。
孔子は御前をさがると、弟子たちに向かって不平そうに言った。
「わたしは大夫の末席をけがしたものとして当然のことを進言したのに」
三人の家老はもちろん、孔子の意見など問題にしなかった。これは孔子の死ぬ二年前のことであり、「死んでもラッパ」ということばこそ、孔子の一生を飾るにふさわしいことばである。
しかし、こうした現世的な欲望、生きているうちに宰相の地位に上って辣腕をふるい、名声を上げたいという肉欲よりも強い欲求が、孔子の思想体系を形づくるうえで、おそらくは最も大きな力となっているのである。
われわれの文明の最も強烈な特徴は、米の飯を食うにしろ、酒に酔っぱらってばかりいるにしろ、あくまでも現世派であるということであろう。
孔子は、妖怪変化や超人的な力や、われわれの推理力を乱す出来事や死んだ人については、いっさい語ることを好まなかった。それは中国人の社会にそんなものが存在しないとか、また中国人がそれに興味をもたないというのではなくて、むしろその逆である。ただ孔子は人間の想像力に訴える代わりに、われわれの思考力で解釈のつかない出来事は、いっさい受け付けようとしなかったのである。
かつて子路が、死んだ人をどう扱ったらよいかときいたことがあった。孔子はこう答えた。
「わしは生きた人間を取り扱うことさえできないでいる。どうして死んだ人の取り扱いができるかね?」
「じゃ、人間死んだらどうなるんでしょうか」
「生きるということさえわからないのに、死んでから先のことがわかるかい」
この、知らないことは知らないこととしておく不可知論の立場は、一種の合理主義精神である。それは西洋的な意味における宗教とは本質的に別個のものであり、むしろギリシャ文明に近い。西欧においては文芸復興以後の精神であるのに、それが中国において終始一貫知識人の立場であったのは、偉大なる教祖が生まれて凡庸なる大衆がこれに続いたのではなく、孔子が中国人的気質の一方の代表選手であったからと考えざるをえない。もしそうだとすれば、中国人にとって最も理解されがたい、極言すれば、中国人に無縁なものは、共産主義ではなくて、むしろキリスト教であるといえるのである。なぜならば、共産主義の立場もまた、現世派と同じ基盤の上に立っており、人間のことは人間の力で解決しようとしているからである。 |