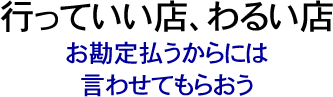
自腹ゆえに本音、愛するがゆえに辛口。
友里征耶さんの美味求真
|
第382回 先日ある新聞に、フランスのウナギの稚魚が激減しているという いつの間にか、ウナギの養殖までもが しかし、私はひっかかるのです。 つまり、大半の日本人が現在口にしているウナギは、 |
| ←前回記事へ |
2004年7月31日(土) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
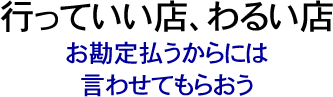
自腹ゆえに本音、愛するがゆえに辛口。
友里征耶さんの美味求真
|
第382回 先日ある新聞に、フランスのウナギの稚魚が激減しているという いつの間にか、ウナギの養殖までもが しかし、私はひっかかるのです。 つまり、大半の日本人が現在口にしているウナギは、 |
| ←前回記事へ |
2004年7月31日(土) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |