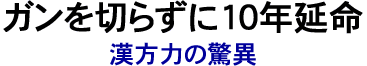|
第203回
名作文学と<心のエンパワー>
あなたも、欧米借り物の勉強をするだけではなく、
自分のいのちの日記、いや、
自分の言葉で<いのちの物語を創る>ことを
クセにしてみませんか?――
わが身やわがいのちに照らして
≪自分の身体用語でいのちを語る≫=
<ナラティヴ・アプローチ>をすれば、
他人任せではない、自分好みの<エンパワー>=自己実現能力が、
必ず、つかめるはずだ――
前回まで、こんな話を書いておりましたら、
じつに、ナラティヴでエンパワーに満ちた
新刊書が贈られてきました。
「名作にひそむ
涙が流れる一行」という、
ユニークなタイトルで、260万部ベストセラー
『声に出して読みたい日本語』の著者・齋藤孝さんの新刊です。
樋口一葉、夏目漱石、島崎藤村、八木重吉から
山本周五郎、遠藤周作、宮本輝、村上春樹、
浅田次郎、吉本ばななまで・・・
古典、現代、また文学、詩歌を問わずに選りすぐった名作から、
「涙が流れる一行」をピックアップしたという内容ですから、
若い人はもちろん、僕のような中高年にもとても面白い本です。
たとえば、以下のように、
名作の「涙が流れる一行」が次々と展開します。
<お米がいっぱい詰まっている米櫃に、
手ェ入れて温もってる時がいちばんしあわせや。
・・・うちの母ちゃん、そない言うていたわ>
(宮本輝・著『泥の川』)
<帰りには寒さの身にしみて手も足も亀(かじ)かみたれば
五六軒隔てし溝板の上の氷にすべり、
足溜りなく転(こ)ける機会(はずみ)に手の物を取落して、
一枚はづれし溝板のひまよりざらざらと翻(こぼ)れ入れば、
下は行水(ゆくみず)きたなき溝泥なり、
幾度も覗いては見たれど是れをば何として拾はれませう>
(樋口一葉・著)『にごりえ』)
――といった箇所を取り上げて、
「樋口一葉の小説はストーリーだけでなく、
文章自体がいまや誰も書くことができないような
水準の日本語で書かれているのが
素晴らしいのです」と、著者は
日本文化の伝承的特性の素晴らしさを評しています。
<こころよ では いっておいで
しかし またもどっておいでね
やっぱり ここが いいのだに
こころよ では 行っておいで>
(八木重吉の「心 よ」)
この詩には、著者は
「自分が自分の味方であると考えられるのは、すごく大事です。
生きていくうえで、
自分が自分の味方でなくなってしまったらつらい。(略)
心が揺らいで(略)不安になった瞬間にこの詩を読むと、
自分というものを取り戻せるのではないかと思います」
とアドバイスしています。
単なる名作文学ガイドや作品論ではなく、
いま私たちの生活の中に必要なものはなにか?
僕流に感想を述べさせてもらえば、
親も子も含めて、いまの日本人が忘れかけている、
<ナラティヴ・アプローチ>=≪自分の身体用語でいのちを語る≫
≪日本の伝承風土に根ざした物語性を見直す≫・・・
この大切さを改めてメッセージした、
珠玉のエッセイであり、とても読んだ後味のよい人生読本です。
お奨めの1冊です。
|