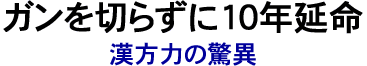|
第83回
週1の「ベジタリアン」のすすめ
マクロビオティック玄米菜食法の奥義は、
「健康と平和」にあり――、
「肉食過食主義」から「菜食見直し主義」に変えると、
美容や病気治しばかりか、一人一人の心身の平安、
さらに地球上の紛争も和らげることができるはずだ――
という話の続きです。
前回、厳しくマクロビオティック玄米菜食法をやらないにしても、
週1の「ベジタリアン」でもよい――、
あなたも挑戦してみてはどうでしょうか?と提案しましたが、
世の中を大きく変えるような歴史上の大人物の中には、
意外とベジタリアン=菜食主義者が多いのですね。
とかく歴史書や小説やテレビドラマで取り上げられる
歴史上の大人物といえば、戦争巧者の武将や軍人とか、
大帝国の国王や宰相など
「闘争型」の人物ばかりがもてはやされますが、
じつは、長い長い歴史の間で、
人間の英知を輝かせて歴史を変えた
「和平型」の人たちはたくさんいるわけです。
もちろん、すべてというわけではありませんが、
そうした和平型・平和派の人物には、
ベジタリアン=菜食主義者が多いことに、
注目したいと思います。
日本人にしても、長い間、穀物菜食を中心とする
いわゆる「ベジタリアン」といってもよい
食生活をしていたのですが、
明治維新以降、欧米に追いつき追い越せというわけで、
国家体制、いや、大衆の風俗・生活や食スタイルも激変。
とくに食事における肉類、乳製品類の過食化と共に、
富国強兵、国威発揚を旨とする
「抗戦型」思考が蔓延したといってもよいと思います。
「肉を食べないから日本の体格が劣っている」
「肉を食べないと頭が悪くなる」といった風潮です。
これは、つい100年ほど前の話です。
近代日本史の中で、日本を抗戦型の熱狂の渦に巻き込んだ
最初の大戦争が、100年前の日露戦争でしょう。
おそらく、国民をして「神風ニッポン」の幻想に酔わせ、
「神聖天皇制」を確固とさせる端緒となった
大戦争といえましょうが、
一方で、明治末期から大正期、知識人の間で
ロシアの文豪・トルストイの共鳴する人道主義に共鳴する
日本の自由人たちが現われました。
トルストイ主義とは
(1)暴力を持って悪に抗するなかれ
(2)怒るなかれ
(3)姦淫するなかれ
(4)誓うなかれ
(5)汝の隣人を愛し同胞を裁くなかれ
・・・・として有名ですが、
まさに「食事と平和」に沿った発想法でした。
このトルストイ主義に影響されて、非戦・自由平等を貫き、
菜食主義を理想とした人に、詩人の宮沢賢治や
インドの無抵抗主義者のマハトマ・ガンジーがおりました。
また、拙著「大正霊戦記―大逆事件異聞
沖野岩三郎伝」
でも取り上げた、「非戦・自由・平等」の運動を続けた、
大正期の牧師・社会活動家の賀川豊彦らがいたわけです。
時代をさかのぼれば、仏陀、イエス・キリスト、モーゼ、
ピタゴラス、ダーウィン、レオナルド・ダ・ヴィンチも
ベジタリアンだといわれています。
まあ、聖人や高僧のように、
厳しく玄米菜食修行をすることはありませんが、
健康、さらに動物愛護や環境保全のみならず、平和のためにも、
これからは、週1の「ベジタリアン」は奨めたいと思います。
|