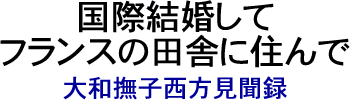|
第131回
もう少し130回の続き…
「暴力」の嵐も、
ようやく3週間目に入ってかなり落ち着いてきました。
夜間外出禁止令など、
まだしばらくは特定の措置が続くかもしれませんが、
2週間前の週末のような事態に陥るようなことはないでしょう。
それにしても日本を始め、アメリカやオーストラリアなどでは、
かなりセンセーショナルに報じられた感があります。
その点ヨーロッパ内では概ね冷静な受け止め方だったのと、
当のフランス国内での反応も
10年前に比べ随分冷静に問題の根っこの「差別」を
正面から議論するようになったかもしれません。
この6月に日本の友人がいろいろ
(もちろん重いので文庫を主に頼んだのですが)と
本を持って来てくれました。
そのなかに1994年初版の
『素顔のフランス通信』(晶文社、飛幡祐規著)
というのがありました。
「少し古いけれど役に立つかもしれないと思って」と友人。
さすがに10年前とずれはありましたが、面白い発見もしました。
特に『[移民]新世代の若者たち』と題された章です。
90年代初頭にも同じようなことが起こっていました。
やはり場所はパリ郊外のシテと呼ばれる大型公共団地。
86年には警察官に殴り殺された青年がいたり、
91年3月には
「スーパーマーケット内のカフェテリアで、
マグレバン二世の青年が警備員に射殺される」
とか、同年5月は
「同じくイヴリンヌ県のマント・ラ・ジョリで、
警察に検挙されたマグレバン二世の若者が
交番で死亡(殴られたうえ、持病の喘息の薬を与えられなかった)」
などなど。当然抗議行動が起こっていました。
「ところがメディアはその背景や事実分析よりも、
センセーショナルなインパクトを優先する」
とありました。
警察官との衝突場面や焼かれた車の画像を多く流したわけです。
その結果、一般の人々の中に
移民に対するさらなる偏見を助長し、
移民排斥を唱えるル・ペン氏率いる
フロン・ナショナル(国民戦線)の極右勢力を勢いつかせている、
というようなことが書かれていました。
90年初頭、フランスは私にとってまだまだ遠い国でした。
何回も旅行や取材で訪れていましたが、
深く関わってはいませんでした。
95年以降状況は一変しましたが、
住んだのはメトロポールから遠く離れた孤島。
本国社会の動きとは無縁でした。
それから10年…フランスで暮らすようになりました。
比べてみると、
今回政府もメディアの対応も変わったように思えます。
暴力に訴える若者たちの声を拾ったり、
しきりと
「ディスクリミナシオンdiscrimination(差別という意)」
という言葉を使って正面から議論をしているように感じるからです。
ただメディアはこの騒ぎが収まれば
また新しい話題
(その前は鳥インフルエンザ一色だったし)に飛びつき、
一般にこの問題を伝えることはなくなるでしょう。
取り上げないから解決した、というのは違います。
根っこにある問題は10年前と何一つ変わっていないし、
前回の最後にも書きましたが、
これからも再燃する火種であるのも変わらないでしょう。
メディアは100%真実を伝えられる道具ではないし、
その情報のみを100%鵜呑みにするのも危険だと思っています。
|