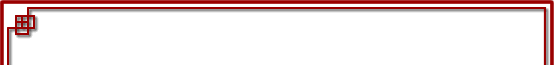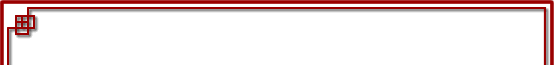|
今日、東洋の古典と考えられている書物、『論語』や『孟子』や『韓非子』を私は少年期から青年期にかけて、強制的に読まされてきた。私が通わされた日本の学校では、漢文が正科目になっていたからである。また、句読点をつけて読む日本流の漢文でなく、その本来の読み方を習う必要上、正規の学校へ通うかたわら、阿片のみで時代から取りのこされたような鬚の老先生のところへも通わされた。そのどちらも私にとっては実に退屈で、文字どおり砂をかむような仕事であった。私自身がそれらの書物の内容を理解するだけの精神年齢に達していなかったことと、教えるほうの先生が機械的な傍註学者ぞろいだったからにちがいない。
私にとっては、西洋の書物やそれから西洋風のものの考え方のほうがはるかに魅カ的であった。なかにはまったく歯の立たないものもあったけれども、歯の立つものからつぎつぎと読破していった。そのなかでも文学(詩や小説)が私にはおもしろかった。いま考えてみると、それらの書物がおもしろかったのは、自分がそれらのものとあまり密接な関係をもっていなかったせいであるらしい。というのは、自分が文筆業にたずさわるようになってからは、私はそれらの書物にもっていた興味をほとんど失ってしまったからである。今日、私が他人の書いた小説に示す興味は、同業に対する興味であって、それ以上のものでも、またそれ以下のものでもないようである。
こうした環境におかれるようになってから、私はふたたびいわゆる東洋の古典を手にとるようになった。それらのものは、今日、ほとんど顧みられなくなっているが、私にはまるで新鮮なものに感じられるのである。それだけに、なぜ人々は古典を読まなくなったのであろうか、同じことであるが、なぜ、古典はその魅力を現代人に失ったのであろうかと、いろいろな疑問が次から次へとわき起こってくる。
まず、第一に、古典の文章が今日の人々にとって難解なものになってしまったことが考えられる。それはひとり日本の現象であるのみならず、中国でも同じである。いや、中国のほうが日本よりもっとひどい。日本ではつい戦前まで漢文が正科目になっていたので、古典の上っ面をなでた人はたくさんいるが、中国ではそれを読んだことさえない人がはるかに多い。この隘路を打開することは、いずれにしても必要なことである。そして、そういう努力は、この数年来、日本では次々と行なわれるようになった。
しかし、隘路はひとり文章の問題ではないという気が私にはするのである。古典が現代人に魅力を失ったより大きな原因は、古典の儒学者流の解釈しか世に行なわれていないせいではないだろうか。たとえば、一人の孔子のまわりに儒服を背広に着かえた儒学者たちが幾重にも取り巻いている。『論語』や『春秋』は難解で、ガイドがいなければふつうの人はそこへ近づけない。近づいても、いったいそれがいかなるものであるのか正体がつかめない。そこで、ガイドたちが下手な英語を操って鎌倉の大仏の説明をするように、儒学者たちは孔子がいかに聖人君子であるかを説明する。その紋切り型の説明に愛想をつかして、人々は孔子見物はもうたくさんだと思う。なぜならば、現代人は聖人君子なんかに用はないからである。はなはだ残念なことだが、現状はそういったものではないだろうか。
私が東洋の思想的遺産の遺産目録を作る必要を感じたのは、こうした動機からであった。中国の思想といえば、数千年来、思想界の表通りを闊歩してきた儒教、すなわち孔盃の教えがなによりもまず頭に浮かんでくる。儒教は中国の科挙考試で六法全書的役割を果たしてきたぐらいだから、その相続人も多く、したがって祖述者も多い。しかし、その元祖は孔子であり、孔子の言行録は『論語』だから、『論語』をその代表に選ぶことに異存はないであろう。
次に、儒教と表裏の関係にあったものとしては、いわゆる老荘思想がある。老荘思想は、世間では老子に出発し、荘子がその相続人であることになっているが、私はこれに異論をもっている。なぜならば、孔孟を表とすれば、老荘はちょうどその裏にあたり、一枚の着物を縫う場合でも表があってはじめて裏があり、裏のほうがさきに存在して、表が後からできるとは考えられないからである。老子は孔子と同じ時代の人物で、孔子がその教えを受けたというぐあいに話はできているが、これはおそらく、老荘の徒がその狡猜な知恵を働かせて作り出したものであろう。その証拠に『論語』には隠者的人物の叙述が出てはくるが、老子的人物は登場してこず、くだって『荘子』になると、孔子が盛んに登場して、荘子の反孔子的立揚が明瞭な形で打ち出されている。また『老子』はそれが『論語』よりも古いものであることを力説する必要上、その文体は難渋、その文旨は曖昧模糊、ちょうどその主張のように混沌として思想的な体系をなさない。この意味で、老荘思想の代弁者としては『荘子』のほうが適当であると私は判断した。
儒家と並んで戦国時代に大いにふるった墨家の代表には墨子がいる。その平和主義やその兼愛思想は中国思想史上、一個の地位を占めるが、倫理的には儒家の思想とそれほど遠いところになく、したがって秦漢以後はしだいに影をひそめ、いつのまにか儒家に吸収合併されてしまった観がある。
荘子より一世紀ほど遅れて韓非子が現われる。いわゆる法家の思想には『筍子』『商子』『韓非子』などがあるが、人間が悪党であるという性悪説を基礎として、最も徹底した政治理論を展開したのは、なんといっても韓非であろう。
私は孔子、荘子、韓非の三人をそれぞれ儒家、道家、法家の代表選手とみなし、彼らの思想とその人物を私が理解した範囲内でできるだけわかりやすく、また現代人の考え方と合致する線で再現するように努めた。
ごぞんじのように、これらの古典は体系的にでき上がっておらず、順序もまた前後して配列されている。それから何千年かのアカがこれらの書物に付着している。それらを整理して、今日の人々が理解できるような形になおすことは容易なことではない。また個々の挿話としては、はなはだ機知に富んだものでも、この目的に必要でないものは割愛せざるをえなかった。
かような試みがどれだけ読者の共感を呼びうるかは、いまのところまったく未知数である。
ことに荘子のように、理論的な頭脳を逆用してことさらに混然とした文章を仕立てた男は、こうした企てを笑うにちがいない。彼は実に用心深い男で、自分の文章やものの考え方に反対する人間のために、応帝王篇の最後に次のような寓話を残している。
「南海の帝を儵(しゅく)といい、北海の帝を忽といい、中央の帝を渾沌という。あるとき、儵と忽が渾沌のところでいっしょになった。渾沌は二人を丁重にもてなしたので、二人は恩返しをしようと相談してこう言った。"人間はみな七つの穴があって、ものを見たり、聞いたり、食ったり、呼吸したりすることができるのに、渾沌にはそれがない。ひとつ穴をこしらえてやろうか"。
そこで二人は一日に一つずつ穴をこしらえてやったが、七日にしてそれができ上がると、渾沌は死んでしまったのである」
この話と同じように、混沌とした古典に目鼻をつけようと努力したことがかえって古典を殺すような結果にならないともかぎらない。もしそうお感じになる方があれば、幸い原本はまだ目の届くところにあるから、それに直接ぶつかることをお勧めする。反対に、私の書物から興味を刺戟された場合にも同じことをお勧めしたい。
さて、以上のような計画を私が立てたのは、ちょうどいまから二年前であった。むかしは原稿料とか発表機関とかいうものがなかったので、そんなものを最初から間題にしないでただちに仕事にかかることができたにちがいないが、今日はそうもいかない。私はまず「論語」から書きはじめ、その前半ができ上がったときに、どこか適当な舞台はないものだろうかとある人のところへ相談に行った。すると、その人は「試みはおもしろいが、いまのジャーナリズムの状態では、日本国じゅうさがしまわっても、それを載せてくれる商業雑誌はないだろう」と言った。私はそれを信ぜず、「この雑誌ならあるいは」と思ったところへ自分で持ち込んだ。返事がくるまでのあいだに私は『論語』を全部書きあげ、さらに「荘子」にかかった。ところが、そこへ原稿を返してきたので、とたんに腰がくだけてあとが続かなくなってしまった。
そのことを新小説社の島源四郎さんに話すと、島さんはうちの雑誌に載せましょうと言ってくれた。『大衆文芸』は商業雑誌でないから私の懐にはいい影響はないが、いつまでも机の中にしまっておくよりはよいかもしれない。私は自分の書いたものがはじめて活字になるときのような気分で校正刷に目をとおした。雑誌ができ上がってからまもなく池島信平さんに会うと、
池島さんは「あれは題がいい。"私の韓非子"を書かないか」とすすめてくれた。そのついでに、「あんたは編集者を怒っているね」と言った。編集者を怒るのははやらない作家にありがちなことだから、当然のことを言われたようなものだが、私はなんのことだかわけがわからなくて目を白黒させた。あとになって気づいたことだが、私は孔子を売れない小説家にたとえて編集者に文句を言わせていたのである。
私はいくらか気をとりなおして「韓非子」を書こうと努力した。しかし、意外に手数がかかって、ようやくそれができたのは半年もたってからであった。「私の韓非子」は昭和三十二年四月号の『文藝春秋』に掲載されて、商業雑誌が必ずしもこうした試みを受けつけないものではないことを立証したが、枚数を制限されて、自分が最初に書きたいと思ったものとはだいぶ違ったものになったので、機会があれば、もう一度やりなおしたいと私は考えた。
幸か不幸か、その後、私は注文原稿に忙殺されて、ほとんど自分の思う仕事に手がつかない。そうなると不思議なもので、自分勝手な仕事が無性にやりたくなる。歳末から正月にかけて印刷所の連中が酒に酔っぱらっているあいだに、私は「韓非子」にとりかかった。私は一日に一節ずつ、渾沌に穴をあけるように「私の韓非子」を書いていったが、「日本読書新聞」にその連載の第一回が載るまでには全部書きあげてしまった。
その手口を覚えた私は、一月の仕事を二十日までに片づけて、それから「私の荘子」にとりかかった。本は以前に読んで、だいたいの構想はできているのだが、荘子という男は実に手数のかかる男である。渺(びょう)々然としてつかみどころがないくせに、ちゃんと予防線をはることを忘れていない。それでも、どうやら目鼻をつけるところまできたが、そこで私はまた考えた。荘子は孔子のように売り込みに行かなかったばかりでなく、買いにきた奴まで追っ払っている。
彼に忠実ならんとすれば、私もこの文章だけは売り込みに行かないことにしなければならない。
しかし、私は荘子ほど毅然とした硬骨漢ではないから、買いに来た出版社まで追っ払う気にはとてもなれない。この本が世に出るゆえんである。
(一九五八年六月一日)
|