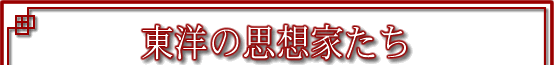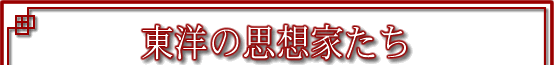|
「楚の人で和氏(かし)という者が楚の山中で玉の鉱石を得た。そこで楚の厲王(れいおう)に献じた。厲王が玉をみがく職人を呼んで鑑定させると、これは石ですと言われた。王は和氏が自分を偽ったと思い、その左足の筋を切った。厲王が死去し、武王が即位すると、和氏はまた同じ玉鉱石を献じた。武王が職人を呼んで鑑定させると、またしても、とるにたらぬ石です、と言われた。そこで王はその右足の筋を切らせた。武王が死去して文王が即位すると、和氏はその玉鉱石をいだいて楚山のふもとで泣くこと三日三晩、涙につぐに血をもってした。
それを伝え聞いた王は人をやって、世の中で筋を切られる者は多いのに、なぜ、あなただけそんなに嘆き悲しむのですか、と聞かせた。和氏が答えて言うには、私は筋を切られることを悲しんでいるのではありません。宝玉を献じたのに石と言われ、貞士のつもりなのに詐欺師だと言われたことを悲しんでいるのです。そこで王は職人に命じて鉱石をみがかせたところ、はたして宝玉を得たので、これに和氏の璧(たま)と命名した。だいたい、珠玉は君主の求めてやまないものである。和氏の献じた玉鉱石が、たとえ見かけがよくなかったとしても、べつに害になるわけのものではなかったのに、両足を切られてからのちようやく問題とされた。宝を論ずることがいかにむずかしいものかがわかるであろう」(和氏)
君主が法術を求める気持は必ずしも宝玉を求めるほど強くない。それでどうして私利私欲の徒を禁ずることができよう。有道の士が刑罰に処せられないですんでいるとすれば、それは和氏のように、帝王術の鉱石を献じていないからにすぎない。
しかし、永いあいだ、その意見がまったく容れられなかった韓非もついに時代の脚光を浴びるときがきた。秦がその保護国同様に扱ってきた弱小国韓を討伐することになり、韓の国内で、この討伐を思いとどまらせるほど始皇帝に対して影響力をもった人物は、彼以外に考えられなかったからである。そこで韓王は韓非を召し出し、使者として秦に派遣した。
韓非は始皇帝に拝謁仰せつかった。さきにも述べたように韓非は生来のどもりであったから、おそらく「アアア……」とどもるだけで、自分の考えていることを思いどおりに述べることはできなかったにちがいない。しかし始皇帝は「孤憤」や「説難」の愛読者であったから、演出効果はむしろかえってよかったのではないかと思われる。
始皇帝は側近によって幾重にも取り囲まれていた。彼らは皇帝が眉ひとつ動かしても、またせきばらいひとつしても、その心中の変化を見破るほど神経質になっている。なかでも韓非といっしょに筍子の門に学び、同じく性悪説の主張者であり、のちに始皇帝から宰相に取り立てられた李斯(りし)は、このとき皇帝のそばに仕えていたが、早くも皇帝が韓非にほれ込んだらしいことに感づいた。宮廷に嫉妬はつきものである。もし韓非が登用されるようなことが起これば、自分らの立場が危うくなる。そこで、仲間の姚買(ようか)とともに、韓非をそしって言った。
「韓非は韓国の公子の末流であります。王がいま、天下統一の大望をもたれているときに、彼を登用しても、韓のためにはかって、結局は秦のためにならないでしょう。またもし彼を登用しないで、そのまま韓に帰らせたら、秦の内情をもらすことになるでしょう。法に照らしてこれを処分するのが上策かと存じます」
始皇帝はもっともな理屈だと思い、ひとまず韓非を獄に下した。
獄に座した韓非は、いまさらのように法がいかに多くの仇敵をもっているかを痛感した。
かつて呉起という人が楚の宰相となり、徹底的な法治政策をとって楚を強国に仕立てあげたが、かえって楚人に恨まれて殺された。また商君は秦の孝公に仕え、これまた徹底的な法治政策をとったが、孝公が死ぬと自分の地位が保てなくなり、魏へ亡命しようとして国境まで逃げて来た。宿屋に泊まろうとすると、宿の主人はこの人が商君であるとは知らず、
「商君の法律では旅行証のない客を泊めると同罪になります」と言って断わった。商君は、
「ああ、新法もついにわが身にまで及んだか」と嘆息した。ようやく魏に逃げのびたが、魏は商君に恨みをもっているので、彼を秦に追い返した。秦の新君恵王は商君を殺し、その屍を車裂きにしたのである。
こういう先例もあるのに、まだ法の万能を主張する韓非に向かって、あるとき堂谿公(どうけいこう)が忠告したことがある。これに対して、韓非は傲然として答えた。
「なるほど、お説のとおり政治は陰険なものです。しかし、人情政治を廃して、法というコンパスを用いよと主張するのは、そうしたほうが国民の福祉に寄与すると私が信じているからです。あなたのご好意はありがたいが、かえって私の心を傷つけます」(間田)
多くの敵をもつことは、韓非にしてみれば、最初から予想していたことであった。だから敵を恐れる気持は徴塵もなかった。しかし、敵を粉砕するためには、もう一度、始皇帝に謁見して、是非を論ずる必要があった。彼は獄中からその旨を訴え出ようと努力した。
けれども李斯に妨げられてその目的を達することができなかった。李斯が皇帝からの返答だと偽って、彼に与えたのはほかならぬ毒薬である。
「もう一度、主上にお目どおりできるようお取り次ぎ願えまいか」と、最後まで韓非は繰り返した。すると、李斯の使者は声も立てずに笑った。のちに始皇帝は前意を翻して赦命を下したが、そのとき、韓非はすでにこの世の人ではなかった。
|