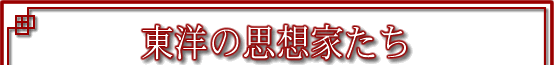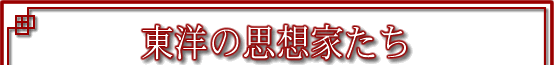|
「飼犬に手をかまれる」というのは、犬は飼主の手をかまないものという先入観があるからである。人間は権勢をもつようになると、必ず犬馬の労をとろうとする家来ができてくる。イヌは主人の顔色を見ることはなはだ敏感で、主人の好むところは、これに従って賞めそやし、主人の憎む相手は、主人にもまして、これを憎む。
人間は感情の動物であるから、好悪の情を等しくするものに好感をいだきたくなるものである。当然のことながら、そうした家来を、そうでない家来よりも信用する。ところが、犬と違って人間は信用されれば、それに乗じて、仲間を賞めたり、敵をけなしたりして、自分の利益をはかろうとするものである。うっかりそのことばを信用すれば、上の者はあざむかれ、やがて家来のほうに勢力を奪われてしまいかねない。
一国の政治がいわゆる陣笠連中によって動かされるようになれば、冷飯を食わされている連中は正しい建言を述べるのがバカらしくなり、役人は法を奉じてあくせくする気がしなくなる。
正しい意見を述べても家は貧しく、一家に危害が及ぶのに反して、うまく立ちまわって賄賂をつかい、当路の大臣に取り入って立身出世できるとなれば、だれだって「寄らば大樹の陰」ということになるのであろう。
かような為政者に対して忠誠を誓う者のいようはずがない。反主流派は必ず言うであろう。
「清廉潔白をもって上に仕えてしかも安全であろうと思うのは、コンパスを使わないで円を描こうとするようなものである。法を守って、私党を組まず、しかもスムーズに役所仕事をやろうと思うのは、足をもって頭をかこうとするようなものである。二つだに不可能だとすれば法を廃して、私利を求め、勢力家の傘下に入るよりほかない。かくて勢力家のために働く者がいよいよ多く、法をもって公のために尽くす者がいよいよ少なくなる」(姦劫弑臣)
もとを質せば、これも君主が陣笠に取り囲まれ、彼らの言に左右されることから起こる。
「楚の荘王の弟にあたる春申君には余という愛妾がいた。余は正妻が目ざわりなので、彼女を亡きものにせんと考え、自分の体を傷つけて、偽って泣いて言うには、あなたの愛妾になれたのは私の幸せですけれど、奥方様に仕えるのはほんとうにむずかしいことです。
"あなたによくしようとすれば、奥方様に悪いし、奥方様によくしようと思えば、あなたによくすることができません。このとおり、私はいまに奥方様に殺されてしまいます。奥方様に殺されるよりはいっそあなたに殺されたほうがましです。どうか私の心をお察しくださって、人様に笑われないようにしてください"。春申君は愛妾のことばを信じ正妻を捨てた。正妻には甲という息子があった。余はまた甲を殺して自分の子を世嗣にせんものと思い、自ら肌着をズタズタに破って、泣きながら訴えた。"わたしがあなたにかわいがっていただくようになってからずいぶん長いことになります。甲はそれを知らないはずもないのに、無理に私に言いよりました。ごらんください、私のこの肌着を!"それを聞いた春申君は思わずカッとなって甲を殺してしまった」(姦劫弑臣)
|