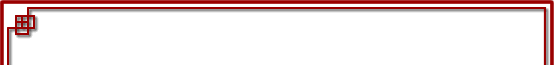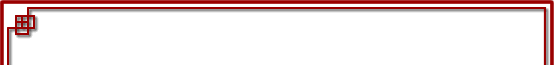|
肉親のあいだでさえかくのとおりであるから、愛などが介入する余地のない赤の他人の場合、利害関係が赤裸々な形で現われるのはむしろ当然であろう。
「医者が自分の口を病人の傷口にあてて腐った血を吸いとるのは、もとより病人に骨肉の愛をもっているからではない。病人を治すことが自分の利益になるからである。駕籠屋になれば、人の懐具合がよくなることを望むし、棺桶屋を職業とすれば、人がたくさん死んでくれたほうがいいと思うようになる。これは駕籠屋が善人で、棺桶屋が悪人だからではなくて、人が金持にならなければ、駕籠屋が繁盛せず、人が死ななければ、棺桶が売れないからである。これと同じように、皇后や太子にそれぞれの徒党ができると、君主の死を願うようになる。君主を憎んでいるからではなくて、君主が死ななければ、自分たちの勢力を伸ばすことができないからである。だから、君主は自分の死によって得をする連中を警戒しなければならない。日や月のまわりに暈(かさ)が生ずれば、賊が中にいると思うべきであって、いくら敵に備えたところで、禍は案外、愛するところから起こってくるかもしれないのである」(備内)
こうした、きわめて非情なる人間観は、マキァヴェリーの思想の根底にも流れており、
「酷薄と仁慈および恐れられるのと慕われるのといずれがまさるか」という文章のなかで、マキァヴェリーは「人は恐怖を受けている者よりも愛されている者を害うことを躊躇しない。というのは、由来愛情は人間の野卑な性質のため、義理の鎖で保たれているのであるから、いつでも都合のよいときに破られるのである」と述べている。
彼らがこうした人間観の上に立って彼らの政治理論を築こうとしたとき、彼らの敵はことごとく彼らを非人のごとく非難攻撃した。その非難攻撃が当をえていないことは、今日の政治機構がほとんどこうした前提の上に立てられていることを思い出すだけでじゅうぶんであろう。個人個人の利害関係をいかにして全体の利害関係に調和させるかが、今日の問題であり、今後の問題でもあることは明らかである。
|