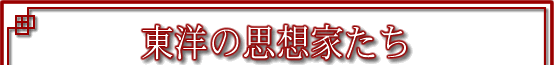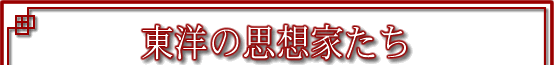|
近ごろは道徳教育の可否をめぐって議論がなかなか盛んである。道徳教育が行なわれて悪いわけはなさそうだが、それに対して反対論が起こるのは、他の学問や知識と離れて単独に道徳教育が可能であるかどうかという疑問と、もう一つは道徳教育の内容いかんという疑問によるものと思われる。
現に戦前には、修身科というものがなんの不思議もなく存在していたから、独立科目として道徳教育が技術的に可能なことは論をまたないが、要はその内容とその効果のいかんにあるであろう。
そこで、かつての修身教育が処世上どの程度の役にたったか――私は雑誌や新聞あたりで一度、各界の人士に聞いてみるようなプランをたてればおもしろいと思っている。その場合にはなるべくなら悪の世界をくぐりぬけてきたような人々に聞いてみるほうかいい。
おそらくきわめて皮肉な結論が出るのではあるまいか。
利已主義が人間に本質的なものだとすれば、愛もまた人間性に根ざしたものである。教えられなくとも、人は人を愛する。ロメオがジュリエットを愛するためには、遊郭に通って愛の手ほどきをしてもらう必要があったであろうか。それと同じように、道徳もまた教えれば守られるというものではない。もし道徳教育によって人間を改善できるものならば、セネカのような偉い先生の門下にネロのような暴君が現われるはずがないであろう。
韓非は、徳の力がこの世の中でどの程度の威力をもっているかを、次のような例を引合いにだして示そうとする。
「孔子は天下にその名を知られた聖人である。修業を積み、人間の進むべき道を明らかにし、諸国を遊説してまわった。人々はその仁を喜び、その義を美しいとしたが、彼の教えに服して門弟となった者はわずか七十人にすぎない。これを見てもわかるように仁義の信徒ははなはだ少ないのである。諸君!この広い天下に彼の教えに従った者はたったの七十人、しこうして仁義を行なう者はたったの一人にすぎなかったのである。しかしその孔子が仕えた魯の哀公は君主としてもきわめて凡庸な君主であったにもかかわらず、南面して王様となると、国じゅうの者がみなその臣となった。人民はもとより権勢に服するものである。逆にいえば、権勢があれば、(徳がなくとも)人民を服従させることができる。
それゆえに孔子がかえって臣となり、哀公が君主となったのである。
もちろん、孔子が義になついたのではなくて勢力に服したまでのことである。もし義を問題とするならば、孔子が哀公に服するはずがなく、勢いに乗ずれば哀公といえども孔子を臣とすることができるのである。ところが今日の学者先生は、必勝の勢いに乗じてはならん、王たるものはすべからく仁義を行なうべし、と説いている。これは君主に孔子になることを要求し、世の凡民をことごとく使徒に仕立てるようなものであり、算術を知らない屁理屈というよりほかない」(五蠧)
しかも、その場合、道学者先生は必ずと言っていいほどむかしの仁徳ある君主の善政を引合いにだす。大むかしの世の中は人間が少なくて野獣が多かった。そこで獣や虫や蛇から身を守るために、知恵のある人間が出て木の上に巣を作ることを考えだした。次に人間が果実や蛤や生肉を食べて胃腸を害するので、また知恵のある人間が出て、火を使うことを教えた。中古になると、人民は水害におびえたので、禹の親子が出て治水工事を起こした。近古になると桀王や紂王のような暴君が出たので、湯王や武王のような聖王がこれを討伐した。
もし中古に至って巣を作ることやものを煮ることを提唱するものがあれば、禹父子に笑われるであろうし、近古になってから治水をうんぬんすれば、湯王や武王に笑われるであろう。それと同じように、いまの世に堯がどうしたの、舜がどうしたの、と言いたてれば、新しい聖人に笑われるにきまっている。むかしはむかし、いまはいま。
むかしはたんぼを耕したり、化学肥料を使ったりしなくても、人間は食っていくことができた。獣の皮をはいで自分の身につければよかったから、女工哀史などの起こる心配はなかった。また人間の数が少なくて、物資があり余ったから、集団を組んで賃金闘争をする必要もなかった。
そういう時代には、法律はおそらく必要でなかったであろう。おそらく徳の仁のとタワゴトを並べたてる必要もなかったであろう。けれどもマルサスの予言したように、人口は幾何級数的に増加してゆくのに、食糧は算術級数的にしか増産されないから、ひとり日本のみならず世界じゅうが「満員電車」のようになってしまう。ぐずぐずしていたら職からあぶれ、飯の食いあげである。そして職にありついてもサラリーの安いことが、とかく夫婦喧嘩の原因になり、自分の力ではとうてい自家用車に乗れそうにないことが、ロマンス・グレーを女にもてさせる原因となる。こうした時代には当然こうした時代にふさわしい政策が考えられるべきである。ところが、相も変わらずむかしの夢を追う人間があとを断たない。
「宋の国に百姓がいた。その耕すたんぼに木の切り株があった。あるとき、兎が走ってきて、株にぶつかって頓死した。そこでたんぼを耕すよりも、株を守って兎を待つほうがよいと考え、鋤を捨てて、国じゅうの笑い者になった。先王の政治を当今の世の中に復活しようと考える者はみな、守株待兎のたぐいである」(五蠧)
|