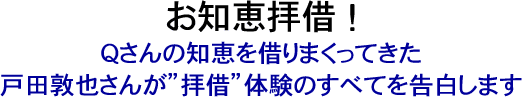|
第659回
“死ぬまで現役”に挑戦したいものです
邱さんは『ダテに年をとらず』の中で
「生きている限り現役を続ける」と宣言し、
つづいて『死に方・辞め方・別れ方』で
「死ぬまで現役が最良の健康法」
と書きました。
そして“死ぬまで現役”という言葉を
そのまま題名にした本を刊行するに至ります。
ひとつの思想が時間をかけながら誕生し、
そして成長していくことがわかります。
さて、この一連の著作のうち
『死に方・辞め方・別れ方』と
『死ぬまで現役』の二冊には
“死”というふだん人が口にするのを
さける文字が刻まれていますが、
邱さんは平成5年に刊行した
『みんな年をとる』で、時の経過とともに、
これらの著作に対する世間の扱い方も
変わってきたことを紹介しています。
「『死に方・辞め方・別れ方』を書いた時は、
さすがにまだ馴染みが薄かったと見えて、
敬遠する人が多く、本も爆発的には売れなかった。
装丁した人も、字をわざとかすれさせたり、
カラーを避けて墨の色だけを使ったりした。
しかし『死ぬまで現役』を書くようになると、
老齢化がすすんで
死に直面することになれたと見えて、
もう死という字を忌み嫌う人はうんと少なくなった。
今でも新聞を見ると、『生涯現役』と
奥歯に物の挟まったようなタイトルを
つけているのにぶつかるが、
現実を直視する勇気のない人と
話をしているような気がして、
あまりピンと来ない。
死ぬものは死ぬにきまっていて、
死ぬっきゃない、と
正面から死と取り組んだ方がいいように思う。
自分がそういう角度から人生を見ているので、
死ぬことは日常の話題だし、
また死を話題にすることをおそれない」
(『みんな年をとる』平成5年)
さて邱さんが創り出した
“死ぬまで現役”という言葉は、
誰の心のなかにも潜在している願望を
表明しているように思えます。
私は自分のセミナーに参加いただいた人たちに、
この言葉にあやかって
死ぬまで、自分の近況を話すことを続けませんかと、
呼びかけましたが、
同好の士がいらっしゃるかぎり、
続けていきたいと考えています。
|