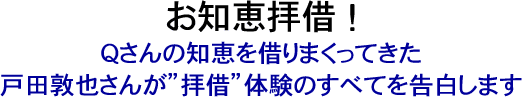|
第275回
「『知足』を体現したのはアンドリュー・カーネギー」
邱さんが最近作『デフレに強い知的金銭生活』で
『知足』という処し方が大事だと書いていることを知り、
バブル勃興を控えた頃に書いた著作でも
「知足」の考えが大切だと述べた文章を再読しました。
ついでにこの際、
「知足」という考えの由来を確かめておこうと思って調べると、
「知足」はお釈迦さまが臨終の際の説法で
説いた教えであることを知りました。
中国の老子の教えの中にとりいれられている
考えであることも知りました。
また江戸時代の学者で「養生訓」を書いた
貝原益軒も重視した考えでもあるんですね。
そうすると『知足』は東洋の人生哲学の教えか
ということになりますが、邱さんは57、8年に執筆した
『金銭処世学』で『知足』は
西洋の人たちの生き方にもある考え方で、
この考えを具現した人として
アンドリュー・カーネギーを挙げています。
「このこと(「知足」)を最も見事に体現したのは、
アンドリュー・カーネギーで、
カーネギーは郵便配達の少年からスタートして、
鉄道会社に勤め、橋梁会社の社長になり、
遂にアメリカの鋼鉄王として
世界的な大資産家にのしあがった。
しかし、カーネギーはそうした自分に甘んずることなく、
満60歳になると、
『これまでお金儲けをしてきて、
幸い、神の恵みにより財産を築くことができたが、
これからはその財産を投じて世の中の役に立つことをしたい』
といって、全財産を処分し、当時のお金の5億ドルで
カーネギー財団をつくって、慈善事業、
社会事業に残りの生涯を捧げた。
有名なカーネギー・ホールやカーネギー工科大学も
その一端を物語るものであるが、
アメリカに行くと、どんな片田舎にも、
カーネギー図書館というのが今に残っている。
あれだけの成功と、あれだけのお金の散じ方は
誰にでもできることではないが、
西洋人も西洋的な『知足』の精神があることを
私たちに教えてくれる。
やはり自分の欲望を自分なりにコントロールできることが、
金銭を追求しながら、金銭の奴隷になり下がらないですむ
最も賢い生き方ということができよう」
と邱さんは『金銭処世学』を締めくくっています。
「知足」という考え方も、洋の東西を問わず、
またいつの時代にも通用する思想なんですね。
|