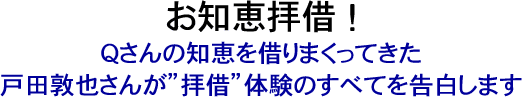|
第268回
「上海B株の上昇は予想できたことです」
平成12年から13年にかけてのことだったと思いますが、
中国のB株が急ピッチで値をあげたことがありました。
そのときのことを邱さんは次のように書いています。
「最近の日本の株式市場は
長期にわたって繁栄してきたアメリカの株価が
下降線をたどりはじめた影響もあって、
バブルのあと、最悪の水準に落ち込んでいる。
商売も駄目、不動産も駄目、その上に株価の低迷が重なれば、
企業も個人もなす術を知らないのが現状である。
そうしたピンチを尻目に、
中国では上海でも深 でもB株が連日、 でもB株が連日、
ストップ高を繰りかえしてきた。
いま時、こんな異常現象があっていいのか
目をこすりたく現象が起こっているのである。」
(『デフレに強い知的金銭生活』)
なぜこうした現象が起こったのでしょうか、
邱さんの説明を聞きましょう。
「ではどうしてこんなことが起こるのか、
また起こることが予想できたのか、というと、
このことは何年も前から予想できたことなのである。
そもそも中国にA株とB株という
二種類の株が上場されたのは
10年前までさかのぼることができる。
10年前、上海と深 の2箇所の証券取引所が開設された時、 の2箇所の証券取引所が開設された時、
中国は外貨の不足に悩んでいた。
為替は国によって統制されていたが、
政府には産業界が外国から
設備や機械を購入する外貨を提供するだけの実力がなかった。
そこで、上場企業が自分らで外貨を調達できるように、
自国民に人民元建てで売り出すA株のほかに、
上海B株はドル建てで、深 B株は香港ドル建てで B株は香港ドル建てで
公募することを許可した。
A株もB株も1株当たりの額面は同じ1元だから、
最初の頃は人民元と外貨が違うだけで株価はほぼ同じだった。
B株を発行して外貨を調達できた上場企業は
自社の保有する外貨を自由に使用できたから、
設備の近代化には大いに役立った。」
(『デフレに強い金銭生活』)
しばらく邱さんの話に耳を傾けましょう。
|