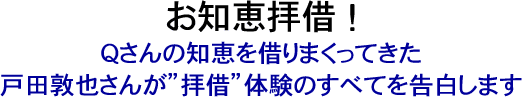|
第227回
「“夫婦同時死亡時マニュアル”はバージョン・アップします」
自分が持っている財産を子供たちに配分する案がきまると、
ついでに相続税はどんな具合になるか興味が湧いてきます。
これまで相続税についても
すこしばかり勉強したことがありますが、
この際、必要な知識を、確かめておこうという気になって、
本を読み直し、また、所定の用紙をもらいに税務署に行きました。
税務署に行き、用紙をお願いすると、
職員の人から「どなたが亡くなられたんですか」、
ときかれましたので、「いや私が死ぬのです」
と答えると、職員の人は狐につままれたような顔をしました。
それはともかく、ニワカ仕込みで
葬式の出し方、子供たちへの遺産の配分案、
そして相続税の計算方式の三部作からなる
“夫婦同時死亡時対応マニュアル”ができあがりました。
つくっただけで棚に置いておくだけでは用をなしません。
我が家には長男と二人の娘がおり、
長男は離れたところに住んでいますが、
二人の娘は家から職場に通っています。
そこで、長女ついで次女と順に声をかけ
都度、妻も同席させて、この三部作を説明しました。
親が死ぬ話ですから、子供たちも何事がおこったかと
いささか緊張気味でしたが、一応の説明をし、
そのあと書類のありかも子供たちに教えて
私と妻は旅に出ました。
世間には「不吉なことを口にすると口にしたことが
起こってしまう」という言い伝えがありますが、
実際はそんなこともなく、私と妻は
気持ちをリフレッシュして返ってきました。
幸いにして旅行に行く前につくった
“夫婦同時死亡時マニュアル”
の出番はなかったのですが、
実際にこれを作った効用がないではありません。
一つは自分の家の経済実態が
子供たちにもよくわかったということです。
もう一つは、親に対する孝行の度合いで、
財産の配分を逐次見直し、都度、
バージョン・アップするよと
子供たちに親孝行を奨励する口実ができたことです。
もっとも、その次に旅行に出るとき、
前回作成した資料に少し手を入れて説明したところ、
初回のときは緊張気味にきいていた娘たちも
「ああ、アレか」ときき流すような風になり、
効用はかなり薄れかもしれませんが。
|