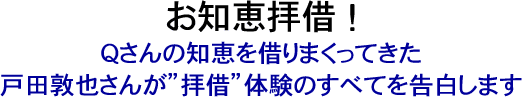|
第221回
「マキシムのリスクをミニマムにする」
邱さんが本や雑誌でしばしば対談し、
邱さんの作品の解説も書かれておられる方に
唐津一さんという人がいます。
この唐津一さんがPHP新書として出版した
『かけひきの科学』(平成8年)とか
『ビジネス難問の解き方』(平成14年)のなかで
「ミニマックスの原理」について解説しています。
「不確実性のリスクに備えるための提案されたのが、
『ミニマックスの原理』というものである。
これは、ノイマン型と呼ばれる
現在のコンピュータの原理を考えた
数学者のジョン・L・フォン・ノイマンと
経済学者オスカー・モルゲンシュタインが体系づけた
『ゲームの理論』のなかの重要な戦略の一つである。
解決策の選択肢がいくつかあり、
状況の変化や競争相手の出方を予測して、
そのどれを選ぶかというときには、
成功した場合のことばかり想定して、
最適案をえらぶのがふつうである。
たとえば、Aという状況下ではX案で行けばいい、
状況がBに変わればY案で行くのが有利だといった具合である。
しかし、競争相手も合理的に予測し、
こちらの手の内を見抜こうとしているわけだから、
そう都合よくいくとは限らない。
最大利益を追求して予測していると、
まかり間違って予想外の方向に転んだときにはお手上げで、
逆に最悪の損害をこうむりかねない。
そもそも問題解決における決断には、
二種類の不確実性を考えておかなければならない。
一つは、競争相手がどんな手を打ってくるか、
あるいはこちらの手の内が読まれているかがわからないという、
かけひきに由来する不確実性である。
もうひとつは偶然性という不確実性が存在する。
『ミニマックスの原理』はこの二つの不確実性を想定し、
それに伴うリスクを極小化するための手法なのである。
そこで成功したときに
どれだけのメリットが出るかを考えるのではなく、
それとは反対に、うまくいかなかったときに
どれだけの損失を抑えられるかを考えて手を打つ
ーすなわち、最悪の場合を想定するのが
ミニマックス原理の基本的な考え方である。
マキシムのリスクをミニマムにするというところから、
こう名づけられた。」
(唐津一『ビジネス難問の解き方』PHP新書。平成8年)
|