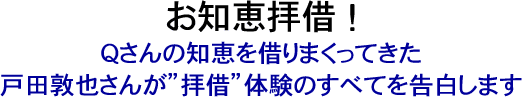|
第205回
日下さん曰く「客観的条件+主体的努力=結果」
いま評論家として活躍している日下公人さんの存在を知ったのは、
邱さんの『お金の使い方』という本でした。
この本で邱さんは日下さんの初期の作品『新・文化産業論』
という本を推奨しました。
私は早速、読み、以来、日下さんの本も出版される都度
読むようになりました。
昭和56年頃に出版された日下さんの著作に
『日本経済“やる気”の研究』という本があります。
日下さんはこの本で、物事の結果は、
当事者が置かれた状況にも左右されるが、
当事者がどういう努力をしたかによっても
大きく変わると指摘し
「客観的条件+主体的努力=結果」
という図式を示しました。
日下さんによれば、学校の先生はとかく物事を
科学的に説明しようとする性癖をもち、
人間の意欲とか努力といった不確かな要因をはずし、
当事者が置かれた客観的な条件で物事の結果が決まる、
つまり「客観的条件=結果」の要領で
物事を説明しようとするとのことです。
たとえば、私などが子供の頃、学校の先生は、
日本は貧乏な国であるという説明に
資源がないとか、周囲を海に囲まれ物資の輸送に不便だ、
といったことを要因として挙げていました。
「客観的条件=結果」スタイルの説明ですね。
しかし日本はいつのまにか金持ち国になりました。
日本が資源がなく、周囲を海に囲まれているのは
昔も今も変わりありませんが、
日本人はそのハンディを逆手にとって、
資源の豊かな国から海路、原料を仕入れ、それを加工して
付加価値の高い製品をつくりだすようにしたからです。
これを説明しようとしたら
「客観的条件+主体的努力=結果」
と表現しなければなりません。
日下さんはこの人間の「主体的努力」が重要ですよ、
これを忘れてはいけませんというために、
この図式を持ち出したのですが、
「今は駄目でも、いつまでもだめではない、
いつかは扉がひらかれる」という邱さんの言葉に
日下さんが示した図式を重ねあわせると
「今は駄目かもしれない。
しかしやる気をだして努力をするうちに、
やがてそれが実って、いつかは扉がひらかれる」
という解釈が生まれ、
理解が幾分か深まったような気持ちになりました。
それにしても私なども、学校の先生のマネをして
「客観的条件=結果」の要領で
物事を説明しようとするところがあり、
これは要注意だと自分を戒めているところです。
|