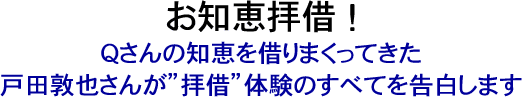|
第189回
「変化に敏感に反応することです」
時流の先を読むための要件として、
邱さんは世の中を動きに好奇心を働かせるとか、
問題意識をもって観察力を働かせることと並んで
「変化に敏感に反応すること」を挙げています。
『金儲け発想の原点』に記載されている
「問題意識を持って変化の先を読む」からの引用を続けましょう。
「私は『変化』という流動的な要素を重視している。
変化がなければ、金儲けのチャンスもなければ、
出世のチャンスもない。
本能寺の変がなければ、
秀吉にも天下をとるチャンスはなかっただろうし、
秀吉が死ななければ、関が原の合戦もなかっただろうし、
家康が徳川三百年の礎を築くこともできなかっただろう。
変化にはそれぞれ継ぎ目というか、分岐点というか、
それが分かれ目になるところがある。
たとえば、中国大陸では中国共産党の天下になって
40年が経過している。
毛沢東は天下をとることには成功したが、
国民を豊かにする生産体制を確立することはできなかった。
毛沢東の死後、 小平が四人組を追放することに成功し、 小平が四人組を追放することに成功し、
胡耀邦、趙紫陽、万里のような柔軟な頭脳の持ち主を
起用することによって、あるていど自由市場を復活させ、
ともかく11億人が腹を空かせないでやっていけるところまで
辿りついた。
ここが中国の次の継ぎ目、分かれ目になるところである。
『人はパンなくして生きられないが、
パンのみにて生きるにあらず』
とでもいえばよいのであろうか
この次は、生産をふやして国民水準を上げなければならないことは、
いくら中共の老幹部たちでも理解している。
そのために開放政策が必要なことも、
外国の資本や技術を導入する必要のあることもわかっている。
またそのために人材の養成をしなければならないことも、
外国に学生たちを留学させなければならないことを納得している。
だからこそそのいずれも実行したのである。」
(「問題意識を持って変化の先を読む」。
『金儲け発想の原点』《平成2年》に収録。)
かねがね思っているのですが、仮に邱さんの文章のなかで
頻繁に使われる二字の単語を調べるとしたら、
この「変化」という二字の言葉がかなりランクの高いところに
並ぶのではないかと思っています。
|