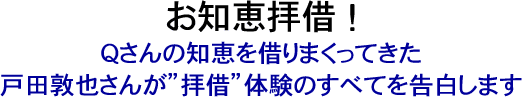|
第105回
ご自分の本をお書きになりませんか
私が予定の時期に『新・メシの食える経済学』の原稿を
届けましたら、グラフ社の中尾社長が待っておられました。
そして、私に自分自身の本を書くことを強く勧められました。
実は自分自身の本を書いてみないかという勧誘は
『原則がわかれば生き残れる』を編集した頃からあり、
私は本を読むことは得意だけど、自分で本を書く力はありません。
ただ邱さんの本のことなら
かなり詳しいという技能をもっているので、
この面でお役に立たせてもらいますといい続けてきました。
ということで私自身が本を書く話はあきらめていただいている
と思っていたのですが、少し買いかぶられたのでしょうか。
中尾社長から、再度お誘いの言葉をいただいたわけです。
数えれば最初にお誘いを受けてから、8年ばかりの年月がたち、
今回のご要望には以前にない熱のこもったものがありましたので
何かを書かないと、ことが収まらないような雰囲気がありました。
「いまは経済の様相がすっかり変わりました。
最近、某ゼネコンが銀行から借りていたお金を
銀行が棒引きするということがありましたが、
借りたお金を返さなくていいなんていうことは
昔にはなかったことですね。
今の経済はいわば『異形の経済』です。
そういうことがわかる本を書いてみませんか」
と中尾社長は言われました。
私もいま経済が大きく変わっていることに気づいていますし、
アジアを代表する超一級の経済通である邱さんの本を
ずっと読んできています。
ただ、自分が経済のことについて書くとしたら、
邱さんが書いていることの要約版のようなものや、
独自性のある文章は書けないのではないかと危惧しました。
そこで中尾社長からの再度の誘いかけに対して、
私は首を縦に振りませんでした。
そのとき、常務の西澤昌司さんも同席しておられて、
中尾社長からの話が終わったあとも
西澤さんは私を離さず、
どうしても本を執筆させようという腹でした。
私が首をふらないので
「戸田さんが自分で書きたいと思うテーマでいいから
書いてみたらどうでしょう」ともおっしゃいました。
そういわれると私に、書きたいテーマがないわけではありません。
私は会社に入って10年ばかりたったころで
「定年」の存在を意識するようになり、
このハードルをどう越えていくかを考えつづけてきました 。
考えるだけでなく、行動にも移してきたところがあります。
このテーマなら、自分自身、
時間をかけて取り組んできたことだし、
ざっと数えてもやってきたことがいくつか思い出されます。
そういう体験を文章にしたら、後輩にあたる人たちにも多少、
役に立つところがあるのではないかと考えました。
|