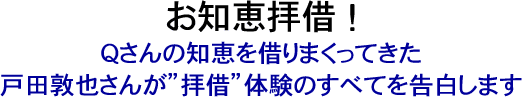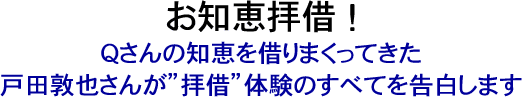| 第65回
家にお金がないことを教えよう
小さな子供が
親も想定していなかったようなことをするような事件が
しばしば起こるようになっています。
時代、時代で子育てのテーマに変化があるようですが、
子育てが親にとってゆるがせにできない重要事であることは
いつの時代も変わりがありません。
私たちのところでも、長男の頭に2人の娘がいて、
私などもある時期、子供の教育に頭を絞った時期があります。
ちょうどその頃に邱さんが
3人のお子さんを育てた体験にもとづく
『子育てはお金の教育から』という本を出版しました。
この本で邱さんは我が家の教育基本法は
「金銭上のことで他人に迷惑をかけないこと」と
「あの家の子供は礼儀知らずだと言われないようにすること」の
2ヶ条だけだと書いていました。
そして自分が実際に行ってきた子育ての体験を書き、
またそれらに基づいて幾つかの提言を書いています。
その一つに「家にお金のないことを教えよう」というのが
ありました。
「家にお金があるように振舞おう」と言われても困りますが、
「家にお金のないことを教えよう」ということなら
誰しもその資格を持っていると思いました。
ただ、子供に余計な心配をさせたくないという
親心がはたらいていたせいか、
子供に家庭の事情について話をすることを避けがちです。
邱さんの場合はそれとは逆で、親の苦労は子供に見せよ、
将来起こるかも知れない心配事は子供にも
伝えておこうという方針を貫いています。
邱さんがご自身のお子さんが小さかった頃、
夕食のときにお子さんたちに向かって盛んに話したのは
「親が死ぬ話」とか「商売が駄目になって倒産する話」といった
クラーイ話だったようです。
人生には心配の種が転がっていて、
そうした心配の種を抱えつつ人間は生きているのだから、
そういうことを子供にも教えて、
日ごろから最悪の場合に備えた心構えを
させておこうということだったのでしょう。
「家にお金のないことを教えよう」としたのも
そうした考えに立ってのことだったのでしょう。
将来起こりうる不安の材料を子供に投げかけ、
現実の厳しさを伝えて子供の精神面を鍛えておこうという
邱さんの教育方針は「先憂後楽」の思想に立つものと、
勉強になりました。
|