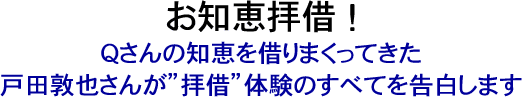| 第55回
苦しみにきたえられる中から次の対策が生まれてきます
このホームページは東京渋谷の代々木公園横にある
邱永漢アジア交流センターから発信されています。
私は、今年の八月のある暑い日、
このページの立ち上げに汗を流していた根石宣昌さんと
打合せるために、このセンターを訪ねましした。
開業に向けて、部屋の改装が進められているときでもありました。
そんなセンターの中にいくつかの書が掛けられています。
根石さんを待つ間、私は展示された書を見て回りましたが、
「成功毎在窮苦日、敗事多因得意事」
という書が飛び込んできました。
どこかで見た覚えのある言葉です。
私は家に帰り本棚から『朝は夜よりも賢い』という
本を取り出しました。
この『朝は夜よりも賢い』の「時間に勝る名医はない」という章に
「ピンチのときにどう対処するか」に関して
邱さんは「ピンチの法則」5か条を紹介しています。
「(1)ピンチというのは人生のリズムみたいなものであるから、
周期的に必ずやってくる。
用心して予防策を講じていても、避けることはできない
(2)ピンチにおちいるときは、身辺におこることが
いずれもマイナスに働くから、八方塞がりの感じになる。
(3)ピンチにおちいると、奈落の底にでもおちるような
不安に襲われるが、それは心理的なものにすぎず、
必ずどこかで底に足がとどく。
ただし、必ず一定の時間の経過を要する。
(4)ピンチの折り返し点は、恐怖におちいって想像したよりも
かなり上のところにある。つまり人間は自分で考えたところまでは、
なかなかおちこまないものなのだ。
(5)ピンチから這いあがるキッカケは、ピンチにおちいる前に
考えていたようなことからは生まれてこない。
苦しみにきたえられ、それが薬になってはじめて次の対策が
生まれてくるものである。」
(『朝は夜より賢い』)
「ピンチの法則」5か条は、邱さん自身がピンチに陥り、そして
そこから這い上がる過程で発見したことをまとめたものです。
そして「成功毎在窮苦日、敗事多因得意事」という中国の諺が
紹介されています。
「貧乏して苦しんだときに何を考えたか、
またどんな手を打ったか、がやがて成功につながっていく」と
いう意味の言葉として。
私ごとき者が自分の乏しい体験を振り返るなかで
邱さんが見つけた一大法則を引用するのはやや仰々しく、
かなり気が引けることでもありますが、
「ピンチの状態にあるときに考えたことがくすりになって、
初めて次の対策が生まれてくる」ということは
私などが体験したことからもハッキリ言えることではないかと思います。
|