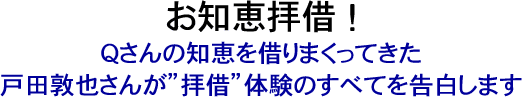| 第49回
地元の人の反応は超希薄でした
さて自分が頭に描いた事業プランが地元の人たちが
どのように受け止められるか、リサーチしてみることが大切です。
自慢ではありませんが、私はこれらの事業を企画するにあたって
外部の機関に検討をゆだねるということは一切しませんでした。
お金が使えないという事情もありましたが、
邱さんの本など読んでいると
みな自分の考えで事を進められているように見えますから、
お金があっても外の機関に検討を頼むということは
しなかったと思います。
さて、たまたま製鐵所が減産気味で人が待っているというので、
ドンドン人を使ってほしいという依頼が来ました。
そこで私は同僚の渋谷さんと相談し、
普段は現場で働いている作業長と工長さんにお願いして、
製鉄所周辺の家を訪ねてもらうことにしました。
渋谷さんは早速、これからやろうとしている事業プランの
アウトラインを書き、現場からやってきた作業長と工長さん二人に説明し、
この二人に地元の人たちの家庭を訪問してもらい、
「いま新日鉄ではこういうことを考えているがどんなものでしょうか」
と感想を聞いてもらうことにしました。
一方、私はもう少し広い範囲で世間の反応を探る必要があるとも思い、
私のところにしばしば取材に来ていた朝日新聞の経済記者の
海老坂さんにある日、自分が企画していることの輪郭を話しました。
海老坂さんは早速、私の構想を地元版の紙面でとりあげてくれました。
地元の人がどう反応するか興味津々でしたが、
この新聞記事に反応して買ってみようかと問い合わせてくれた人は
残念ながらたったの一人でした。
しばらくたってもう一人の方が現れましたが、合わせてもたったの2名です。
渋谷さんが試算してくれたマンションの事業計画によれば
部屋数は最低限でも130室が必要で、それに対して入居希望者は
2名というのですから前途多難です。
私は自分のプランに対する世間の反応が低調であることに
ショックを受けました。
そういう低調ムードが漂うなかで私は前に進むか否かの
孤独な判断が求められることになりました。
常識的に考えたら企画を白紙に戻すというのが妥当なところでしょう。
私ももし少し可能性のある事業プランを考えついたら
私はそちらの方に乗り移っていたかもしれません。
しかし事業という名に値する事業としては
このプラン以外考えられません。
東京の研究所で考えたことを製鐵所でためしに生産してみる
といった右から左に移すだけの仕事には、私自身はまったく
興味を持ちませんでした。
しかし自分の企画したプランに対する世間からの反応は
まことに厳しいものです。
そうした反応を考慮に入れてどうすればいいか考え続けることにしました。
|