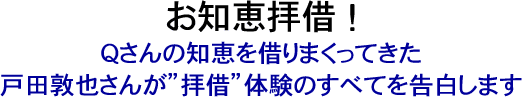| 第41回
リスクの小さな仕事は得られるチャンスも小さいことを知りました
私は会社のOBを対象にして、毎日の生活のなかに潤いをもたらすような
サービスを提供する会社の設立を企画しました。
公共機関でもお年寄り向けに色々なイベントや勉強会を実施していて、
ほとんどすべてが無料です。
そうしたサービスと似たようなサービスを有料で提供することを危ぶむ
意見がありましたので、公共機関が提供しているようなサービスは避け、
お金をいただくのに値するだけのサービスに絞ることにしました。
しかし、私は顧客へのサービスより新しい船を出すことを
優先していたように思います。
新しく世に出す会社にNTTのハローページをもじって
「ハロー・クラブ」と名づけ、私はスーパー、不動産開発、鉄の流通の
仕事をしている三つの関連会社の九州在住の担当者に打診しました。
新しい事業の誕生を待ちの望む雰囲気が新日鉄の社内に強く、
親会社の言うことだからということでついてきてくれたのでしょう。
関連会社の共同出資で資本金、1000万円、
従業員3人の小さな会社ができました。
開業にあたって設定した会費は月に1万円
といったところだったかと思います。
元々、入るお金が小額で、多くの収入が見込めない事業でしたから、
製鉄所から「ハロー・クラブ」に出向してもらう社員の給料は
新日鉄から出る給料の3割程度にとどめ、
オフィスは製鉄所の古い建物をタダで借るという条件でスタートさせました。
私はこの会社を世に出したあと、また別の事業の企画に当たることになり、
新しい企画に取り組みながら、「ハロー・クラブ」の立ち上がりを
傍から見ることになりました。
ただ企画に当たったのは私ですから、立場は変わっても、その出帆から
目をそらすわけにはいきません。
やがて私の目に入ってきたのは、会員獲得の低調さです。
製鐵所には数多くの工場があり、
それぞれの工場毎にOB会があります。
私は、工場に出かけて工場長や労務担当の人に、
OB会のネット・ワークを活用して
会員の募集を手助けしほしいと頼んで回りました。
会員の獲得には営業車が必要だという声も出て、車も購入しました。
しかし会員数は思うようには伸びません。
このように「ハロー・クラブ」は発足時点から前途多難の様相で
結末から言いますと3年目に頓挫し、
この事業は関連会社のスーパーで拾ってもらうことになりました。
私がこの仕事を通じて感じたことは
簡単にできる事業は簡単につぶれるものだということでした。
またリスクが小さくて、皆からすぐに賛同を得られる事業は
得られるチャンスも小さいことを知りました。
この事業の場合は生き続けることすらできなかったわけです。
|