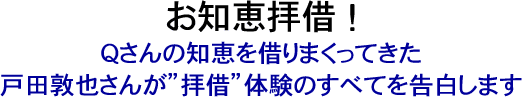
Qさんは、かつて「知恵は借り物でも知恵である」と書きました
そういうことをおっしゃる人の知恵ならいくら借りてもモンクは出ませんね
|
第30回 私の上司が赤字の事業を儲けの出る事業に切り替えた源泉は ずっと時間がたってから知ったことですが、いま多方面で ついでにいえば、邱さんがこの辺のところをどう書いているのかと思って、 |
| ←前回記事へ | 2002年9月26日(木) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
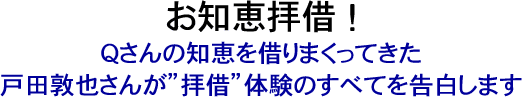
Qさんは、かつて「知恵は借り物でも知恵である」と書きました
そういうことをおっしゃる人の知恵ならいくら借りてもモンクは出ませんね
|
第30回 私の上司が赤字の事業を儲けの出る事業に切り替えた源泉は ずっと時間がたってから知ったことですが、いま多方面で ついでにいえば、邱さんがこの辺のところをどう書いているのかと思って、 |
| ←前回記事へ | 2002年9月26日(木) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |