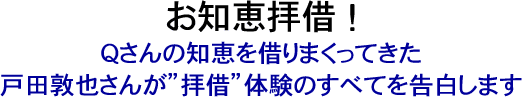|
第25回
わけがわからないままに気分が落ち込むことを経験しました
邱さんは42歳と55歳の二つの厄を経験しました。
このうち55歳の厄とは日本の選挙に出たことで、
ジャーナリズムが政治に踏み込んだ人間に警戒的で、
邱さんもじっとしていたら、作品発表の舞台を失うのではないかと
心配したそうです。
そこで、生き残りを賭けて、「香港の挑戦」とか「海外投資」とか
「経済一等国日本」の作品を矢継ぎ早に書き続けたのだと
あとになって教えられ、なるほど、そうだったのかと納得したことでした。
さて、「厄年」とは「災難にあう年齢」という意味ですね。
私がこの言葉を耳にしたのは子供のころで
オトナたちがしばしば「厄年」とか「前厄」、「後厄」という言葉を
使っているのを耳にしていました。
私にはオトナたちが「迷信」話をしているようにしか聞こえませんでした。
会社に入り、人身事故が続いたりすると、労務部長が安全課長に
「厄払いに行こうや」などと、「厄」という言葉を使うのを耳にしました。
この「厄」という言葉にもなにか迷信じみた響きを感じ、
「厄」とか「厄年」は「死語」に近い言葉ではないかと思っていました。
ところが邱さん自身が人生の節々で、
気分が落ち込み憂鬱になった体験を開陳し、
それを「厄年」の現象であった解説するに及び、
「迷信」だとか「死語」だとかで
片付けるわけにはいかないと思うようになりました。
そして、何よりも私自身がわけのわからないままに
だんだん気分が落ち込み、ある時、あれが
「厄年」の現象だったのだと思うようなことが起こったのです。
君津製鉄所の課長に赴任してしばらくのことです。
職場は活気がありますし、我が家も平穏です。
後半期の人生に備えた手も打ってきています。
にもかかわらず、なぜか、仕事に熱を注げなくなったのです。
夜になると私は高台にある社宅のベランダに出て、
ボーと外を見て、もの思いに耽ける毎日が多くなりました。
私がこの心に起こった変調が
「厄年」現象であったらしいと気づいたのは、
あとになってからのことですが、邱さんが
「厄年というのは、なんとなく先が見えてくることと関係があるようだ」
(『貧しからず 富に溺れず』。昭和60年)と
指摘している文章に出会ったからです。
|