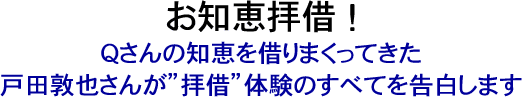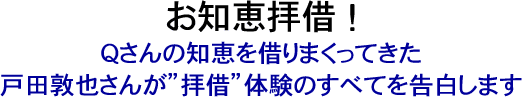|
第3回
30代半ばの私は、自分の将来のことを考え頭を痛めていました。
はじめて邱さんの文章に触れた頃,
私は新日鉄の本社に努めていました。
勤務先は労務部門でした。
本社に来る前、私は大阪府の堺市と、
北九州市の八幡にある二つの製鉄所で合計12年の年月を過ごし、
気分的には至ってのんびりした生活を送っていました。
ところが東京の本社で仕事をするようになり、
かなり憂鬱な気分になっていました。
一つは「定年」の存在に気づき、
この問題をどう乗り越えるか見通しがつかなかったのです。
当時、私は30代半ばでしたが、
私の上長について皇居前にある日経連に行きました。
私の上司が日経連の人事部門関係の特別委員会のチェアマンになり、
私はその上司のカバン持ちでついて行ったのです。
『高齢化と高学歴化にどう対処するか』
というテーマの委員会で、
半年後に一定の方向を打ち出すことが予定された会議でした。
当時、第二次石油ショックの嵐が吹き荒れ、
今の「リストラ」に相当する「減量経営」
という言葉がハヤッていました。
定年が当時は55歳が普通で、年金を貰えるのが60歳で、
このギャップを埋めるために
定年を60歳まで延長することが期待されていました。
しかし、各社ともピンチな状態に陥っていて、
定年延長どころの話じゃないよという雰囲気でした。
そして、会議の場では、
定年を迎える前後の高齢者の処遇が話題になりました。
この委員会に集まっていた人事関係の課長さんたちが
口をそろえて言っていたのが
「ホワイトカラーは年をとってからの処遇が難しい。
プライドは高いのだけど実力が伴わない。」
という話でした。
私は耳を傾けながら、
「ああそうだ、サラリーマンには定年があるんだ。」
「自分だって定年の年になったら
会社とオサラバしなければいけないんだ」
ということに気づきました。
というのも私の親戚縁者みな自営業者で、
私の選んだ人生コースに定年があることがピンときていなかったのです。
|